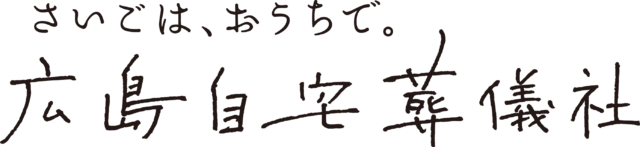お寺に法事を頼む電話のマナーやタイミングを紹介
更新:2025.11.03
一周忌や三回忌など、人が亡くなると定期的に法事が発生します。
このとき「法事の依頼は、電話では失礼?」
「菩提寺には、どのくらい前に依頼すればいいのだろう?」と迷う人もいるでしょう。
法事の依頼は、電話が最も適しています。
お寺に法事を頼むときの電話のマナーやタイミングについて、詳しく解説します。
目次
お寺に法事を頼む場合は、電話が適している
法事は、亡くなった方を供養する大切な儀式です。
そのため、「直接お寺に出向いてお願いするのが礼儀ではないか」と考える人は少なくありません。
しかし現代では、電話での依頼が一般的です。
お寺側もスケジュールを確認する必要があるため、突然の訪問よりも電話連絡を歓迎する場合が多いでしょう。
お寺のメールアドレスやSNSを事前に知っていて、常にそれらの手段でやりとりするほど仲が深まっている場合は、メールやSNSでも問題はないでしょう。
しかし、そのようなやりとりもないまま、お寺のHPにある「お問い合わせ」欄へ法事の問い合わせをするのは控えましょう。
日頃メールなどでやりとりする間柄でなければ、まずは電話をして、檀家としてお世話になっていることを伝えた上で、法事の申し込みをします。
法事を依頼する電話はいつかければいい?
法事を依頼する電話をかけるのは、希望する日の2ヶ月から1ヶ月前あたりが理想的です。
法事の1ヶ月前までには、参加してほしい人に案内状を出す必要があるため、お寺には早めに連絡を入れて日程を確定させましょう。
ただし、お寺には繁忙期があります。
お盆とお彼岸です。お盆の時期は初盆供養のための法事が立て込んだり、お寺で一斉法要があったりします。
お彼岸にも、やはり一斉供養の催しがあったり、お祭りがあったりなど、お寺は大変な時期です。
お盆やお彼岸に法事を行いたい場合、連絡が遅れると良い日程が取りづらくなるおそれがあります。
もし法事を行いたい時期がお盆やお彼岸に当たるようなら、2~3ヶ月前にはお寺に電話しましょう。
お盆は毎年8月12日から8月16日で、一部地域では7月12日~7月16日となります。
春のお彼岸は春分の日を中日とした1週間で、例年、3月中旬です。
秋のお彼岸は、秋分の日を中日とした1週間で、9月中旬から下旬です。
お寺に電話をかけて良いタイミングは?
お寺に電話をかける場合、一般的な家庭と同様、緊急でなければ早朝や深夜帯は避けましょう。
学校の先生などと兼業している僧侶もいるため、兼業の内容を知っている場合は、仕事の時間帯を避けます。
また、土日の日中は法要が入っている場合が多いため、避けた方がいいでしょう。
平日の日中か、土日の夕方以降に電話をかけるのがおすすめです。
もしご住職自身が電話に出られない場合でも、奥さまなどお寺の中の方に伝言をお願いできます。
「自分が折り返しの電話に出られないかも」と不安があれば、留守番電話に連絡内容を吹き込んでもらえるよう、お願いしておきます。
お寺への電話で伝えるべき内容

法事を依頼する電話では、以下の情報を整理して伝えることが重要です。事前にメモしておくと、電話中に抜けや間違いが生じず、スムーズに依頼できます。
・施主の名前
・亡くなった方の戒名・俗名
・回忌(1周忌、三回忌など)
・法事の希望日程(候補を複数用意しておくとスムーズ)
・参列予定人数・会場の相談(自宅か寺か会館か)
・会食の有無(僧侶は参加可能か)
・施主の連絡先
なかには、次のようなことが気になっている人もいるでしょう。
初めて電話するときに余裕があれば、この機会に尋ねておくと安心です。
・用意するもの(位牌、納骨も含む場合は骨壺、供物、花束、数珠など)
・服装の相談(七回忌以降など、喪服が良いかどうか迷う場合)
・自宅で法事を行う場合、僧侶の交通手段(お迎えに上がるか、その必要はないか)
・お布施の金額(お寺側で取り決めなどがあるか否か)
お寺から「卒塔婆」について聞かれた場合の対応
法事の依頼をすると、お寺側から「卒塔婆(塔婆)は何本立てますか?」と尋ねられることがあります。
初めて法事を依頼する人は、きっと戸惑うことでしょう。
卒塔婆(そとば)、あるいは塔婆(とば)とは、故人の供養のためにお墓へ立てる長い木の板のことです。
古くはお釈迦様の遺骨を納めた塔(仏塔)という意味を持ち、法事の節目に追善供養としてお墓の後ろへ立てます。
1回の法事につき1本の卒塔婆を立てるのが一般的ですが、兄弟の数だけ立てるケースもみられます。
特にこだわりがなければ「1本でお願いします」と答えて良いでしょう。
卒塔婆の料金は、一本あたり数千円が相場です。
なお、浄土真宗など、卒塔婆を立てない宗派もあります。
その際は、卒塔婆について聞かれることはありません。
電話対応のシミュレーション
お寺の固定電話に法事の依頼をすると想定して、電話対応のシミュレーションをご紹介します。
【ご住職が電話に出られる場合】
「もしもし。檀家の○○と申します。
いつも大変お世話になっております。
法事をお願いしたくてお電話しました。
ご住職はいらっしゃいますか?」
(ご住職が電話に出る)
「こんにちは、○○です。
▲▲(故人)の葬儀につきましては、大変お世話になりありがとうございました。
一周忌が近づいて参りましたので、法事をお願いしたくてお電話しました。
○月×日か、その次の週あたりの午前中、ご都合はいかがでしょうか?」
(日程が決まる)
「それでは、その日程でお願いしたいです。
法事の会場は、私どもの家でもよろしいでしょうか。
お迎えに上がりましょうか、それともお車で来られますか?」
「法要の後、会食を予定しています。
ご参加いただくことはできますか?
それとも、お持ち帰りのお弁当をご用意した方がよろしいでしょうか」
(やりとりがあって)
「ありがとうございます。
それでは○月×日の日曜日、午前11時から○○家での法要をよろしくお願いします。
もし何かございましたら、私の携帯電話までお電話ください。
番号は○○○です。」
【ご住職が電話に出られない場合】
「もしもし。檀家の○○と申します。
いつも大変お世話になっております。
法事をお願いしたくてお電話しました。
ご住職はいらっしゃいますか?」
(住職不在を告げられる)
「そうですか。
それでは、時間を改めてお電話します。
何時頃がよろしいでしょうか?」
(伝言を受けてもらえる場合)
「ありがとうございます。
それでは、○○より、▲▲(故人名)の一周忌法要について電話があった旨をお伝えください。
法事の希望日は、○月×日か、その次の週あたりです。
私の電話番号は、○○○です。
電話に出られない場合もあるかもしれませんが、その場合は、留守番電話に伝言いただければ嬉しいです。」
電話依頼をした後の対応
電話で法事の日程が決まったら、以下の手配を行いましょう。
決まった日程を家族や親戚に共有する
正式な案内状を送る前に、家族や主な親戚には日程を簡単に知らせておきます。
会食会場の決定
会食を行いたい料亭などに、予約を入れます。
人数はまだはっきりとは決まらないため、だいたいの人数で押さえておきましょう。
正確な人数が決まったら、速やかに会場へ伝えます。
案内状の作成
法事の日程や会食の有無を盛りこんだ案内状を作成します。
喪服での参加ではない場合は、「平服でお越しください」と忘れずに加えましょう。
案内状は、法事の1ヶ月前を目安に出します。
参加の可否の連絡は、2週間前までに受け取れるようにしましょう。
法事の依頼は電話で行おう
法事をお寺に依頼する電話は、失礼ではありません。
むしろ、事前に日程や必要事項を整理して丁寧に伝えることで、円滑に準備を進める第一歩になります。
「電話で頼むのは不安」という気持ちになる人もいるかもしれませんが、この記事のシミュレーションを参考に、最低限のマナーと聞きたい情報を押さえて電話してみましょう。

この記事を書いた人
奥山 晶子
葬儀社への勤務経験、散骨を推進するNPO「葬送の自由をすすめる会」の理事の経験、遺品整理関係の著書・サイト制作サポートなどから、終活全般に強いライター。ファイナンシャルプランナー(2級)。終活関連の著書3冊、監修本1冊。最近の著書は「ゆる終活のための親にかけたい55の言葉」オークラ出版。ほか週刊現代WEBなどサイトへの終活関連コラム寄稿、クロワッサン別冊「終活読本」の監修や、令和6年5月発刊「ESSE」6月号のお墓特集を監修している。