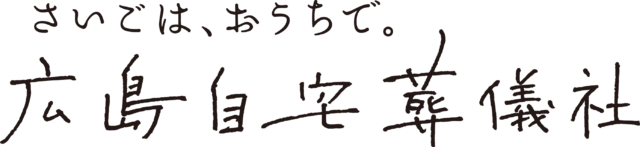後飾り祭壇はいつまで使うもの?ずっと使い続けてもいい?
更新:2025.05.20
葬儀を行った後、自宅に遺骨や遺影を飾るとき、多くの人は「後飾り祭壇」を葬儀社から購入して使用します。
この後飾り祭壇は四十九日法要が終わったら解体し、処分するケースがほとんどですが、ずっと使い続けても構いません。
後飾り祭壇の意味や使用期間、使用する際の注意点、処分の仕方などについて解説します。
後飾り祭壇は自宅に遺骨などを安置するための簡易的な祭壇
後飾り祭壇とは、葬儀が終わった後、遺骨や遺影、位牌を一時安置してお供えをするための祭壇です。
木でできていることはまれで、ほとんどの場合は白い段ボールで作られており、白い布を被せて利用します。
段ボールに白い布をかけた祭壇は、かなり簡素な姿です。
しかし、この簡素さが「まさか亡くなるとは思わず、取り急ぎ簡素な祭壇を作った」というメッセージになるとされています。
黒塗りの立派な祭壇を使っては、まるで不幸を予見し、前もって準備していたかのようだからです。
自宅に仏壇がある場合でも、葬儀後しばらくはこの後飾り祭壇を使い、ご先祖様と分けて供養します。
なぜなら、亡くなってから日にちの経たない故人はまだ「仏様」になれておらず、霊としてこの世をさまよっている存在なので、仏様として仏壇にまつってはならないという考え方があるためです。
後飾り祭壇は、基本的には四十九日法要で役目を終える
後飾り祭壇を使うのは、四十九日法要までとされています。
四十九日法要の日には納骨を済ませ、後飾り祭壇を処分し、故人の位牌や小さな遺影を仏壇へ安置します。
大きな遺影は、他のご先祖様の遺影と並べて、壁などに掛けられる場合もあります。
これは、亡くなって49日を過ぎると故人の霊はさまようのをやめ、仏の世界へ行くとされているためです。
仏となった故人の位牌は仏壇におさまり、やっと「ご先祖様」の仲間入りができます。
後飾り祭壇はいつまでも使って良い
以上のように、後飾り祭壇は多くの場合、四十九日法要をめどに片づけるものですが、「49日を過ぎたら使ってはならない」というものではありません。
いつまで使っても良いものです。
例えば以下のような場合は、後飾り祭壇があると便利です。
四十九日法要までに仏壇が間に合わない場合
四十九日法要までに仏壇が届かなくても、法要自体を後飾り祭壇で行うことは可能です。
自宅ではなく、法要会館で法要を行うという方法もあります。
自宅で法要を営む場合は、菩提寺などに、後飾り祭壇を使いたいと相談しましょう。
四十九日法要までにお墓が完成しない場合
亡くなってからお墓を注文した場合はとくに、四十九日法要までにお墓が完成しないことがあります。
仏壇へ遺骨をまつることもできますが、かなり存在感があるため、後飾り祭壇を使えば無理なく遺骨を安置できます。
納骨することにためらいがある場合
四十九日法要を迎えても、納骨にためらいがあり「いつまでも故人とともにいたい」と感じる人もいるでしょう。
後飾り祭壇があれば、心の整理がつくまで遺骨を安置できます。
仏壇を購入する予定がない場合
仏壇を購入しないと決めた場合、後飾り祭壇を利用すれば、いつまでもゆったりと故人の遺影や位牌を安置できます。
新盆用の祭壇として後飾り祭壇を使いたい場合
故人が亡くなって49日目以降に、初めて迎えるお盆を「新盆」といいます。
新盆では、故人の位牌や遺影を仏壇からいったん取り出し、特別に祭壇を設けてまつる必要があります。
後飾り祭壇を処分せず保管しておくと、新盆用の祭壇として利用することもできます。
飾り付けは、地域の初盆飾りを参考に行いましょう。
後飾り祭壇を長く使う際に注意したいこと
後飾り祭壇に使われているのは、段ボールです。
ある程度の強度を持つものが使われてはいますが、やはり水に弱く、あまり重いものを載せるとへこんでしまう可能性があります。
49日を過ぎても後飾り祭壇を使いたい場合は、なるべく長く使えるよう、以下に注意しましょう。
お供え物は下にお盆やお皿を敷いて供える
特に果物など水分が多いお供え物は、段ボールが傷む原因になりかねません。
また、じかに祭壇へ置くことで布を汚してしまったり、匂いが付いてしまったりする可能性があります。
お供え物の下には、必ずお盆やお皿を敷きましょう。
水やお茶はこぼさないように注意
故人へのお供えとして、水やお茶を用意したい人もいることでしょう。
水をこぼしてしまうと、段ボールの強度が落ちる可能性があります。
なるべく、祭壇の手前にテーブルを置き、そこへお供えするようにしましょう。
ロウソクの火に注意
後飾り祭壇のロウソク立てが倒れると、布や段ボールに火が移り、火災になってしまうおそれがあります。
ロウソクに火をつけるのはお参りのときだけにしましょう。
線香立ての下にお盆を敷く
線香立ての周囲は、灰で汚れる可能性が高い場所です。
後飾り祭壇に線香立てを置く場合は、必ずお盆を敷きましょう。
陰膳の取り扱いに注意
誤って陰膳をひっくり返すと、布や段ボールが汚れ、臭いがなかなか取れなくなってしまいます。
陰膳を供えるとき、下げるときは慎重に行いましょう。
後飾り祭壇の処分方法
役目を終えた後飾り壇を、どのように処分すれば良いか分からないという人もいるでしょう。
祈りに使う祭壇ではありますが、後飾り壇には魂が込められていないとされています。
よって、自治体の処分方法に従って処分して構いません。
もしどうしても処分ができないと悩む場合は、葬儀を依頼した葬儀社に電話して事情を話し、引き取ってもらいましょう。
49日目までなら、無料で引き取りに来てくれる葬儀社もあります。

この記事を書いた人
奥山 晶子
葬儀社への勤務経験、散骨を推進するNPO「葬送の自由をすすめる会」の理事の経験、遺品整理関係の著書・サイト制作サポートなどから、終活全般に強いライター。ファイナンシャルプランナー(2級)。終活関連の著書3冊、監修本1冊。最近の著書は「ゆる終活のための親にかけたい55の言葉」オークラ出版。ほか週刊現代WEBなどサイトへの終活関連コラム寄稿、クロワッサン別冊「終活読本」の監修や、令和6年5月発刊「ESSE」6月号のお墓特集を監修している。