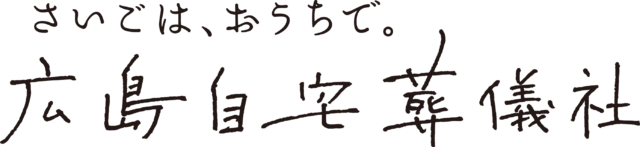生前お世話になった方へのお礼の方法、お礼の品物やのし、お礼状の例文を紹介
更新:2025.07.27
葬儀後、生前とくにお世話になった人にお礼をする場面があります。
お礼の手紙を品物に添えるべきか、手紙だけにすべきか、どんな手紙にすべきかなど、判断に迷うことは少なくありません。
お礼の対象となる相手の範囲から、お礼の方法、品物の選び方、のしの書き方、手紙の文例までを解説します。
ぜひ参考にしてください。
目次
「生前お世話になった人」には、どんな人が当てはまる?
まずは、「どなたにお礼をすればいいのだろう?」と考えている方のために、生前お世話になり、お礼をすべき人について整理しておきましょう。
例えば、以下のような方々が当てはまります。
・故人の勤務先
・故人の商売の得意先
・故人のご近所
・故人の長年の友人
・故人の所属するサークルや地域活動
・故人が入居していた介護施設
・故人が最後に入院していた病院
・故人のことで相談に乗ってもらった方
なお、例で挙げた方々に「絶対にお礼をすべき」というわけではありません。
生前、とくにお付き合いがあり、遺族としても「お世話になった」と感じている方々にお礼をしましょう。
お礼の方法にはどんなものがある?
お礼の方法には以下の4パターンがあり、相手によってふさわしい方法が違います。
お礼の手紙に品物を添えて送る
遠方の方や、故人とだけ付き合いがあったなど遺族が訪問したらかえって恐縮させてしまうような方には、お礼の手紙に品物を添えて送ります。
故人の長年の友人や、故人の勤務先が遠方の場合などに使える方法です。
お礼の手紙だけを送る
病院や介護施設は、お礼の品を受け取らない方針としている場合が多いものです。
直接手渡しに行く場合は相手がその場で断れますが、送られてきた品物は辞退できないため、困らせてしまいます。
お世話になった病院や介護施設が遠方の場合には、主治医や担当者にあててお礼の手紙だけを送るのがいいでしょう。
もし贈り物をしたい場合は、事前に電話などで問い合わせましょう。
直接訪問してお礼の品を手渡す
最も丁寧な方法です。
相手が近くに住んでいる場合や、手続き関係で先方へ伺う予定のあるときに使えます。
ご近所には、葬儀が済んだことの報告と合わせてお礼に伺います。
また、保険の手続き関係で故人の勤務先に行ったり、請求関係で故人の商売の得意先に行ったりすることもあるでしょう。
このように、葬儀後初めて伺うときは、忘れずにお礼の品を持参しましょう。
直接訪問してお礼の手紙を渡す
故人に関わる請求関係などで病院や介護施設に訪問するときは、お礼の手紙を持参しましょう。
もし品物を持参したい場合は、お礼の品を受け付けているか、事前に必ず連絡します。
お礼の品を受け付けていない場合は、主治医や担当者にあてた手紙を持参します。
生前お世話になった方へのお礼の品はどんなものがいい?
生前お世話になった方へのお礼の品は、香典返しと同様、「消えもの」が良いとされています。
消えものとは、食品や消耗品など、食べたり使ったりしてなくなるものです。
葬儀の後に渡すお礼の品として消えものを贈るのは、「不幸を引きずらないため」の風習とされてきました。
ただ、葬儀に限らず、相手の好みが分からないときの「お礼の品」は、食品が一般的といえます。
相手と自分の関係性や相手の立場を考えて、品物を選ぶのがいいでしょう。
ご近所へ配るお礼の品
ご近所へ配るお礼の品は、1,000円~2,000円の菓子折りが一般的です。
全て同じものに統一するのがいいでしょう。
また、地域の風習によって「饅頭」や「タオル」「酒」など、品物が決まっている場合もあるため、可能であれば親族やご近所に確認してから用意しましょう。
故人の勤務先や所属していたサークルなどに配るお礼の品
相手先の人数が多い場合は、人数に合わせて個包装の菓子折りを用意するのが一般的です。
予算は、人数にもよりますが、3,000円~5,000円程度と考えます。
故人の友人や相談相手など、個人に贈るお礼の品
相手が個人の場合は、2,000円~3,000円程度の菓子折りやお茶、コーヒーのセット、タオルや洗剤などの消耗品を用意するのがいいでしょう。
あまりに高価な物はかえって恐縮させてしまいます。
「その程度の金額では気持ちが収まらないほどお世話になった」と思うなら、その感謝は手紙に込めましょう。
病院や介護施設がお礼の品を受け付けている場合
病院や介護施設がお礼の品を受け付けているなら、看護師や介護担当者の数に合わせて、個包装の菓子折りなどを用意します。
なお、金券や現金は避けましょう。
お礼の品にかけるのしは「志」
生前お世話になった方へのお礼の品には、香典返しと同様、白黒の水引がプリントされたのし紙に「志」と書かれたものを使います。
「志」を水引の上に書き、水引の下の部分には「○○家」や喪主の姓名を書き入れます。
のしの表書きは、「志」のほかに宗教や地域によっては「偲び草」、「茶の子」と書くこともあります。
なお、「あまり葬儀を連想させるようなものは使いたくない」という気持ちがある場合は、白いのし紙に「御礼」としても構いません。
生前お世話になった方へ書く、お礼の手紙の文例3つ

生前お世話になった方へのお礼の手紙は、以下のような構成にします。
1. 葬儀へ参列くださったことへのお礼
葬儀に参列されなかった方への手紙は、葬儀が終わったことの報告から始めます。
2. 生前お世話になったことへのお礼
3. お礼の品を同封したこと
お礼の品がある場合は、お礼の品について伝えます。
4. 締めの文言
「今後も変わらぬお付き合いを」「益々のご発展をお祈り申し上げます」など、相手に合わせた締めの言葉とします。
生前お世話になった方への手紙のマナーは、以下の2つです。
1.頭語と結語を使う(「拝啓」「敬具」「謹啓」「謹白」など)
2. 句読点を使わない
実際の例文をご紹介しましょう。
【文例① お礼の手紙に品物を添えて送る場合(相手:故人の友人)】
拝啓
故○○儀 葬儀に際しましては ご会葬いただき誠にありがとうございました
なお 生前中は何かとお世話になりましたこと
家族一同 心から厚く御礼申し上げます
ささやかではございますが 感謝の気持ちとして心ばかりの品を同封いたしました
今後も変わらぬお付き合いのほど どうぞよろしくお願い申し上げます
略儀ながら書中をもってお礼に代えさせていただきます
敬具
【文例② お礼の手紙だけを送る場合(相手:病院)】
拝啓
先般 亡き○○の葬儀も終わり ようやく日常が落ち着きを取り戻してきました
生前中は大変お世話になりましたこと心から厚く御礼申し上げます
生前 ○○も何かにつけ △△先生と看護師さん方への感謝の言葉を申しておりました
みなさまのご健勝を心よりお祈り申し上げます
本来であれば直接お目にかかるべきところではございますが 略儀ながら書中をもってお礼に代えさせていただきます
敬具
【文例③ お礼の品に手紙を添えて手渡す場合(相手:ご近所)】
※お礼の品を直接手渡すときも、できれば簡単な手紙を添えます。
ただし葬儀の翌日にたくさんのご近所へお礼を配る場合など、手紙が用意できない場合は省略してもやむを得ません。
謹啓
故○○の葬儀に際しましては ご多用中にもかかわらず
ご丁寧にお手伝いをしてくださり 誠にありがとうございました
おかげさまで滞りなく葬儀を執り行うことができました
生前 ご近所の皆様に囲まれ 穏やかな日々を過ごしていた故人を想うと
みなさまに感謝の気持ちでいっぱいです
ささやかではございますが 感謝の気持ちとして心ばかりの品を同封いたしました
今後も変わらぬお付き合いのほど どうぞよろしくお願い申し上げます
謹白
どの人にどんなお礼がしたいか、遺族の気持ちが大事
生前お世話になった方へのお礼を、どんな範囲にまで行うかは決まりがありません。
あくまで遺族として「この方には、個別にお礼を言いたい」と感じる方に、お礼をするのが大事です。
なお、お礼の品物については、相手との関係性や地域の慣習を踏まえたうえで、適切なものを選びましょう。
品物の種類や予算に迷うようなら、その地域についてよく知っている年長者や、最近葬儀を経験した親族などに相談するのもいい方法です。

この記事を書いた人
奥山 晶子
葬儀社への勤務経験、散骨を推進するNPO「葬送の自由をすすめる会」の理事の経験、遺品整理関係の著書・サイト制作サポートなどから、終活全般に強いライター。ファイナンシャルプランナー(2級)。終活関連の著書3冊、監修本1冊。最近の著書は「ゆる終活のための親にかけたい55の言葉」オークラ出版。ほか週刊現代WEBなどサイトへの終活関連コラム寄稿、クロワッサン別冊「終活読本」の監修や、令和6年5月発刊「ESSE」6月号のお墓特集を監修している。