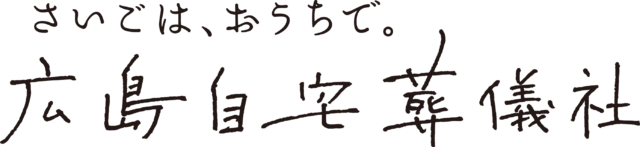戒名とは?何のためにつけるの?戒名の意味をわかりやすく解説
更新:2023.07.20
亡くなった人はお葬式で戒名をつけてもらう。
そう認識されている方は多くいらっしゃいますが、実は戒名は亡くなった人の名前ではありません。
この記事では戒名とは一体何なのか、何のためにつけるのかをわかりやすく解説させていただきます。
戒名とは本来生前に授かるもの
現在、葬儀の場で亡くなった方に戒名を授けるのが一般的になっていますが、本来は生前に授かるものでした。
戒名とは仏教徒として守るべき戒律を受けた者に対して授けられる名前です。
戒律を受けた者の名前=戒名、これに対して普段私達が日常で使っている名前は俗名と言われます。
本来ならば生きている間に戒律を守って仏教徒としての生活を送ることが理想なのですが、それが叶わなかったため、遅ればせながら亡くなってから授かっているというのが実情です。
戒名は仏門に入った者が授かるもの
戒名は生前に受戒して仏門に入った者が授かるものでした。
戒名の「戒」という字は、仏教徒が守るべき戒律の「戒」になります。
しかしながらそうした意味合いは時代とともに薄れていき、現在は遺族が菩提寺のお寺へお布施を行い、戒名をつけていただくことがほとんどです。
お寺にある墓地では戒名をつけていないと埋葬することができない墓地もありましたので、
そのため多くの方が戒名をつけるようになったとも言われています。
戒名の構成について
戒名の基本は「△△院□□○○居士」で、△△院=院号、□□=道号、○○=法号、居士=位号となります。
法号の部分が本来の戒名で、生前のお寺への貢献度や仏教への信心深さによって院号が付与されることや、年齢や性別によって位号が変化することもあります。
元々戒律のない浄土真宗では「法名(ほうみょう)」と呼び、日蓮宗では「法号(ほうごう)」と呼びます。
▪️院号(いんごう)
「院」は寺院のことです。戒名の一番上に位置します。生前に寺院への貢献が高かった方などにつけられます。
▪️道号(どうごう)
仏道を習得した特別な方に対するもう一つの名前になります。
▪️法号(ほうごう)
本来の戒名。俗名から1字取ってつけられることが多いです。
▪️位号(いごう)
性別や年齢、位を表します。成人男性の場合は大居士、居士、信士。成人女性の場合は、清大姉、大姉、信女。子供の場合は、童士、童女などとなります。
戒名のランクや費用など戒名について詳しく知りたい方は、下記の記事で詳しく紹介していますので、合わせてご覧ください。
有名人の戒名
「文献院古道漱石居士」は誰の戒名か、おわかりでしょうか?
一般人の場合は、生前の俗名から1字取って戒名をつけることが多いのですが、有名人の場合は、生前の功績や人柄を表す戒名をつけることが多く見られます。
例えば小説家の夏目漱石は「文献院古道漱石居士」という戒名を授かりました。
昭和の歌姫、美空ひばりは「茲唱院美空日和清大姉」、昭和の大スター石原裕次郎は「陽光院天真寛裕大居士」という戒名を授かっています。
日本で一番長い戒名は戦国大名の徳川家康で、「東照大権現安国院殿徳蓮社崇誉道和大居士」という19文字になります。
いずれもその方の功績やお人柄が感じられるものになっていることがわかります。

この記事を書いた人
廣田 篤 広島自宅葬儀社 代表
葬儀業界23年、広島自宅葬儀社代表。厚生労働省認定技能審査1級葬祭ディレクター。終活カウンセラー。前職大手葬儀社では担当者として 1500 件、責任者として1万件以上の葬儀に携わる。実母の在宅介護をきっかけに広島自宅葬儀社を立ち上げて現在に至る。広島市内だけでなく瀬戸内海に浮かぶ島々から、山間部の世羅町、神石高原町まで広島県内あらゆる地域の葬儀事情に精通する広島の葬儀のプロ。身内の死や介護の経験、数々の葬儀を通じての縁から「死」について考え、文章にすることをライフワークとしている。