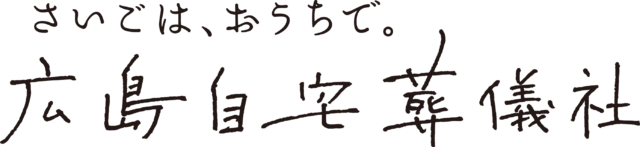お葬式へ参列するときのマスクの色は、白がいい?黒がいい?
更新:2024.02.26
新型コロナウイルスが流行し、これまでは屋外ではマスク着用は不要、屋内では原則着用とされていたマスクですが、政府の発表により令和5年3月13日以降、マスク着用は個人の判断が基本となりました。
詳細は厚生労働省発表の「マスク着用について」をご参照ください。
屋内でのマスク着用が個人の判断となったことで、今この時期にお葬式へ参列する機会があれば、マスクを着用するべきなのか、しなくても良いものなのか、お悩みになる方も多いのではないでしょうか。
また、葬儀と言えば黒を連想しがちなため、黒いマスクをして参列すると良いのだろうか?それとも白がいいのだろうか?
疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
この記事では、葬儀参列の際のマスクについて、実際に葬儀に携わっている私が解説させていただきます。
お葬式ではまだ多くの方がマスクを着用
新型コロナウイルスの位置付けが5類になったことで、日常生活を取り戻した現在、マスクを外して外を歩く方も増えています。
現在のマスク着用率はコロナ禍に比べて1/3に激減しているそうです。
そんな時だからこそ、葬儀に参列する際は「まだマスク着用がマナーなのかな?」
疑問に思う方も多いと思われます。
結論から言えば、お葬式の場面では、場面によっては今も殆どの方がマスクを着用されています。
例えば控室で家族だけで過ごす場面はマスクを外されている方が多いです。
一方で儀式の最中や他の家の方とも会う確率の高い火葬場ではマスク着用率が高い傾向です。
気心知れている気を遣わない間柄ではマスクを外し、周囲へ気を遣う場面ではマスクを着用するという使い分けをされている方が多い印象です。
また、高齢者の方の中には日常的に感染予防としてマスク着用を続けている方もいらっしゃいます。
葬儀の場は不特定多数の方が集まる場でもありますから、感染予防としてのマスク着用は継続いただければと思います。
多くの斎場、葬儀社の職員は引き続きマスク着用をしているところが殆どです。
葬儀でマスク着用がマナーになる理由
令和4年5月23日に政府が新たに示したマスク着用の考え方は、下記の通りです。
| 身体的距離が確保できる | 身体的距離が確保できない | |
| 会話を行う(屋内) | 着用を推奨する | 着用を推奨する |
| 会話を行う(屋外) | 着用の必要はない | 着用を推奨する |
| 会話を行わない(屋内) | 着用の必要はない | 着用を推奨する |
| 会話を行わない(屋外) | 着用の必要はない | 着用の必要はない |
葬儀の場面、斎場での場面は屋内になります。
葬儀では葬儀中に参列者同士の会話はありませんが、葬儀中は読経が行われます。
そして葬儀前後には参列者同士の会話などその場に集う方々の会話が屋内であります。
葬儀といえば、参列者がさまざまな地域からお越しになるのが特徴です。
そのため、感染すると広範囲に広がってしまうのが葬儀においてのリスクと言えます。
また、幅広い年代の参列がある場所で、高齢者の参列も日常的にある場所のため、マスクを着用した方が良い場所とも言えます。
このような理由から屋内での会話を伴う場所として、感染拡大防止の観点からマスク着用が推奨されています。
お葬式に参列する時のマスクはどんなのがいい?
マスク着用がお葬式のマナーとされる理由は、周囲への配慮です。
一番飛沫の拡散を抑える効果が高い不織布マスクは、布製、ウレタン製に比べて、吐き出し飛沫量も吸い込み飛沫量も少ないので、こちらが最善です。
しかし現在では布製、ウレタン製を選ぶ人も増えています。
コロナ禍では殆どの方が葬儀においては不織布マスクを着用されていましたが、コロナが5類に移行して以来、布製、ウレタン製を着用する参列者も増加傾向です。
お葬式に参列する時のマスクの色は?
色は白が良いです。白の不織布マスクが最適です。
急なお葬式でも用意がしやすく、手に入れやすい。そして一番無難だと言えます。
黒でも構いませんが、黒は若い世代に人気でカジュアルな場面でもよく使われるため、葬儀の場では周囲にカジュアルな印象を与えてしまう可能性があります。
肌の色に合わせて目立たないようにベージュをお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
コロナ禍の葬儀では、マスクしていますよと一目でわかるほうが相手に安心感を与えるという理由で、ベージュよりも白がおすすめでしたが、現在はベージュでも構いません。
しかし、ベージュも黒同様にカジュアルな印象を与えてしまう可能性はあります。
結論としては、白が無難、色は白でも黒、ベージュでも構いません。
本来のマスク着用の意味を考えれば、マスクをするならば、色よりも、不織布のマスクでお願いしたいということです。
お葬式のマスクで気をつけたいこと
最近では、参列者は家族だけという家族葬であれば、マスクを着用しない葬儀も普通にあります。
それでも葬儀中はマスクをしなかったが、火葬場ではマスクを着用するご家族もいらっしゃいます。
家族だけの空間、不特定多数の方と過ごす空間でマスクの使い分けです。
冒頭でも申し上げましたが、マスクをする場面、しない場面の使い分けが出てきているのが今のお葬式です。
つまりすぐに取り出せるようにしておくことなどの工夫が必要です。
代えのマスクを数枚持っておくなどの準備がおすすめです。
お葬式でおすすめのマスク
豊橋技術科学大学の研究結果で、下記の結果が出ています。
| 吐き出し飛沫量 | 吸い込み飛沫量 | |
| 不織布製 | 20% | 30% |
| 布製 | 18〜34% | 55〜65% |
| ウレタン製 | 50% | 60〜70% |
このようなデータから、不織布マスクは、感染予防効果が高く、感染拡大を防ぐには欠かせません。
お葬式は、他県からも人が集まる場で、クラスターの発生する可能性も秘めています。
少しでもリスク軽減するために、不織布マスクがおすすめです。

この記事を書いた人
廣田 篤 広島自宅葬儀社 代表
葬儀業界23年、広島自宅葬儀社代表。厚生労働省認定技能審査1級葬祭ディレクター。終活カウンセラー。前職大手葬儀社では担当者として 1500 件、責任者として1万件以上の葬儀に携わる。実母の在宅介護をきっかけに広島自宅葬儀社を立ち上げて現在に至る。広島市内だけでなく瀬戸内海に浮かぶ島々から、山間部の世羅町、神石高原町まで広島県内あらゆる地域の葬儀事情に精通する広島の葬儀のプロ。身内の死や介護の経験、数々の葬儀を通じての縁から「死」について考え、文章にすることをライフワークとしている。