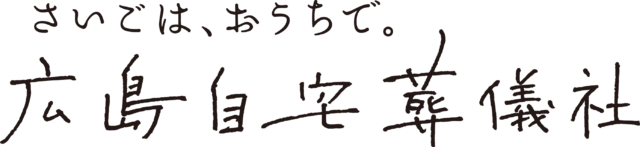死産をされた赤ちゃん(胎児)の供養方法と両親の心をケアするヒント
更新:2025.04.15
死産となった赤ちゃんも、この世に生を受けた人と同様に供養できます。
「あの子がお腹にいてくれたことをずっと忘れないでいたい」
「死産を経験した後、気持ちのよりどころとなる何かがほしい」
そう考えている方に向けて、死産となった赤ちゃんの葬儀をした後にどのような供養をしたらよいかを解説します。
最後には、悲しみに暮れる両親の心のケアを行う方法についても書いているので、ぜひ参考にしてください。
遺骨がなくても残っているもので供養はできる
妊娠12週以降に流産や死産をした場合、日本では赤ちゃんを火葬することが求められています。
多くの人は火葬のみを行いますが、しっかりした葬儀を行う人もいます。
ただ、火葬炉の構造上、胎児の遺骨を残して火葬するのは簡単ではありません。
胎児用の火葬炉を設けている火葬場もありますが、数が少ないため利用できる人は少ないでしょう。
なるべく遺骨を遺して火葬するようお願いしても、難しい場合は多々あります。
遺骨を遺すことができなくても、死産となった赤ちゃんの供養は可能です。
遺灰を骨壺に納めたり、赤ちゃんがまだ火葬にならないうちに病院にお願いして、あるいは両親自ら、爪や髪、手形、足形を残しておくと、後の供養に使えます。
もし爪や髪、手形などを遺せなかった場合には、エコー写真で供養をすることも可能です。
まずは、供養の対象にできるものを探しましょう。
何も残っていなくても供養はできる
赤ちゃんの状態や病院の方針によっては、爪や髪、手形、足形を残せないことがあります。
また、エコー写真も残っていないという人もいるでしょう。
そんなときであっても、供養ができないわけではありません。
例えば献体を希望している人の場合、亡くなったら大学病院などへ遺体が預けられてしまい、数年は遺族の手に遺骨が戻りません。
遺族は、遺体がないまま葬儀や供養を行います。
故人の爪や髪を遺して供養する人ももちろんいますが、位牌だけで葬儀や供養を行う人もいます。
僧侶が葬儀で儀式を行い、魂を込めた位牌をよりどころにして、その後の供養を行っていくのです。
死産となった赤ちゃんの形見が何も残っていないなら、よりどころになるものを新たに作りましょう。
以下のようなものが挙げられます。
赤ちゃんの名前をモチーフにしたもの
赤ちゃんのために準備していた名前があったら、その名前をモチーフにしたものを作りましょう。
名前をしたためた紙を入れた額縁、名入れのオブジェ、ペンダントトップや指輪の裏側に名前を刻んだジュエリーなどです。
位牌を作ることもできます。
ただし、菩提寺に依頼できるかどうかは、お寺の方針にもよりますので、まずは相談してみましょう。
天使のぬいぐるみやオブジェ
この世に生を受けず亡くなった赤ちゃんは、エンジェルになぞらえられることがよくあります。
天使のぬいぐるみやオブジェ、天使をモチーフにしたジュエリーなどを用意すると、赤ちゃんを感じさせるものとして愛着が湧くでしょう。
赤ちゃんのために準備していたものを供養の対象にする
帽子や靴下、おもちゃなど、赤ちゃんのために準備していたものはないでしょうか。
もしそれを見たときに死産となった赤ちゃんを強く思わせるようであれば、どのようなものでも供養の対象にすることが可能です。
ぜひ、自分にとってしっくり馴染むものを探してみてください。
死産となった赤ちゃんの供養方法3つ
死産となった赤ちゃんの供養方法には、大きく分けて以下の3つがあります。
3つ全てを行うことも可能です。
祈りのためのステージを作る
毎日そこへ向かって祈りを捧げられるような、小さなステージを作ります。
髪や爪が残っていれば小さな骨壺へそれを納め、手形や足形、エコー写真は額縁などに入れてステージに飾りましょう。
ほか、前章に示したように、両親が「これを供養の対象にする」と決めたものであれば何でも祀ることができます。
ステージには水や供物を捧げたり、お祈りをしたりして供養しましょう。
「ミニ仏壇」で検索すると、仏壇型からステージ型まで、様々なタイプのものがインターネット通版で販売されています。
気に入ったものを購入するのも、手作りのステージとするのも自由です。
メモリアルジュエリーを身につける
大事な人の遺灰などを込めたペンダントや指輪を、メモリアルジュエリーと呼びます。
遺髪や爪を込めることも可能です。
前章に示したように、とくに何も残っていない場合であっても、名前を刻んだり天使をモチーフにしたジュエリーを選んだりして、供養の対象とすることができます。
メモリアルジュエリーを作れば、肌身離さず持ち歩けます。
ずっと、赤ちゃんと一緒です。
何らかの事情で家の中に祈りのステージを作れない人にも向いています。
水子供養をする
流産、死産してしまった赤ちゃんの供養を、日本では昔から「水子供養」といいます。
お寺に水子供養を申し込み、寺院内にある水子地蔵のそばへ塔婆を立て、読経してもらいます。
この水子供養は、何回でも行うことが可能です。
四十九日や一周忌などの節目に関わらず、悲しさや辛さを感じたらいつでも供養を申し込むことができます。
そのとき、辛い気持ちをご住職に聞いてもらうこともできるでしょう。
両親の悲しみをケアするための方法3つ

死産となった赤ちゃんの供養をすることは、両親の悲しみを癒すための大事なセルフケアです。
しかし、心を込めて供養をしていても、ときにどうしようもない悲しみ、辛さ、悔しさ、やりきれなさを感じて苦しくなるときがあります。
そんなときどうしたらよいか、3つのヒントをお伝えします。
自分の悲しい気持ちを否定しない
死産を経験すると、周りから「いつまでも悲しんでないで」
「今回は残念だったけど、また頑張ろう」などと、前向きになるよう促されることがあります。
すると、本当は悲しい自分の気持ちに蓋をして、頑張って明るく振る舞ってしまうかもしれません。
しかし、自分の気持ちを否定したままでいると、苦しい気持ちが長く続いてしまう恐れがあります。
自分の悲しい気持ちに、正直になりましょう。ときには思い切り泣くなど、自分の感情を受け止められる場所と時間を作ります。
赤ちゃんへの想いを日記に書く
辛い気持ちを紙に書き出すと、頭の中が整理されることがあります。
また、自分の状態を客観的に受け止めることが可能になります。
辛くなったら、自分の想いを日記に書いてみてはいかがでしょうか。
ときどき日記を振り返ると、自分の気持ちの変化がよく分かります。
「このときは、こんな風に考えていたんだ」と改めて自分を理解することで、過去の自分を受け止められるでしょう。
また、「命日が近くなると悲しみが深くなる」など、気持ちの傾向をつかむことも可能になります。
当事者同士で話せる場所に参加する
同じように死産で赤ちゃんを亡くした人たちが集まる会が近くにあれば、参加してみましょう。
同じ体験をした人たちが感情や情報を分かち合う会を「自助会」「自助グループ」といいます。
市役所の福祉課で尋ねたり、役所や図書館のチラシコーナーを覗いてみたりすると、情報が集まります。
死産となった人にどう声をかけたらいい?
喪失感を乗り越えて行くには、周囲のサポートも欠かせません。
ただ、周りの人も「どう声をかけてよいか分からない」と迷い、腫れ物に触るように接したり、死産などなかったかのように接したりと、話題を避けてしまうケースがよく見られます。
周囲の人に必要なのは、「辛いときはいつでも話を聞くよ」
「あなたにとって大切だった存在のことを忘れていないよ」という姿勢です。
どう声をかけてよいか分からないのであれば、そのままストレートに「どう声をかけてよいか分からないけど、私で良ければいつでも頼ってね」と伝えましょう。

この記事を書いた人
奥山 晶子
葬儀社への勤務経験、散骨を推進するNPO「葬送の自由をすすめる会」の理事の経験、遺品整理関係の著書・サイト制作サポートなどから、終活全般に強いライター。ファイナンシャルプランナー(2級)。終活関連の著書3冊、監修本1冊。最近の著書は「ゆる終活のための親にかけたい55の言葉」オークラ出版。ほか週刊現代WEBなどサイトへの終活関連コラム寄稿、クロワッサン別冊「終活読本」の監修や、令和6年5月発刊「ESSE」6月号のお墓特集を監修している。