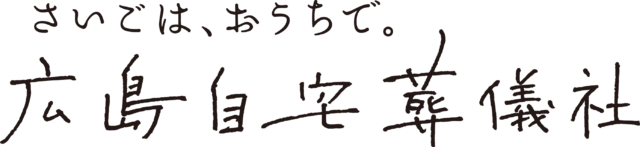葬式帰省のお土産は縁起が悪い?忌引き明けに職場へ持参するお礼に悩む方へ
更新:2025.04.29
お葬式で帰省をすると、「旅行で有給休暇を取ったときは職場にお土産を買うけれど、今回も買うべき?」と悩むことがあります。
遠方への葬式で仕事を休むのは、不幸のためやむないことであり、遊びに行くわけではないのでお土産を買う必要はありません。
ただし突然仕事を抜けたことに対するお詫びはするべきであり、それは言葉だけでも十分伝わりますが、そのために品物を用意するのも良いでしょう。
それでも「葬式帰省の土産なんて縁起が悪い?」と悩む人のために、忌引き明けのお礼について、一定のマナーをご紹介します。
目次
原則として葬式帰省のお土産を買う「必要」はない
まず、葬式帰省では、お土産を買う「必要」はありません。
葬式で帰省したら、お土産を買っていかなければならないというマナーはありません。
不幸は突然のことであり、大切な人を亡くすため精神的なダメージが大きい出来事です。
例えば職場に「休暇を取ったらお土産を買う」という慣習があるとします。
しかし、葬式帰省の最中、お土産を買うことに思い至らなくても、またその時間がなくても、それをもってあなたを責める人はいません。
皆、心情を分かってくれます。
友人同士ならなおさらです。
職場に前例がなければ、やめておくという判断もある
もし職場に「休暇を取ったらお土産を買う」という慣習がなければ、葬式帰省のお土産を買うことはやめておいた方がいいかもしれません。
今回のことで前例を作ると、次に不幸のあった人も、お土産を買わなければならない雰囲気ができてしまうためです。
ただ、一部の人にかなり負担をかけてしまったなど、どうしてもお礼をしたい人には、個別にお土産を買っていっても構わないでしょう。
「本当に助かりました、ありがとう」とお礼の言葉を添えて渡します。
「葬式帰省のお土産は縁起が悪いか」は、気にしなくていい
「葬式で帰省したときのお土産なんて、縁起が悪くて嫌という人もいるかも」という考えが頭をよぎるかもしれません。
しかし、そこに嫌悪感を覚える人は、少数と言っていいでしょう。
例えば、忌引き明けに職場へお菓子を配るのは、実際によくあることだからです。
もしかしたら「お土産」という表現が良くないのかもしれません。
「お土産」というと、旅行などへ行ったとき、楽しい思い出をお裾分けする品として選ぶイメージがあります。
なんとなく、ポジティブなイメージを持った表現です。
「葬式」と「お土産」のイメージのギャップに違和感があるという人もいるのではないでしょうか。
葬式帰省のとき「皆に何か買って帰らなければ」と思うのは、葬式の思い出を共有したいからではないでしょう。
急に仕事を抜けたことに対するお詫びや、感謝のしるしとして買うのですから、「お土産」ではなく「お礼の品」「お詫びの品」と考えるのはいかがでしょうか。
ただ、葬式を直接連想させる品物を敬遠する人はいるかもしれません。
もし気になるようなら、葬式で配られたお菓子をそのまま持って行ったり、香典返しをそのままお礼として渡したりするのは、やめておきましょう。
「お土産」とは別に「香典返し」は必要

葬式帰省のお土産を買う必要はありませんが、香典返しは必要です。
もし職場や得意先、友人から香典を頂いており、葬式で香典返しを渡せなかったなら、忌引き明けから四十九日までの間に香典返しを用意しましょう。
香典返しは、頂いた金額の半額程度の品物を用意するのが一般的です。
葬式のとき参列者へ配ったお返しものが、金額的に妥当であれば、そのお返しもので構いません。
ただ、職場から連名で香典を頂く場合は、1人あたりへのお返しが少額になることがあります。
その場合は、個包装のお菓子などを別に購入して用意するのも良いですし、急なことですから、後日手配しても全く問題ありません。
得意先から高額な香典を頂いた場合は、できれば得意先へ伺う日にちに間に合うよう、香典返しを用意しましょう。
余裕があったら帰省先で品物を選び、「志」の掛け紙をかけてもらうのがベストです。
余裕がない場合は葬儀社に相談するか、インターネットのギフトショップで手配するのが安心です。
「香典返し」とは別に「お土産」を買うべき?
なかには、職場から香典を頂き、香典返しを持っていくため「お土産はいらない?」と悩む人もいるでしょう。
職場全体から連名で香典を頂き、香典返しを皆に配る場合は、お土産はいらないでしょう。
香典返しの上にお土産を配ったら、職場の人たちはかえって恐縮してしまうかもしれません。
しかし上司など一部の人から香典を頂いた場合は、その人への香典返しの他に、お土産があってもいいかもしれません。
とくに、急な忌引きのため仕事で負担をかけた人には行き渡るようにしたいものです。
葬式帰省のお土産を買うときのマナー
葬式帰省のお土産を買うときは、以下に気をつけましょう。
個包装のお菓子にする
配りやすく、また食べやすいよう、個包装になったお菓子を選びます。
「お土産」には掛け紙をかけない
香典返しには「志」の掛け紙をかけますが、お土産には掛け紙をかけません。
葬式のお返しものではなく、仕事を抜けたことに対するお詫びやお礼を表す品だからです。
あまりに高価なものは避ける
個包装のお菓子なら、1つあたり200~300円程度のもので十分です。
あまりに高価なお土産は、「次に自分に不幸があったら同じようにしなければならない」と相手に思わせてしまうので避けましょう。
●葬式帰省のお土産を渡すときのマナー
お土産を渡すタイミング
葬式帰省のお土産は、職場であれば忌明け後、初めて出社したときに渡しましょう。
朝礼等があればベストですが、朝にみんなが集まる機会がなければ、ランチなどの休憩時に声をかけるのが一般的です。
どんなタイミングがベストか、上司に相談するのも良い方法です。
友人であれば、帰省から戻って初めて会ったときに手渡しましょう。
お土産を渡すときの挨拶
「葬式で遠出したことによるお土産」ではなく、「仕事で穴を開けたことへのお詫び」「対応してくれたことへの感謝」を伝えながら渡しましょう。
友人に手渡す場合も、「葬式帰省のお土産」と口に出す必要はありません。
【職場に葬式帰省のお土産を渡すときの挨拶例】
このたびは突然、お仕事を抜けてしまい誠に申し訳ありませんでした。
急なことにもかかわらず、快くフォローをお引き受けくださった皆さんに、ささやかながら感謝の気持ちをお配りします。
仕事の遅れを取り戻すよう、精一杯頑張りますので、今後もどうぞよろしくお願いします。
【友人に葬式帰省のお土産を渡すときかける言葉】
「地元のものだけど、良かったら食べてね」
「この前はバタバタしていて、予定をキャンセルしちゃってごめんね。これ、良かったら」
本当に必要なのは、お土産ではなく「言葉」
以上、葬式帰省のお土産マナーについて解説しました。
葬式帰省は旅行ではないので、「お土産」を買う必要はありません。
しかし、誰かに感謝の気持ちを伝えたいときは、そのしるしとして「お礼の品」を買いましょう。
そして、品物は「感謝のしるし」にすぎません。
必ず、感謝の言葉をかけることを大切にしましょう。
「本当にお世話になった」と感じ、また少しなりとも心に余裕があるなら、「今回はありがとうございました」とメッセージをしたためた手紙や付箋を添えて、品物を渡すのもおすすめです。

この記事を書いた人
奥山 晶子
葬儀社への勤務経験、散骨を推進するNPO「葬送の自由をすすめる会」の理事の経験、遺品整理関係の著書・サイト制作サポートなどから、終活全般に強いライター。ファイナンシャルプランナー(2級)。終活関連の著書3冊、監修本1冊。最近の著書は「ゆる終活のための親にかけたい55の言葉」オークラ出版。ほか週刊現代WEBなどサイトへの終活関連コラム寄稿、クロワッサン別冊「終活読本」の監修や、令和6年5月発刊「ESSE」6月号のお墓特集を監修している。