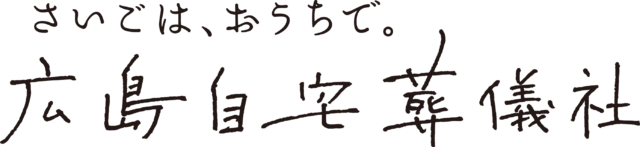葬儀前に亡くなった方の家に訪問してもいい? 訪問の可否とマナーを解説
更新:2025.09.23
「葬儀には出られないため、葬儀前にお別れを伝えたい」
「悲しむ遺族のため、すぐに駆けつけたい」などの理由で、葬儀前に亡くなった方の家に訪問したいと考える人もいるでしょう。
ただ、葬儀前のご遺族は慌ただしく、訪問が迷惑になってしまうことも考えられます。
この記事では、「そもそも訪問してよいのか」「どんな配慮が必要か」といったポイントを中心に、亡くなった方の家に訪問する方法についてわかりやすく解説します。
目次
葬儀前に、亡くなった方の家に訪問してもいい?
葬儀前に、亡くなった方の家に訪問するのは、珍しいことではありません。
ほんの一昔前は、葬儀前の故人宅には弔問客がひっきりなしに訪れるものでした。
「親しい人が亡くなったら、何はともあれ駆けつけるのが礼儀」
「ご近所だから手伝いをしなければ」などの理由から、葬儀の日まで毎日訪れ、葬儀にも参列するような人がたくさんいたのです。
しかし現代では、地域や人間関係の希薄化に加え、大勢の弔問客への対応で遺族が心身ともに疲弊してしまうことへの配慮もあり、葬儀前の訪問を控える傾向が強まっています。
そのため、どうしても事前に弔いたい特別な事情がない限り、お別れは葬儀や通夜の場で行うのが、今の時代に即したマナーといえるでしょう。
葬儀前に訪問したい「特別な事情」にはどんなものがある?
やむなく葬儀前の弔問を行う事情として、例えば以下のような場合があります。
葬儀に出られないが、最後に故人と対面したい方
葬儀に出られない場合、後日香典を持参したり送ったりするのが一般的ですが、それでは故人と対面できません。
「どうしても、故人に直接さよならを言いたい」と考えるなら、葬儀前に弔問するのがいいでしょう。
葬儀に出られないが、葬儀前なら駆けつけられる近親者
故人の子、兄弟など、葬儀に出るべき近親者なのに、事情があってどうしても葬儀に参列できない。
そんな立場の方は、葬儀前に都合がつくのであれば弔問しましょう。
葬儀の手伝いをする立場の方
今も、ご近所が葬儀の手伝いをする風習が残っている地域があります。
葬儀の手伝いをする立場の方は、手伝いのスケジュールや自分の役割を確認するために、一度弔問して喪主に挨拶すると良いでしょう。
「今回は、近所の手伝いがいるだろうか?」と疑問に思っている町内会の代表者も同様です。
どうしても対面で仕事の打ち合わせが必要な同僚や上司
喪主の忌引き休暇中の引き継ぎが、電話やメールではうまくできず悩んでおり、喪主が身動き取れない状況にいるなら、弔問の上で手短に打ち合わせるのも一手です。
葬儀前の弔問にアポイントは必要?
葬儀前に亡くなった方の家へ訪問したい場合、基本的には電話やメール、SNSなどでアポイントを取った方がいいでしょう。
喪主は、常に故人宅にいるとは限りません。
最近では、故人が葬儀社などの安置施設に安置されているケースもあります。
「故人をひと目見て、お別れを言いたい」など弔問の目的を添えて連絡しましょう。
ただし、喪主がタイミングよく電話に出てくれたり、すぐに返事をしてくれたりということは、平常時に比べて難しいといえます。
返事がない場合は「喪主はいないかもしれないけれど、とりあえず行ってみよう」というくらいの気持ちで、出かける準備をしましょう。
葬儀前、亡くなった方の家に訪問する場合のマナー5つ
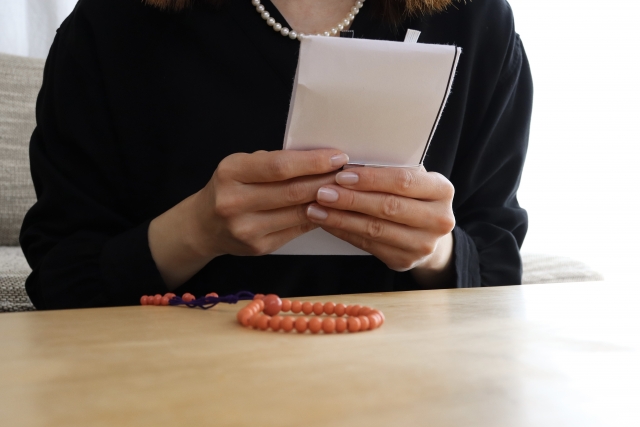
亡くなった方の家に、葬儀前に訪問するときは、以下のマナーに気をつけましょう。
1.喪服を着ず、平服とする
葬儀前の弔問は、平服を着用します。
平服とは、普段着ではなく、礼服でもないいわゆる「お出かけ着」のことです。
男性は黒、紺、グレーなど地味な色味のスーツを着用し、女性も地味な色味のワンピースに同系色のジャケットを羽織るか、スーツを着用しましょう。
また、可能であれば華美なネイルを外し、ヘアアクセサリーも装飾のついていないものを選びましょう。
2.葬儀に参列できない場合は香典を用意する
香典は、葬儀に参列できるなら、なるべく葬儀に持参するのがマナーです。
弔問時には、受付や記帳の場が整っていないためです。
ただし、葬儀に参列できないなら、香典を用意します。
ご近所や仕事の同僚など、香典を出すかどうか迷うような場合は、この場では用意しなくても構いません。
最近では香典を辞退する葬儀が増えています。
弔問時に喪主へ香典を差し出し、辞退されたら、無理に受け取ってもらうのはやめましょう。
3.どんな目的であっても、最初にお悔やみを言い、故人に手を合わせる
「葬儀の手伝いについて確認したい」
「仕事をするうえで喪主に確認したいことがある」など、故人に別れを告げることが主目的ではない人もいるでしょう。
しかし、葬儀前に亡くなった方の家に訪問するなら、どんな目的であれ、まずは遺族をいたわり、故人を悼むのが大事です。
故人宅に着き、遺族と顔を合わせたら「このたびはご愁傷様でした」
「お悔やみ申し上げます」と告げます。
そのうえで「まずはお線香をあげさせてください」と、仏間などへ向かいましょう。
故人の布団あるいは棺の前まで来たら正座し、手を合わせます。
故人と対面してお別れを言いたい近親者は、遺族に「お顔を拝見してよろしいでしょうか」と許可を得ましょう。
その後、焼香台で線香をあげます。
4.他の人の話を遮らず、静かに順番を待つ
故人宅には他にも弔問客がいる場合があります。
訪問時に先客がいたら、静かに座って自分の順番を待ちましょう。
もしその場に知り合いがいても、挨拶程度でとどめ、長話や、大きな声で話をしないよう心がけます。
5.短時間で話を切り上げる
葬儀前に限らず、弔問においては短時間でおいとまするのがマナーです。
遺族に労いの言葉をかけ、喪主に必要なことを伝えた後は、長居せずに退出しましょう。
余裕があったらお手伝いを申し出てみる
葬儀の場では、何かと人手が足りなくなるものです。
弔問時、気がついたことがあったら、率先してお手伝いを申し出てみましょう。
例えば、以下のようなお手伝いが考えられます。
子どもの世話や遊び相手
葬儀の場では、どうしても小さい子のお世話が大変になりがちです。
もし子どもの相手に慣れているなら、「少し面倒を見ていましょうか」
「遊び相手になりますよ」と申し出てみましょう。
供花の手入れ
故人宅にはたくさんの花が持ち込まれます。
なかには、元気がなくなっている花や、花束のまま花瓶に入れられずお供えされているものもあるかもしれません。
さりげなく「お花、花瓶に活けますよ」「水をあげておきましょうか」と申し出てみましょう。
玄関先の靴を揃える
たくさんの人が出入りするため、故人宅の玄関は散らかりがちです。
おいとまするとき、さりげなく、自分の靴があった周りだけでも整頓して帰るのはいかがでしょうか。
弔問客へのお茶やお茶菓子の手配
遺族と親しい場合や、あらかじめ葬儀の手伝いを任されている場合は、おいとまするとき「何か買ってくる物ありますか?」と声がけしてみましょう。
弔問客へのお茶やお菓子が必要なのに、遺族が出かけられず手が回っていない場合があります。
遺族の昼食が手配できず、空腹のまま弔問客の対応をしていることも珍しくありません。
現代の弔問に大切なのは「遺族への配慮」
葬儀前の弔問は、かつては当たり前の風習でしたが、現代では遺族への配慮がより一層求められるものになっています。
訪問するかどうか迷ったときは、まず遺族の状況や気持ちに思いを寄せることが大切です。
たとえ短い時間であっても、心からの弔意と気遣いが、遺族にとって深い慰めとなるでしょう。

この記事を書いた人
奥山 晶子
葬儀社への勤務経験、散骨を推進するNPO「葬送の自由をすすめる会」の理事の経験、遺品整理関係の著書・サイト制作サポートなどから、終活全般に強いライター。ファイナンシャルプランナー(2級)。終活関連の著書3冊、監修本1冊。最近の著書は「ゆる終活のための親にかけたい55の言葉」オークラ出版。ほか週刊現代WEBなどサイトへの終活関連コラム寄稿、クロワッサン別冊「終活読本」の監修や、令和6年5月発刊「ESSE」6月号のお墓特集を監修している。