ご依頼・ご相談の方はこちら
ご相談は無料
24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも
フリーダイヤルへご連絡ください。
「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は
メールでのご相談も可能です。
ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
四十九日の服装は、基本的には葬儀と同じで構いません。
ただ、「葬儀には出られなかったから、改めてどんな服装がいいか知りたい」という人もいるでしょう。
また、季節が進むと服装も変わり、「暑いときジャケットを脱いでもいい?」
「コートはどんなものでもいい?」と悩む人もいるかもしれません。
本記事では、男女別に四十九日の基本の服装を解説した後、季節別の注意点や妊婦さん、子どもの服装についてもご案内します。

四十九日で着る喪服は、遺族、親族、一般会葬者を問わず、「準喪服」が基本です。
準喪服とは、衣料店や百貨店で販売されている、いわゆるブラックフォーマルのことです。
男性なら黒いスーツ、女性なら黒いワンピースに短めのジャケットを合わせたアンサンブルを指します。
みんなが葬儀で着用するような喪服が、「準喪服」であるということです。
「準喪服」に対応する言葉として、「正喪服」があります。
正喪服とは、最も正式な喪服のことであり、紋付の黒い着物や、黒いモーニングコートを指します。
この正喪服は、遺族など特に故人と縁の濃い親族が着るものとされています。
しかし最近では葬儀においても、法要においても、正喪服を着用する遺族は少数派となりました。
立場を問わず、準喪服を着るのが一般的です。
基本的には「葬儀に出たときの格好で、そのまま四十九日にも出られる」と言えます。
四十九日における男性の基本的な服装は、黒いスーツです。
一概に「黒」といっても、黒いビジネススーツではなく、ブラックフォーマル売り場に売られている光沢のない礼服が基本です。
ただ、礼服は高価なものなので、社会人経験の浅い20代前半までは、黒いビジネススーツでも許されるとされています。
ワイシャツは白無地のものを選びましょう。
柄が入っているものや、襟先にボタンがついているボタンダウンシャツは避けます。
ネクタイは黒無地で、光沢のないものを選びましょう。
少しでも柄が入っているものは使えません。
ブラックフォーマル売り場で、一本買い求めておくのがおすすめです。
靴下、ベルト、靴、カバンといった小物も基本的に黒無地で、柄や色が入っておらず、金具が目立たないものを選びます。
ベルトのバックルも黒が理想的ですが、どうしても金具がついたものしかなく、金か銀かで迷うようなら銀の方が悪目立ちしません。靴も同様です。
男性が最も迷いがちなのは、カバンをどうするかでしょう。
男性が法要に持つのであれば黒いセカンドバッグが一般的ですが、持っていない人も多いと思われます。
そんなときは地味な印象のカバンであれば構いません。
カバンを持たず、胸ポケットに入る範囲の荷物で参列する男性も多くみられます。
四十九日における女性の基本的な服装は、黒いワンピースに揃いのジャケットを合わせたブラックフォーマルです。
衣料店へ出向くと種類が複数あるため、どんなものを選べば良いか迷う人もいるでしょう。
迷ったら、まずは丈感をチェックしてください。
椅子に座ったり正座をしたりしたときに膝が出ないよう、長めの丈を選ぶのがマナーです。
ブラックフォーマル売り場には、一般的なスーツ型や、パンツスーツ型も販売されています。
ワンピース型の喪服がよりフォーマルとされていますが、とくに年長者はパンツスーツの方が安心と、購入する人も多くいます。
若い方のなかにも、スカートが苦手な方がいることでしょう。
そんなときは、パンツスーツを選んでも構いません。
スーツを選ぶ場合、ジャケットの中に着るのは白無地のブラウスか、白無地のワイシャツとします。
小物はすべて黒無地でまとめます。
ストッキングは肌色ではなく黒とし、バッグは布製が正式です。
黒い布で巻かれたハンドルバッグに、サブバッグとして黒無地のトートバッグを持参します。
パンプスは金具のついていないシンプルなものを用意しましょう。
喪服を購入したときに、小物も一揃いまとめて購入しておくのがおすすめです。
マナーを守りながら暑さ、寒さに対応するには、それなりの準備が必要です。
暑さ厳しい折と、寒さが辛いときに分けて、四十九日における服装の注意点を解説します。
男女ともに、ジャケットを脱ぎ、手に持って参列しても構いません。
ジャケットを持参する際は、腕の日焼け止めなどが付着して白くならないよう、裏側を見せてたたみましょう。
ブラウスやワイシャツは半袖でもよいとされます。
ただ、ネクタイを外してよい葬儀はまだ見られません。
風通しの良い生地を使った、夏用のフォーマルウエアも売られています。
余裕がある場合は、検討してみましょう。
また、日傘や扇子を持参しても構いませんが、色は地味めのものを選ぶのが大事です。
式場内では基本的なブラックフォーマルスタイルでいなければならないため、インナーを厚くして対応しましょう。
ストッキングは、極寒となる地域ではタイツでも良しとされます。
黒い膝掛けを持参するのもおすすめです。
豪雪地帯などでは、ブーツでの参列も仕方ないとされる地域があります。
金具のついていない黒いブーツが最もよいとされますが、なければブラウンやグレーなど、地味な印象のブーツを選びましょう。
アウターの生地や色味は、基本的にはそれほど気にしなくてもいいでしょう。
アウターを着て参列することはなく、通常は式場の外で脱いでしまうためです。
とはいえ納骨式など外での式典がある場合は、やはり落ち着いた色味や素材のアウターを選びましょう。
ウールの黒無地のコートが理想的です。
妊婦は体調が変化しやすいため、無理して参列しなくても良いとされます。
少しでも不安なら辞退しましょう。
参列する場合は「略喪服」で構いません。
略喪服とは、急な不幸に駆けつけるときや通夜のときに着用する服装で、黒、ブラウン、グレーなど落ち着いた色合いのお出かけ着を指します。
お腹を圧迫しないよう、ゆったりとしたワンピースを選ぶのがおすすめです。
上着はジャケットの他、カーディガンでも構いません。
体を冷やさないよう、ストールや膝掛けを持参し、少しでも体調が悪くなったら無理をせず休みましょう。
四十九日では、子どもが18歳になるまでは、正装である制服を着用します。
制服がない場合は、なるべく見た目を大人の喪服に合わせます。
とはいえ、スーツやワンピースを新調する必要はありません。
手持ちの服の中で工夫しましょう。
白いワイシャツに黒のスラックス、黒いジャケットが理想的ですが、手持ちになければなるべく理想型に近づけます。
黒、ブラウン、グレーなど落ち着いた色味の服を選び、キャラクターものは控えましょう。
音が出る靴、光る靴を避ければ、スニーカーでも構いません。
靴下は黒か白とします。
白い靴下は汚れていると目立つため、畳に座る場合は、できれば新調しましょう。
黒いワンピースに黒いカーディガンやボレロが理想型。
なければなるべく地味めな色のワンピースを選び、タイツを履く場合は黒を選ぶと落ち着いた印象になります。
靴下は黒か白を選びましょう。
音や光が出る靴を避け、手持ちにあるようなら革靴を履きます。
光沢やリボン、ファーなどがついているものは控えましょう。
以上のように、四十九日の服装は、基本的には葬儀と同様に準喪服を着用するのが一般的です。
男女別・季節別・子どもや妊婦の服装についても、それぞれの立場や状況に応じて、落ち着いた色味と形式を意識した装いを選びましょう。
ただ、服装自体がマナーに沿っていても、身だしなみが整っていなければ、良い印象を与えることはできません。
喪服が汚れていたり、かび臭かったり、飼い猫の毛が付着していたりしていませんか。
ワイシャツに折りじわがついていると、特に夏場はジャケットを脱ぐ機会があるので目立ちます。
靴下に穴が空いていたり、すり切れていたりすると、畳に上がる場合はかなり注目されてしまいます。
服装を整えると同時に、ヘアスタイルやメイクにも気を配り、身だしなみをチェックしてから式場へ向かいましょう。
一周忌や三回忌など、人が亡くなると定期的に法事が発生します。
このとき「法事の依頼は、電話では失礼?」
「菩提寺には、どのくらい前に依頼すればいいのだろう?」と迷う人もいるでしょう。
法事の依頼は、電話が最も適しています。
お寺に法事を頼むときの電話のマナーやタイミングについて、詳しく解説します。
法事は、亡くなった方を供養する大切な儀式です。
そのため、「直接お寺に出向いてお願いするのが礼儀ではないか」と考える人は少なくありません。
しかし現代では、電話での依頼が一般的です。
お寺側もスケジュールを確認する必要があるため、突然の訪問よりも電話連絡を歓迎する場合が多いでしょう。
お寺のメールアドレスやSNSを事前に知っていて、常にそれらの手段でやりとりするほど仲が深まっている場合は、メールやSNSでも問題はないでしょう。
しかし、そのようなやりとりもないまま、お寺のHPにある「お問い合わせ」欄へ法事の問い合わせをするのは控えましょう。
日頃メールなどでやりとりする間柄でなければ、まずは電話をして、檀家としてお世話になっていることを伝えた上で、法事の申し込みをします。
法事を依頼する電話をかけるのは、希望する日の2ヶ月から1ヶ月前あたりが理想的です。
法事の1ヶ月前までには、参加してほしい人に案内状を出す必要があるため、お寺には早めに連絡を入れて日程を確定させましょう。
ただし、お寺には繁忙期があります。
お盆とお彼岸です。お盆の時期は初盆供養のための法事が立て込んだり、お寺で一斉法要があったりします。
お彼岸にも、やはり一斉供養の催しがあったり、お祭りがあったりなど、お寺は大変な時期です。
お盆やお彼岸に法事を行いたい場合、連絡が遅れると良い日程が取りづらくなるおそれがあります。
もし法事を行いたい時期がお盆やお彼岸に当たるようなら、2~3ヶ月前にはお寺に電話しましょう。
お盆は毎年8月12日から8月16日で、一部地域では7月12日~7月16日となります。
春のお彼岸は春分の日を中日とした1週間で、例年、3月中旬です。
秋のお彼岸は、秋分の日を中日とした1週間で、9月中旬から下旬です。
お寺に電話をかける場合、一般的な家庭と同様、緊急でなければ早朝や深夜帯は避けましょう。
学校の先生などと兼業している僧侶もいるため、兼業の内容を知っている場合は、仕事の時間帯を避けます。
また、土日の日中は法要が入っている場合が多いため、避けた方がいいでしょう。
平日の日中か、土日の夕方以降に電話をかけるのがおすすめです。
もしご住職自身が電話に出られない場合でも、奥さまなどお寺の中の方に伝言をお願いできます。
「自分が折り返しの電話に出られないかも」と不安があれば、留守番電話に連絡内容を吹き込んでもらえるよう、お願いしておきます。

法事を依頼する電話では、以下の情報を整理して伝えることが重要です。事前にメモしておくと、電話中に抜けや間違いが生じず、スムーズに依頼できます。
・施主の名前
・亡くなった方の戒名・俗名
・回忌(1周忌、三回忌など)
・法事の希望日程(候補を複数用意しておくとスムーズ)
・参列予定人数・会場の相談(自宅か寺か会館か)
・会食の有無(僧侶は参加可能か)
・施主の連絡先
なかには、次のようなことが気になっている人もいるでしょう。
初めて電話するときに余裕があれば、この機会に尋ねておくと安心です。
・用意するもの(位牌、納骨も含む場合は骨壺、供物、花束、数珠など)
・服装の相談(七回忌以降など、喪服が良いかどうか迷う場合)
・自宅で法事を行う場合、僧侶の交通手段(お迎えに上がるか、その必要はないか)
・お布施の金額(お寺側で取り決めなどがあるか否か)
法事の依頼をすると、お寺側から「卒塔婆(塔婆)は何本立てますか?」と尋ねられることがあります。
初めて法事を依頼する人は、きっと戸惑うことでしょう。
卒塔婆(そとば)、あるいは塔婆(とば)とは、故人の供養のためにお墓へ立てる長い木の板のことです。
古くはお釈迦様の遺骨を納めた塔(仏塔)という意味を持ち、法事の節目に追善供養としてお墓の後ろへ立てます。
1回の法事につき1本の卒塔婆を立てるのが一般的ですが、兄弟の数だけ立てるケースもみられます。
特にこだわりがなければ「1本でお願いします」と答えて良いでしょう。
卒塔婆の料金は、一本あたり数千円が相場です。
なお、浄土真宗など、卒塔婆を立てない宗派もあります。
その際は、卒塔婆について聞かれることはありません。
お寺の固定電話に法事の依頼をすると想定して、電話対応のシミュレーションをご紹介します。
【ご住職が電話に出られる場合】
「もしもし。檀家の○○と申します。
いつも大変お世話になっております。
法事をお願いしたくてお電話しました。
ご住職はいらっしゃいますか?」
(ご住職が電話に出る)
「こんにちは、○○です。
▲▲(故人)の葬儀につきましては、大変お世話になりありがとうございました。
一周忌が近づいて参りましたので、法事をお願いしたくてお電話しました。
○月×日か、その次の週あたりの午前中、ご都合はいかがでしょうか?」
(日程が決まる)
「それでは、その日程でお願いしたいです。
法事の会場は、私どもの家でもよろしいでしょうか。
お迎えに上がりましょうか、それともお車で来られますか?」
「法要の後、会食を予定しています。
ご参加いただくことはできますか?
それとも、お持ち帰りのお弁当をご用意した方がよろしいでしょうか」
(やりとりがあって)
「ありがとうございます。
それでは○月×日の日曜日、午前11時から○○家での法要をよろしくお願いします。
もし何かございましたら、私の携帯電話までお電話ください。
番号は○○○です。」
【ご住職が電話に出られない場合】
「もしもし。檀家の○○と申します。
いつも大変お世話になっております。
法事をお願いしたくてお電話しました。
ご住職はいらっしゃいますか?」
(住職不在を告げられる)
「そうですか。
それでは、時間を改めてお電話します。
何時頃がよろしいでしょうか?」
(伝言を受けてもらえる場合)
「ありがとうございます。
それでは、○○より、▲▲(故人名)の一周忌法要について電話があった旨をお伝えください。
法事の希望日は、○月×日か、その次の週あたりです。
私の電話番号は、○○○です。
電話に出られない場合もあるかもしれませんが、その場合は、留守番電話に伝言いただければ嬉しいです。」
電話で法事の日程が決まったら、以下の手配を行いましょう。
正式な案内状を送る前に、家族や主な親戚には日程を簡単に知らせておきます。
会食を行いたい料亭などに、予約を入れます。
人数はまだはっきりとは決まらないため、だいたいの人数で押さえておきましょう。
正確な人数が決まったら、速やかに会場へ伝えます。
法事の日程や会食の有無を盛りこんだ案内状を作成します。
喪服での参加ではない場合は、「平服でお越しください」と忘れずに加えましょう。
案内状は、法事の1ヶ月前を目安に出します。
参加の可否の連絡は、2週間前までに受け取れるようにしましょう。
法事をお寺に依頼する電話は、失礼ではありません。
むしろ、事前に日程や必要事項を整理して丁寧に伝えることで、円滑に準備を進める第一歩になります。
「電話で頼むのは不安」という気持ちになる人もいるかもしれませんが、この記事のシミュレーションを参考に、最低限のマナーと聞きたい情報を押さえて電話してみましょう。
「葬儀には出られないため、葬儀前にお別れを伝えたい」
「悲しむ遺族のため、すぐに駆けつけたい」などの理由で、葬儀前に亡くなった方の家に訪問したいと考える人もいるでしょう。
ただ、葬儀前のご遺族は慌ただしく、訪問が迷惑になってしまうことも考えられます。
この記事では、「そもそも訪問してよいのか」「どんな配慮が必要か」といったポイントを中心に、亡くなった方の家に訪問する方法についてわかりやすく解説します。
葬儀前に、亡くなった方の家に訪問するのは、珍しいことではありません。
ほんの一昔前は、葬儀前の故人宅には弔問客がひっきりなしに訪れるものでした。
「親しい人が亡くなったら、何はともあれ駆けつけるのが礼儀」
「ご近所だから手伝いをしなければ」などの理由から、葬儀の日まで毎日訪れ、葬儀にも参列するような人がたくさんいたのです。
しかし現代では、地域や人間関係の希薄化に加え、大勢の弔問客への対応で遺族が心身ともに疲弊してしまうことへの配慮もあり、葬儀前の訪問を控える傾向が強まっています。
そのため、どうしても事前に弔いたい特別な事情がない限り、お別れは葬儀や通夜の場で行うのが、今の時代に即したマナーといえるでしょう。
やむなく葬儀前の弔問を行う事情として、例えば以下のような場合があります。
葬儀に出られない場合、後日香典を持参したり送ったりするのが一般的ですが、それでは故人と対面できません。
「どうしても、故人に直接さよならを言いたい」と考えるなら、葬儀前に弔問するのがいいでしょう。
故人の子、兄弟など、葬儀に出るべき近親者なのに、事情があってどうしても葬儀に参列できない。
そんな立場の方は、葬儀前に都合がつくのであれば弔問しましょう。
今も、ご近所が葬儀の手伝いをする風習が残っている地域があります。
葬儀の手伝いをする立場の方は、手伝いのスケジュールや自分の役割を確認するために、一度弔問して喪主に挨拶すると良いでしょう。
「今回は、近所の手伝いがいるだろうか?」と疑問に思っている町内会の代表者も同様です。
喪主の忌引き休暇中の引き継ぎが、電話やメールではうまくできず悩んでおり、喪主が身動き取れない状況にいるなら、弔問の上で手短に打ち合わせるのも一手です。
葬儀前に亡くなった方の家へ訪問したい場合、基本的には電話やメール、SNSなどでアポイントを取った方がいいでしょう。
喪主は、常に故人宅にいるとは限りません。
最近では、故人が葬儀社などの安置施設に安置されているケースもあります。
「故人をひと目見て、お別れを言いたい」など弔問の目的を添えて連絡しましょう。
ただし、喪主がタイミングよく電話に出てくれたり、すぐに返事をしてくれたりということは、平常時に比べて難しいといえます。
返事がない場合は「喪主はいないかもしれないけれど、とりあえず行ってみよう」というくらいの気持ちで、出かける準備をしましょう。
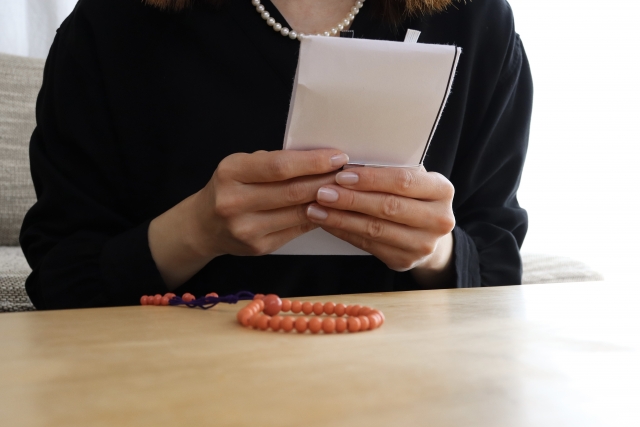
亡くなった方の家に、葬儀前に訪問するときは、以下のマナーに気をつけましょう。
葬儀前の弔問は、平服を着用します。
平服とは、普段着ではなく、礼服でもないいわゆる「お出かけ着」のことです。
男性は黒、紺、グレーなど地味な色味のスーツを着用し、女性も地味な色味のワンピースに同系色のジャケットを羽織るか、スーツを着用しましょう。
また、可能であれば華美なネイルを外し、ヘアアクセサリーも装飾のついていないものを選びましょう。
香典は、葬儀に参列できるなら、なるべく葬儀に持参するのがマナーです。
弔問時には、受付や記帳の場が整っていないためです。
ただし、葬儀に参列できないなら、香典を用意します。
ご近所や仕事の同僚など、香典を出すかどうか迷うような場合は、この場では用意しなくても構いません。
最近では香典を辞退する葬儀が増えています。
弔問時に喪主へ香典を差し出し、辞退されたら、無理に受け取ってもらうのはやめましょう。
「葬儀の手伝いについて確認したい」
「仕事をするうえで喪主に確認したいことがある」など、故人に別れを告げることが主目的ではない人もいるでしょう。
しかし、葬儀前に亡くなった方の家に訪問するなら、どんな目的であれ、まずは遺族をいたわり、故人を悼むのが大事です。
故人宅に着き、遺族と顔を合わせたら「このたびはご愁傷様でした」
「お悔やみ申し上げます」と告げます。
そのうえで「まずはお線香をあげさせてください」と、仏間などへ向かいましょう。
故人の布団あるいは棺の前まで来たら正座し、手を合わせます。
故人と対面してお別れを言いたい近親者は、遺族に「お顔を拝見してよろしいでしょうか」と許可を得ましょう。
その後、焼香台で線香をあげます。
故人宅には他にも弔問客がいる場合があります。
訪問時に先客がいたら、静かに座って自分の順番を待ちましょう。
もしその場に知り合いがいても、挨拶程度でとどめ、長話や、大きな声で話をしないよう心がけます。
葬儀前に限らず、弔問においては短時間でおいとまするのがマナーです。
遺族に労いの言葉をかけ、喪主に必要なことを伝えた後は、長居せずに退出しましょう。
葬儀の場では、何かと人手が足りなくなるものです。
弔問時、気がついたことがあったら、率先してお手伝いを申し出てみましょう。
例えば、以下のようなお手伝いが考えられます。
葬儀の場では、どうしても小さい子のお世話が大変になりがちです。
もし子どもの相手に慣れているなら、「少し面倒を見ていましょうか」
「遊び相手になりますよ」と申し出てみましょう。
故人宅にはたくさんの花が持ち込まれます。
なかには、元気がなくなっている花や、花束のまま花瓶に入れられずお供えされているものもあるかもしれません。
さりげなく「お花、花瓶に活けますよ」「水をあげておきましょうか」と申し出てみましょう。
たくさんの人が出入りするため、故人宅の玄関は散らかりがちです。
おいとまするとき、さりげなく、自分の靴があった周りだけでも整頓して帰るのはいかがでしょうか。
遺族と親しい場合や、あらかじめ葬儀の手伝いを任されている場合は、おいとまするとき「何か買ってくる物ありますか?」と声がけしてみましょう。
弔問客へのお茶やお菓子が必要なのに、遺族が出かけられず手が回っていない場合があります。
遺族の昼食が手配できず、空腹のまま弔問客の対応をしていることも珍しくありません。
葬儀前の弔問は、かつては当たり前の風習でしたが、現代では遺族への配慮がより一層求められるものになっています。
訪問するかどうか迷ったときは、まず遺族の状況や気持ちに思いを寄せることが大切です。
たとえ短い時間であっても、心からの弔意と気遣いが、遺族にとって深い慰めとなるでしょう。
四十九日は故人を偲ぶ大切な法要です。
しかし、四十九日の案内状が届いても、仕事や家族の事情などで、どうしても参列が難しいこともあります。
「断ってもいいのか」「どう伝えれば失礼にならないか」と、悩む声も多く聞かれます。
本記事では、参列できない場合に失礼にならず事情を伝える方法、香典や供物のマナーをわかりやすくご紹介します。
仏教では、亡くなった日から数えて四十九日間を「中陰(ちゅういん)」といい、亡くなった人の霊がこの世とあの世の間を旅している期間であると捉えられています。
四十九日目は「満中陰」とされ、故人が浄土へ行けるかどうか審判が下る、大事な日です。
この四十九日という節目に、故人の冥福を祈り、静かに手を合わせる場が「四十九日法要」です。
故人が亡くなってから行われる行事としては、葬儀の次に大切な場と位置づけられています。
また、四十九日は昔から、遺族にとっても心の区切りになる大切な日とされています。
参列者の存在が遺族の支えとなることもあり、できれば参列したい法要です。
「その日はどうしても都合が合わない」というケースは、誰にでも起こりうるものです。
実際には、次のような事情で参列を断念する方も少なくありません。
・どうしても抜けられない仕事がある
・同じ日に身内の法事や冠婚葬祭が重なっている
・自分や子どもの試験など、変更が難しい予定と重なっている
・遠方で移動や宿泊が難しい
・入院中など体調面で外出が難しい
四十九日法要は葬儀に準じて大事にされるものですが、忌引き休暇が使えるわけではありません。
よって親族が集まりやすい土日にセッティングされる例が大半ですが、土日だからこそ外せない用事が生じる人もいますし、土日が休みの人ばかりではないでしょう。
四十九日法要に行けないときは、事前に行けない旨を伝え、香典や供物を前もって送るなどのフォローをしましょう。
「行くことができず大変申し訳なく思っている」
「故人を軽んじているわけではない」という気持ちが、遺族に伝わるような対応を心がけます。
家族のうち、誰かが四十九日法要に行ける場合は、誰かひとりでも参列した方がいいでしょう。
その際、できれば故人と一番血縁の濃い人が優先して参列します。
例として、父親、母親、子どもの3人が「母親の家系」の四十九日法要に招待され、子どもの行事の日と重なったら、母親だけでも参列するのがおすすめです。
無理にとは言いませんが、子どもを見送ったあとでも参列が可能な距離であれば、父母での参加が望ましいといえるでしょう。
同じ家族構成の例で、母親が病気やケガで療養中だとしたら、可能であれば父子で参列するのがいいでしょう。
故人が、父親にとって義父や義母など近しい存在にあたるならなおさらです。
ただし母親が深刻な病状にあり、身内がそばにいなければならない場合などは、例外とします。
家族の中の誰かが参列する場合には、遺族に前もって人数を伝えておきます。
四十九日法要は会食つきが大半なので、人数の把握は遺族にとって重要だからです。
四十九日法要の案内状は、法要の1ヶ月ほど前に届きます。
案内状をいただいたら、行けない場合はできるだけ早めに返事を伝えましょう。
連絡の手段としては、案内状に返信ハガキがついているとしても、まずは電話をするのがおすすめです。
いち早く相手に返事を伝えることができ、また、遺族への気遣いやお詫びの気持ちを言葉に込めやすいためです。
電話が繋がりにくかったり、連絡がどうしても夜分になってしまったりするなどの場合は、SNSやメールなど、日常的に相手と連絡を取っている手段で伝えましょう。
【電話例】
「このたびは、四十九日法要のご案内をありがとうございます。葬儀から少し経ちましたが、ご体調などはいかがですか?」
「実は、当日はどうしても外せない予定があり、残念ですが参列できません。本当に申し訳ありません」
「故人のご冥福をお祈りしています。○○さんも、手続きが大変かと思いますが、体調に気をつけてくださいね。私にお手伝いできることがあれば、いつでも言ってください」
【メールやSNSの文例】
「このたびは四十九日のご案内を頂き、誠にありがとうございます。
ただ、当日はどうしても外せない予定が重なっており、残念ながら参列がかないません。
何卒ご容赦いただけますよう、お願い申し上げます。
故人の冥福を心よりお祈りしております。
手続きばかりで大変かと思われますが、お疲れが出ませんよう、ご自愛ください。」
なお、電話やメールでお断りを入れたあとであっても、案内状に返信ハガキがついている場合には、後日忘れず投函しましょう。

四十九日法要に参列できない場合は、法要に間に合うよう香典を送ります。
四十九日法要に行けない場合の香典相場は、親族で1万円、その他で5,000円です。
香典の表書きは仏式であれば「御仏前(御佛前)」、神式なら「御玉串料」とし、現金書留で送付します。
郵便局の窓口に用意されている現金書留用の袋を使いましょう。
現金書留用の袋には、香典袋のほか、お悔やみの手紙を入れます。
1枚の便箋に、手短にお悔やみとお詫びを書くのがいいでしょう。
【お悔やみの手紙の文面例】
このたびの四十九日法要につきましては、事情により参列が叶わず、誠に申し訳なく存じます。
ご家族の皆様が穏やかに過ごせますよう、心よりお祈り申し上げます。
心ばかりではありますが、香典を同封いたしましたので、ご仏前にお供えください。
猛暑の折からくれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。
故人が両親やきょうだい(義理も含む)である、遺族と常に交流があるなど関係性が深い場合は、香典とは別に、供物あるいはお花を送るのがおすすめです。
予算は3,000円から5,000円程度とし、四十九日法要に間に合うよう手配します。
【供物の種類とのし書き】
四十九日法要のために贈られる供物は、仏壇の周りに供えられたあと、地域によっては参列した親族へお裾分けされます。
お裾分けしやすいよう、個包装されたお菓子などの詰め合わせを選ぶのがおすすめです。
供物には、白黒あるいは地域によっては黄白の水引がプリントされたかけ紙をかけ、「御供」と表書きします。
【お花の種類とのし書き】
お祝いをイメージさせるような、華やかな色味や雰囲気の花を避け、白、紫、黄色を基調としたフラワーアレンジメントを選び、遺族宅へ届けてもらいます。
心配な場合は生花店に「四十九日に送るお花を選びたい」と言えば、アドバイスをもらえるでしょう。
「供花」や「御供」と書いた紙や、名札をつけてもらうとより丁寧ですが、必ずしもつけてもらう必要はありません。
四十九日法要のあとに遺族へ連絡すると、より「参列できず申し訳ない」
「故人の冥福を祈っている」という心を伝えることができます。
電話やSNSなど、日常的に相手と連絡を取っているツールで「四十九日、お疲れ様でした」
「行けなくてごめんなさい」と伝えてみましょう。
可能であれば、アポイントを取って訪問すると、より良いマナーになります。
四十九日に参列できないことで、「失礼ではないか」と悩む方もいるかもしれません。
しかし大切なのは、故人を偲ぶ気持ち、遺族をいたわる気持ちを誠実に伝えることです。
完璧である必要はないので、できる範囲で、自分らしい弔いの気持ちを形にしてください。
葬儀後、生前とくにお世話になった人にお礼をする場面があります。
お礼の手紙を品物に添えるべきか、手紙だけにすべきか、どんな手紙にすべきかなど、判断に迷うことは少なくありません。
お礼の対象となる相手の範囲から、お礼の方法、品物の選び方、のしの書き方、手紙の文例までを解説します。
ぜひ参考にしてください。
まずは、「どなたにお礼をすればいいのだろう?」と考えている方のために、生前お世話になり、お礼をすべき人について整理しておきましょう。
例えば、以下のような方々が当てはまります。
・故人の勤務先
・故人の商売の得意先
・故人のご近所
・故人の長年の友人
・故人の所属するサークルや地域活動
・故人が入居していた介護施設
・故人が最後に入院していた病院
・故人のことで相談に乗ってもらった方
なお、例で挙げた方々に「絶対にお礼をすべき」というわけではありません。
生前、とくにお付き合いがあり、遺族としても「お世話になった」と感じている方々にお礼をしましょう。
お礼の方法には以下の4パターンがあり、相手によってふさわしい方法が違います。
遠方の方や、故人とだけ付き合いがあったなど遺族が訪問したらかえって恐縮させてしまうような方には、お礼の手紙に品物を添えて送ります。
故人の長年の友人や、故人の勤務先が遠方の場合などに使える方法です。
病院や介護施設は、お礼の品を受け取らない方針としている場合が多いものです。
直接手渡しに行く場合は相手がその場で断れますが、送られてきた品物は辞退できないため、困らせてしまいます。
お世話になった病院や介護施設が遠方の場合には、主治医や担当者にあててお礼の手紙だけを送るのがいいでしょう。
もし贈り物をしたい場合は、事前に電話などで問い合わせましょう。
最も丁寧な方法です。
相手が近くに住んでいる場合や、手続き関係で先方へ伺う予定のあるときに使えます。
ご近所には、葬儀が済んだことの報告と合わせてお礼に伺います。
また、保険の手続き関係で故人の勤務先に行ったり、請求関係で故人の商売の得意先に行ったりすることもあるでしょう。
このように、葬儀後初めて伺うときは、忘れずにお礼の品を持参しましょう。
故人に関わる請求関係などで病院や介護施設に訪問するときは、お礼の手紙を持参しましょう。
もし品物を持参したい場合は、お礼の品を受け付けているか、事前に必ず連絡します。
お礼の品を受け付けていない場合は、主治医や担当者にあてた手紙を持参します。
生前お世話になった方へのお礼の品は、香典返しと同様、「消えもの」が良いとされています。
消えものとは、食品や消耗品など、食べたり使ったりしてなくなるものです。
葬儀の後に渡すお礼の品として消えものを贈るのは、「不幸を引きずらないため」の風習とされてきました。
ただ、葬儀に限らず、相手の好みが分からないときの「お礼の品」は、食品が一般的といえます。
相手と自分の関係性や相手の立場を考えて、品物を選ぶのがいいでしょう。
ご近所へ配るお礼の品は、1,000円~2,000円の菓子折りが一般的です。
全て同じものに統一するのがいいでしょう。
また、地域の風習によって「饅頭」や「タオル」「酒」など、品物が決まっている場合もあるため、可能であれば親族やご近所に確認してから用意しましょう。
相手先の人数が多い場合は、人数に合わせて個包装の菓子折りを用意するのが一般的です。
予算は、人数にもよりますが、3,000円~5,000円程度と考えます。
相手が個人の場合は、2,000円~3,000円程度の菓子折りやお茶、コーヒーのセット、タオルや洗剤などの消耗品を用意するのがいいでしょう。
あまりに高価な物はかえって恐縮させてしまいます。
「その程度の金額では気持ちが収まらないほどお世話になった」と思うなら、その感謝は手紙に込めましょう。
病院や介護施設がお礼の品を受け付けているなら、看護師や介護担当者の数に合わせて、個包装の菓子折りなどを用意します。
なお、金券や現金は避けましょう。
生前お世話になった方へのお礼の品には、香典返しと同様、白黒の水引がプリントされたのし紙に「志」と書かれたものを使います。
「志」を水引の上に書き、水引の下の部分には「○○家」や喪主の姓名を書き入れます。
のしの表書きは、「志」のほかに宗教や地域によっては「偲び草」、「茶の子」と書くこともあります。
なお、「あまり葬儀を連想させるようなものは使いたくない」という気持ちがある場合は、白いのし紙に「御礼」としても構いません。

生前お世話になった方へのお礼の手紙は、以下のような構成にします。
1. 葬儀へ参列くださったことへのお礼
葬儀に参列されなかった方への手紙は、葬儀が終わったことの報告から始めます。
2. 生前お世話になったことへのお礼
3. お礼の品を同封したこと
お礼の品がある場合は、お礼の品について伝えます。
4. 締めの文言
「今後も変わらぬお付き合いを」「益々のご発展をお祈り申し上げます」など、相手に合わせた締めの言葉とします。
生前お世話になった方への手紙のマナーは、以下の2つです。
1.頭語と結語を使う(「拝啓」「敬具」「謹啓」「謹白」など)
2. 句読点を使わない
実際の例文をご紹介しましょう。
拝啓
故○○儀 葬儀に際しましては ご会葬いただき誠にありがとうございました
なお 生前中は何かとお世話になりましたこと
家族一同 心から厚く御礼申し上げます
ささやかではございますが 感謝の気持ちとして心ばかりの品を同封いたしました
今後も変わらぬお付き合いのほど どうぞよろしくお願い申し上げます
略儀ながら書中をもってお礼に代えさせていただきます
敬具
拝啓
先般 亡き○○の葬儀も終わり ようやく日常が落ち着きを取り戻してきました
生前中は大変お世話になりましたこと心から厚く御礼申し上げます
生前 ○○も何かにつけ △△先生と看護師さん方への感謝の言葉を申しておりました
みなさまのご健勝を心よりお祈り申し上げます
本来であれば直接お目にかかるべきところではございますが 略儀ながら書中をもってお礼に代えさせていただきます
敬具
※お礼の品を直接手渡すときも、できれば簡単な手紙を添えます。
ただし葬儀の翌日にたくさんのご近所へお礼を配る場合など、手紙が用意できない場合は省略してもやむを得ません。
謹啓
故○○の葬儀に際しましては ご多用中にもかかわらず
ご丁寧にお手伝いをしてくださり 誠にありがとうございました
おかげさまで滞りなく葬儀を執り行うことができました
生前 ご近所の皆様に囲まれ 穏やかな日々を過ごしていた故人を想うと
みなさまに感謝の気持ちでいっぱいです
ささやかではございますが 感謝の気持ちとして心ばかりの品を同封いたしました
今後も変わらぬお付き合いのほど どうぞよろしくお願い申し上げます
謹白
生前お世話になった方へのお礼を、どんな範囲にまで行うかは決まりがありません。
あくまで遺族として「この方には、個別にお礼を言いたい」と感じる方に、お礼をするのが大事です。
なお、お礼の品物については、相手との関係性や地域の慣習を踏まえたうえで、適切なものを選びましょう。
品物の種類や予算に迷うようなら、その地域についてよく知っている年長者や、最近葬儀を経験した親族などに相談するのもいい方法です。
この記事では広島市で死産された赤ちゃん(胎児)のお葬式、火葬を行う場合について、わかりやすくご案内させていただきます。
正直あまり良いことではありませんし、避けたくなる辛い出来事です。
執筆しようかどうしようかと、何年も迷っていましたが、広島市の葬儀社からの情報があまりにも少なすぎると感じていたこともあり、誰かが発信しないといけないという思いから、心を込めて執筆させていただきました。
お困りの方がこの記事を見つけられ、少しでもお力になれば幸いでございます。
①自然分娩のケース
自然分娩の翌日、お母様は退院というのが多いです。
②病院で帝王切開手術のケース
手術の日時が決まり次第、手術を行い、翌日退院というケースが多いです。
(お母様の体調により、数日伸びるケースもあります。)
病院によっては、葬儀社がお迎えに来るようにして欲しいと遺族へ依頼するところもありますし、自分達の自家用車があるなら、自分達の自家用車で連れて帰っても構いませんよという病院もあります。
このように赤ちゃんを誰がどうやって自宅へ連れて帰るのかを決めます。
(病院から直接火葬場へという流れもありますが、そこに関しては後述します。)
赤ちゃんは病院から支給される小さな箱やケースに入っていることが多いです。
そのまま抱っこをして連れて帰りたいお気持ちもわかりますが、病院から出ると周囲の目にも触れるため、可哀想かもしれませんが、受け入れましょう。
赤ちゃんの肌はとてもデリケートで柔らかく、乾燥してしまわないように注意してあげてください。
ハンドクリームのようなクリームタイプでも、ローションのような乳液でも良いので、優しく撫でてあげる感じで、肌へ塗ってあげてください。
成人と違い、赤ちゃんはまだ身体が小さいと思われるかもしれませんが、心臓も内臓もあります。冷やしてあげないといけません。
保冷剤でも構いませんが、一番良いのはドライアイスです。
ドライアイスは、ドライアイス業者へ相談、葬儀社へ相談することで手に入れることができます。
体の上に直接置くのは避けて、タオルを体の上に敷いてから、小さくしたドライアイスを置きましょう。
置く場所は、首の下から上半身を覆うくらいが理想です。
置いたらその上からまたタオルもしくは掛け布団をかけてあげましょう。
手順4、5に関して不安を感じる方は、葬儀社へ依頼した方が良い方です。
迷わず弊社、広島自宅葬儀社の廣田までお電話ください。
TEL 0120-564-594(24時間365日対応)
最寄りの火葬場へ電話しましょう。
広島市の火葬料金は、死産児(広島市在住の方)3,200円、死産児(広島市外在住の方)23,000円です。
【広島市永安館】
広島市東区矢賀町官有無番地
TEL 082-289-1698
9時30分〜16時まで
※夜間は繋がりません、翌朝以降のお電話になります。
詳しくは、広島市永安館(広島市東区)「高天原」火葬場のご案内をご覧ください。
【広島市西風館】
広島市安佐南区伴西2-7-1
TEL 082-848-8279
9時30分〜16時まで
※夜間は繋がりません、翌朝以降のお電話になります。
詳しくは、広島市西風館火葬場(広島市安佐南区西風新都)のご案内をご覧ください。
【広島市五日市火葬場】
広島市佐伯区五日市町大字保井田字稗畑350-134
TEL 082-923-2942
9時30分〜16時まで
※夜間は繋がりません、翌朝以降のお電話になります。
詳しくは、広島市五日市火葬場(広島市佐伯区)のご案内をご覧ください。
【広島市可部火葬場】
広島市安佐北区可部町大字下町屋字高松山
TEL 082-923-2942(五日市火葬場)
9時30分〜16時まで
※夜間は繋がりません、翌朝以降のお電話になります。
詳しくは、可部火葬場(広島市安佐北区可部)のご案内をご覧ください。
葬儀社のサービスを受ける場合は、火葬場の予約も葬儀社が代行してくれます。
お住まいの区役所の1階市民課の戸籍係へ死産届を提出します。
死胎火葬許可申請書は、窓口でいただけるので、その場で記入して提出しましょう。
提出すると「死胎火葬許可証」を取得できます。
必ずこの書類を持って当日火葬場へ行ってください。
お忘れになった場合、火葬を行うことは出来ません。
当日は、火葬予約時間に合わせて自分達で火葬場へ向かいます。
棺は、病院でいただいた箱のままで大丈夫です。
骨壷は普通の容器でも対応してくれますので、一時的に家庭にある容器に収めて、後日購入した骨壷に収める方法、あるいは最初から葬儀社から購入する方法もあります。
火葬場では5分程度のお別れの時間になりますので、自宅を出発する前にしっかり最後のお別れをしてください。
火葬場に到着したら、受付窓口で死胎火葬許可証と火葬料を渡します。
あとは、火葬場のスタッフの指示に従って動いていただければ大丈夫です。
先述した火葬終了までの流れ、1~8までをお読みいただくと、葬儀社にわざわざ頼む必要はないのでは?
このようにお感じになった方もいらっしゃると思います。
実はその通りで、葬儀社の手を借りず、自分達で送ってあげることもできます。
自分達で行いたい方、大切な我が子を他人に触れて欲しくない方、費用をあまりかけられない方はご自身で全て行うことをお勧めします。
一方で葬儀社へ依頼した方が良いという方もいらっしゃいます。
心身ともにお疲れの中、区役所へ死産届の提出へ行ったり、火葬場へ火葬予約の電話をしたり、ドライアイスの準備や骨壷の準備で動いたりするのは、なかなか難しいものです。
それを全て代わりにやってくれるのが葬儀社です。
弊社、広島自宅葬儀社であれば、棺も病院で用意された箱ではなく、赤ちゃん用の白い布張棺をご用意させていただきますし、赤ちゃん専用の骨壷もご用意させていただきます。
また、「死産届け〜火葬予約だけ不安なのでお任せしたい」、あるいは「当日、火葬場での案内だけお願いしたい」など、部分的に葬儀社からのサービスを受けることもできます。
臨機応変にご両親の状況に応じて、より良い方法を一緒に考えますので、自分達だけでは難しいと感じる部分があれば、遠慮なくご相談いただければと思います。
これまで火葬の流れを中心に執筆していますが、葬儀を行う方も中にはいらっしゃいます。
しかしそれはごく稀で、ご両親、祖父母のみ、少人数で行う場合が多いです。
赤ちゃんの葬儀の料金は特に定めていませんので、その時にお支払い出来るもので結構です。
葬儀社として、出来ることは何でもさせていただきます。
わからないことや、ご不明な点がありましたら、いつでも広島自宅葬儀社の廣田を頼ってください。
通常料金は下記の通りです。
■シンプル火葬プラン40,000円(税込44,000円)
プランに含まれる内容
・棺
・骨壷
・死産届・火葬予約手続き代行
・当日火葬場でのサポート
・ドライアイス1日分
※別途、広島市の火葬料金、死産児(広島市在住の方)3,200円、死産児(広島市外在住の方)23,000円が必要です。
※オプションになるサービス
・ドライアイス追加 (税込5,500円)
・寝台車 (税込14,850円)
(退院時、病院から自宅まで赤ちゃんとご両親を乗せて運行するサービスです。)
・寝台霊柩車 (税込14,850円)
(寝台霊柩車は、ご両親に自家用車がない場合や運転が困難な場合に、弊社車輌が自宅前までお迎えに上がらせていただき、赤ちゃんと一緒にご両親を乗せて火葬場まで運行するサービスです。)
A.火葬場ではしっかりとした棺に納棺されていることを義務付けられているわけではありません。それに準ずるものであれば構わないとされています。病院から退院時に小さなケースや箱をいただく場合が多いので、それをそのまま使用して火葬場へ行かれる方が多いです。葬儀社から棺を購入する方というのは、「もっとしっかりした棺に入れてあげたい」というお気持ちを持つ方や、退院時に病院から小さなケースや箱の支給が無かった方という印象です。
A.ご不安かもしれませんが、いざ役所へ行ってみると、窓口で丁寧に説明をしてくださいますので、何もわからなくても大丈夫です。
お母様がまだ入院していらっしゃる時に、お父様がお一人で役所へ行かれるケース、退院してからお二人で行かれるケース、さまざまですが、ご両親に自分達で行いたいお気持ちがあるなら、ぜひ自分達で行ってあげてください。
いきなり役所へ行くのは不安という方は、広島自宅葬儀社へお電話をください。
お代はいりませんので、お力になれることであれば、お力になりたいと思います。
A.はい、それはあります。実際に広島市の場合、一番早い時間で火葬を行う方が多い印象です。
朝は混雑していないため、一番時間をかけて丁寧に調整できるためです。
それは火力だけでなく、お別れの場面から、他の家の方と重ならず、赤ちゃんとご遺族だけの空間になるように配慮され、充分なお別れの時間を設けてくださいます。
そういう配慮された充分なサービスを受けられるのも一番早い時間帯なので、広島市であれば9時30分のご火葬予約がお勧めです。
産婦人科で死産という出来事は、お母様、お父様にとって、とても残酷で辛い出来事です。
ただでさえ辛いことなのに、追い打ちをかけるようなこともあります。
病院内には、これからお母様になろうという方が他にも入院されていらっしゃいます。
否応無しに隣から元気な産声が聞こえてくる場所なのです。
悪気が無くても、やっぱり幸せそうな声、元気な産声が聞こえてくると、余計に辛さが湧き出てきます。
家族では無いはずの葬儀社の私でさえも、その場にいると自然と無念の涙が出てきます。
そんな時、たしかに産声は聞こえなかったけれども、お母様の腕の中で安らかに眠る、しっかりと姿形のある赤ちゃんがお側にいらっしゃいます。
短いけれども火葬当日までの間は、安らかに眠る赤ちゃんと一緒に過ごすことが出来る、最初で最後の貴重なお時間になります。
私としては火葬当日のお手伝いよりも、この父母と赤ちゃんが一緒に過ごせる、最初で最後のお時間に対して、自分がどういうお手伝いができるだろうか。
ここを毎回、真剣に考えています。
火葬が終了したとしても、赤ちゃんはお母様、お父様の心の中でこれからもずっと生き続けていくはずでしょう。
それが少しでも鮮明に、赤ちゃんの顔の表情、抱いた時の重さ、交わした会話、全てをしっかり記憶していただいて、これからもはっきりとお二人の中で赤ちゃんが生き続けていってもらえるように、この最後のお時間にしっかりと思い出を作っていただきたいと思っています。
そのための身の回りのケアをさせていただくのが私の役目と考えています。
ご不安のある方は、広島自宅葬儀社の廣田まで、いつでもご連絡をいただければと思います。
葬儀からだいぶ経っても、遺骨が自宅に置きっぱなしになっている人はいませんか。
『納骨する気力が湧かない』
『お墓を買えない』
『ずっと手元に置いておきたい』など、ご事情はさまざまかと思われます。
遺骨はいつまでも家に置いていいものです。
お墓に納骨しなければならないものではありません。
納骨せず家で供養する『手元供養』の方法について解説します。
『遺骨はお墓に納めなければならない』と決まっているわけではありません。
一般的に、遺骨は四十九日法要のタイミングでお墓へ納骨します。
よって、四十九日を過ぎても骨壺が自宅にあると、親族や友人などから『いつまでも遺骨が家にあるのはよくない』などと言われたり、直接言われることはなくても後ろめたさを感じたりする人はいることでしょう。
しかし、遺骨の取り扱いについて、法的に遺族が気をつけなければならないのは、以下の2点だけです。
遺骨をごみの日に出すなどして勝手に処分してしまったら、遺体の遺棄罪にあたる可能性があります。
例えば自宅の庭に、勝手にお墓を作るなどして、遺骨を埋めてはいけません。
この2点を守れば、遺骨をずっと手元に置いておいてもいいのです。
『そうはいっても、お墓に入れてあげないと故人も浮かばれないのでは?』
『骨壺のままなんてかわいそう』と感じる人もいることでしょう。
しかし、骨壺を自宅に置いておくのは、かわいそうなことでも何でもなく、『手元供養』と呼ばれる立派な供養方法の1つです。
手元供養を行う人は、お墓を持たない人とは限りません。
『愛する人を身近に感じたい』という想いから、お墓があってもあえて手元供養を選んだり、遺骨の一部はお墓へ納骨し、一部だけを手元に残したりする人もいます。
また、故人の希望により散骨したものの、お参りの対象を残しておきたくて少しだけ遺灰を手元に残す人もいます。
2025年1月には、手元供養の事業に取り組む仏具店の関連サービス売り上げが、5年間で1億円を突破したというニュースが報道されました。
このように、手元供養を選ぶ人は、今確実に増えてきています。
参考:「遺骨を近くに」「仏壇に入らない」…手元供養へ遺骨を粉末化、関連サービス売り上げ1億円突破(読売新聞オンライン)

手元供養にはさまざまな方法があります。代表的なのは、以下の5つの供養法です。
手元供養では、特別な骨壺を使う必要はありません。
葬儀で使用した骨壺のままでもいいのです。
仏壇やテーブル、棚の上などに骨壺を安置し、ご先祖様と同じように線香をあげたり、お水やご飯をお供えしたりして供養しましょう。
美しい絵柄のついた骨壺に移し替えて供養する人もいます。
仏壇やテーブル、棚の上などに遺骨を安置し、線香やお水で供養します。
手元供養をする人のために、小さな骨壺がたくさん市販されています。
遺骨の一部を小さな骨壺に移し替え、そのまま仏壇などで供養してもいいですし、お参り専用のミニステージを作るのもいいでしょう。
『ミニ仏壇』といった名称で、仏具店やインターネットで販売されていますが、手作りすることもできます。
ミニステージを手作りする場合は、お盆やプレートにミニ骨壺を載せ、小さな線香立てを置き、小さなコップにお水を入れてお供えすれば完成です。
骨壺のそばに遺影を安置すると、お参りの際にもっと故人を近くに感じることができるでしょう。
ミニ骨壺に納まらなかった遺骨は、合祀墓に納骨したり、散骨したりして手放すのが一般的です。
葬儀のときに使った骨壺に再び納骨して、ミニ骨壺の後ろなどに安置しておくという方法もあります。
手元供養への理解が進んだ現代では、あらかじめ骨壺を収納するスペースがついている仏壇が市販されています。
見た目は一般的な仏壇と変わりませんが、上段には位牌や遺影などを安置してお参りでき、下段に骨壺を納められるスペースがついているタイプです。
下段にある骨壺は、仏壇の扉を閉めてしまえば外から見えることはありません。
手元供養をしていることを、訪問者に知られたくない人にもおすすめです。
『故人をいつも近くに感じていたい』という人のなかには、遺灰をペンダントトップなどに込められるアクセサリーを作る人もいます。
遺骨アクセサリーには、ペンダントの他、指輪やブレスレットもあります。
遺骨アクセサリーに使う遺灰はほんのわずかです。
使われなかった遺骨は、ミニ骨壺に納まりきれないときと同様、合祀や散骨を選んだり、もともとあるお墓に納骨したりするのがいいでしょう。
手元供養を行うときは、以下の4つに注意しましょう。
先述したように、お墓として許可を受けていない場所に遺骨を埋めると、法律違反になってしまいます。
庭などに骨壺を埋めるのは、やめましょう。
骨壺はあくまで家の中に安置して、供養を行います。
遺骨は湿気に弱く、適切に管理しないとカビが発生してしまうおそれがあります。
長く自宅に安置するときは、湿気の多い場所に置かない、骨壺に乾燥剤を入れるなどの方法でカビから守りましょう。
手元供養を行いたい旨をしっかり家族や親族に伝えて、理解を得ましょう。
親族が遺骨の手元供養を知らなければ、お墓参りのとき故人の遺骨が納骨されていると信じてお祈りしてしまう可能性があります。
身近な人に説明するときには、『遺骨が手元からなくなってしまうと寂しいから』
『お墓を買うかどうか迷っているから』など、手元供養を選ぶ理由を添えるのが大事です。
『大事な親族の遺骨が納骨されず、放置されている』と感じてしまう人もいるため、丁寧にご自身の意思を伝えてください。
手元供養は、自宅で遺骨を供養する人がいるからこそ選べる供養法です。
ご自身が遺骨を供養できなくなったときのことを、考えておく必要があります。
家族と同居しているのであれば差しあたり不安はありませんが、1人暮らしの場合は手元供養を離れた家族などに引き継げるかどうか確認しておきましょう。
もし手元供養を引き継いでくれる人がいない場合は、お墓への納骨、合祀墓への納骨、散骨など、将来どのように遺骨を手放すかを考えておきましょう。
『自分の遺骨と一緒に、手元供養していた故人の遺骨も散骨してほしい』などと、家族に希望を話しておく人もいます。
手元供養は、自分で供養の方法を考えることができる自由な供養法といえます。
玄関先にミニ骨壺と遺影を安置して、毎日『いってきます』『ただいま』を言うこともできますし、寝室のサイドテーブルに祈りのステージを作って、1日の始まりと終わりに故人へ挨拶することも可能です。
書斎の本棚の一角に、祈りのスペースを作る人もいます。
また、祈りの形も多種多様です。
線香やお水をお供えするのは一般的な方法ですが、必ずそうしなければならないわけではありません。
故人が気に入っていたお菓子をお供えしたり、一輪挿しにお花を活けたり、お財布や愛用していたペンなどの遺品を添えたりなど、いろんな形で供養ができます。
ぜひ、オリジナルなアイデアで、遺骨の供養をご自身のライフスタイルに組み込んでください。
「遠い親戚の遺骨を引き取ってしまった」
「お墓を購入する余裕がない」など、やむを得ない事情で遺骨を手放したいと考えている方もいることでしょう。
遺骨はごみとして処分することができないので、適切な供養が必要です。
数ある選択肢の中でも、なるべく安価に、かつ安心して遺骨を手放せる方法を解説します。
遺骨は、ごみに出すなどして処分することができません。
刑法第190条の「死体損壊・遺棄罪」にあたる可能性があるためです。刑法190条には、以下のように記されています。
刑法190条
(死体損壊等)
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
このように、死体損壊・遺棄罪は、遺体だけでなく、遺骨を遺棄した場合でも当てはまってしまいます。
よって、「処分」ではなく「供養」しなければなりません。
長らく遺骨の「供養」といえば、先祖代々のお墓に納骨するのが一般的な方法とされてきましたが、最近ではさまざまな供養方法があります。
それらの中から、なるべく費用を抑えて、安心して遺骨を供養できる方法をご案内します。
「送骨」とは、お寺や霊園に遺骨を送ることです。
遺骨はゆうパックで郵送することができます。
送骨を受け付けているお寺や霊園に、ゆうパックで遺骨を骨壺ごと郵送すると、そのまま永代供養を行ってくれる仕組みです。
永代供養とは、お墓の管理や供養を家族が行わず、お寺や霊園が行ってくれる供養のシステムです。
つまり永代供養を選ぶと、お墓参りやお墓掃除をする必要がありません。
年間使用料もいりません。
送骨の場合、たくさんの遺骨が眠る永代供養墓に、骨壺から遺骨を取り出して納骨することで供養されます。
そして一度お寺に遺骨を送れば、そのままそのお寺に遺骨の供養をお任せできます。
送骨は、3万円程度から受け付けているところがあります。
骨壺から遺骨を取り出して、他の人の遺骨と一緒に合祀(ごうし)されるため、後から個別に遺骨を取り出すことができません。

散骨とは、遺骨を粉末状にして海や陸へ撒くことです。
以前は違法と思われていましたが、散骨を明確に禁止している法律はなく、散骨を行う人が増えるにつれて徐々に市民権を得てきました。
現在は全国にたくさんの散骨事業者がいて、安心して散骨を任せることができます。
散骨は陸地でも可能ですが、海洋散骨を行っている事業者の方が圧倒的に多いのが特徴です。
他の人の迷惑にならない場所で散骨しなければならず、陸地では散骨に適した場所を探すのが難しいためです。
ただ、「自分名義の山を持っている」など、他の人に迷惑がかからず、かつ自分の所有地であり、条例で散骨が禁止されていない自治体内なら問題なく散骨ができます。
また、他人名義の土地であっても、土地の所有者から許可された場所であれば散骨が可能です。
ただし後でトラブルにならないよう、土地の所有者に散骨を許可した旨を一筆書いてもらうなどしておきましょう。
事業者に散骨を依頼する場合、依頼主が散骨に立ち会わない委託散骨の相場が1体5万円です。
依頼主が散骨に立ち会う場合、複数の遺族が同じ船に乗る合同散骨で10~15万円、単独で船をチャーターする個別散骨で20~30万円程度です。
自分で散骨を行う場合、もしご自身が所有する山などに散骨を行う場合は、0円から散骨が可能です。
ただし遺骨をパウダー状に粉骨しなければならず、周辺への配慮も必要になるなど金銭面以外での負担が大きいのがデメリットです。
散骨するとお墓がないため、手を合わせる場所がなくなります。
他の親族にもその旨をしっかり説明しましょう。
なお、いつ、どこで散骨を行ったかを記載した「散骨証明書」を発行してくれる事業者を選びましょう。
まだ火葬がされていない段階でのみ、可能な方法です。
一部の火葬場では、火葬の後に遺骨を引き取らないことを選択できます。
遺骨を持ち帰る必要がないため、骨壺もいりません。
骨壺料金の必要もないという意味では、今回ご紹介する中で最も金銭的負担の少ない方法です。
ただ、一般的な方法ではないため、葬儀社や火葬場に相談しても許可が得られない場合が多々あります。
そのことを理解した上で、なるべく早めに希望してみましょう。
送骨や散骨は、事業者に遺骨を郵送する手間と費用がかかります。
なるべく自分の負担を減らしたいと考えるなら、永代供養を行っている近隣の寺院を探してみてはいかがでしょうか。
郵送ではなく、自分の手で骨壺を埋葬場所へ運ぶ方法です。
「永代供養」「宗教・宗派不問」といった文言が看板に掲げられていて、合同で埋葬してもらえる大きな永代供養墓があるお寺が近所にあったら、供養の費用について相談してみましょう。
数万円で供養してもらえるようであれば、送骨先や散骨先を探すよりも、負担なく遺骨を手放せます。
納骨堂とは、たくさんの遺骨が納骨されている屋内施設です。
個別にスペースを設けている納骨堂は費用が高いですが、大きな1つの納骨堂にたくさんの人の遺骨を埋葬する合祀型納骨堂であれば、費用はぐっと抑えられます。
近隣の納骨堂施設に、合祀型納骨堂が設置されていないかどうか調べてみましょう。
合祀型納骨堂の費用相場は、5万円~30万円程度です。
送骨同様、骨壺から遺骨を取り出して他の人の遺骨と一緒に埋葬されるため、後で個別に遺骨を取り出すことはできません。
樹木葬とは、墓石ではなく樹木を墓標として、樹木のそばに遺骨を埋葬するお墓です。
一本の大きな木をシンボルツリーとして周りに納骨するタイプが主流ですが、個別にスペースを設けて1本の木を独占するタイプもあり、また大きな納骨スペースを作ってたくさんの遺骨をまとめて納骨する合祀型もあります。
樹木葬の中では、合祀型が最も費用を抑えられる形式です。
近隣に樹木葬霊園がある人は、合祀型の樹木葬を扱っているかどうか、調べてみましょう。
合祀型樹木葬の費用相場は、5万円~20万円程度です。
合祀型納骨堂と同様、後で個別に遺骨を取り出すことはできません。
なお、契約時には埋葬費用以外の費用が発生しないかどうか、しっかり確認しましょう。
プレートに名前を刻むための彫刻代などが別途必要な場合もあります。
なかには、古いお墓から取り出された先祖の遺骨を引き取るなどして、複数の遺骨の処分に困っている方もいるでしょう。
送骨、委託散骨、合祀型といった供養法において、費用は「一体あたり」の金額です。
いくら費用が抑えられるといっても、遺骨がたくさんある場合はかなりの出費になってしまいます。
もし遺骨が複数あって困っているなら、依頼を検討しているお寺や霊園、散骨事業者に相談してみましょう。
「一体あたりではなく、骨壺1つあたりでよい」と返答してくれるところがあります。
複数の遺骨をまとめることで骨壺の数を減らせれば、費用負担が減ります。
骨壺の中の遺骨は、年数が経つにつれて水分が失われ、かさが減ってきます。
骨壺が複数あって困っている人は、まずは骨壺を開けてみるのがおすすめです。
後飾り祭壇には、二段のものと三段のものがあります。
いずれも基本的な飾り方は同じですが、二段の場合はスペースが足りず、一方で三段の場合はスペースが余り、困ることもあるでしょう。
二段の場合と三段の場合、いずれも詳しい飾り方を徹底解説します。
なお、地域の風習や宗派によって飾り方が違う場合もあるため、周囲に相談しながら飾るのがおすすめです。
最初に後飾り祭壇の基本的な飾り方を解説します。
基本は、至ってシンプルです。
上段、または一~二段目には、故人にまつわるものを安置します。
お参りのとき、祈りを捧げる本体となるものを上に安置するという考え方です。
具体的には、位牌、遺影、遺骨があります。
下段、または二~三段目には、故人へのお供えを飾ります。
いただいた供物のほか、線香も広い意味では「故人にお供えするもの」です。
具体的には、果物、菓子、弔辞、弔電、焼香のためのロウソクや線香類を飾ります。
つまり、「上の段に安置されている故人ゆかりのものに向かって、お供えやお祈りをする」というイメージで、ものを配置していきます。
このイメージを守れば、基本的な配置に迷うことはないでしょう。
基本を踏まえた上で、まずは二段飾りの飾り方を解説します。
上の段は、祈りの対象となるものを安置する段です。
一番上の段に、向かって左から遺影、位牌、遺骨の順番に並べます。
位牌が中央に来るよう調整するのが大事です。
白木の位牌は背が高いため、ぐらつきが心配になる人もいるかと思われます。
後飾り壇は日常的に動かすようなものではないのであまり心配はいりませんが、周囲で子どもが活発に動き回るなど、位牌が倒れやすい環境の場合は、位牌の足底部分に粘着テープを貼るなどの対策を検討しましょう。
祈りの対象である位牌に粘着テープを貼ることに、戸惑いを覚える人もいるかもしれません。
しかし何回も倒れた結果、破損する可能性もあります。
また、白木の位牌は四十九日法要のとき塗りの位牌に魂を入れ替え、処分するものです。
安全性の確保を何より大事にしましょう。
下の段には、故人へのお供えを配置します。
供物としていただいたお菓子や果物、お水を両脇に配置し、中央には黒いお盆を置いて、その上に弔辞や弔電を重ねましょう。
後飾り壇の手前に経机を置くスペースがない場合は、焼香のための仏具を下段に配置します。
下段の中央に、ロウソクと線香立て、小さい「おりん」などの仏具を置きます。

陰膳(画像のような、故人のためのお膳)を置いても構いませんが、置くものが多く配置できなかったり、お膳が大きい場合は不安定になったりすることもあります。
その場合は無理せず、後飾り祭壇の手前にテーブルを置いてお供えするのがおすすめです。
後飾り祭壇の手前に経机(小さなテーブルでも可)を置き、お線香をあげるための道具を配置します。
ロウソク、線香、線香立ての他、小さな「おりん」や一輪挿しを置く場合もあります。
なお、供花は花瓶に立てて後飾り祭壇の手前か脇に置きます。
線香立ての前に座布団を敷き、大きい「おりん」や木魚は、座布団の左右に並べます。
後飾り祭壇の飾り方は、三段の場合も、二段と基本は変わりません。
二段よりもゆったり飾れるため、飾り方を工夫するのがポイントです。
一段目の左側に遺影、右側に遺骨を置き、中央は空けておきます。
二段目の中央に位牌を安置します。
位牌を二段目に安置する理由は、白木位牌の背が高く、一段目では不安定になりがちだからです。
ただ、本来は位牌がお参りの対象として最も大事なものであり、菩提寺によっては位牌を一段目に安置するようアドバイスをいただくかもしれません。
その場合は、菩提寺のアドバイス通りにしましょう。
位牌の両脇を飾るお供えには、果物類や菓子を高く積んだものなど、高さのあるもの、見栄えのするものが適しています。
お水や陰膳をこの二段目に置くケースもみられます。
三段目の中央には線香立てやロウソクなど、お参りのための仏具を配置します。
仏具の左右には、菓子や陰膳、お水、いただいた弔辞・弔電などのお供えを配置します。
とくに置くものがなければ、仏具だけでも構いません。
後飾り祭壇の手前に、座布団を置きます。
お供えするものがたくさんあったり、日頃から経机に仏具を置いてお参りをする習慣があったりする場合は、後飾り祭壇の手前に机を置き、そこへ仏具を配置します。
二段目と同様、供花は花瓶に活けて、後飾り祭壇の手前か脇に置きます。
机の前に座布団を敷き、大きい「おりん」や木魚は、座布団の左右に並べます。
以上、後飾り祭壇の飾り方について解説しました。
飾り方に迷う人のため詳細に解説しましたが、「故人にまつわるものは上段、お供え物は下段」という基本的なルールを守れば、飾り方は自由です。
地域や菩提寺の考え方も参考にしながら、故人を偲ぶ気持ちを一番大切に飾り、心を込めて日々のお参りを行いましょう。
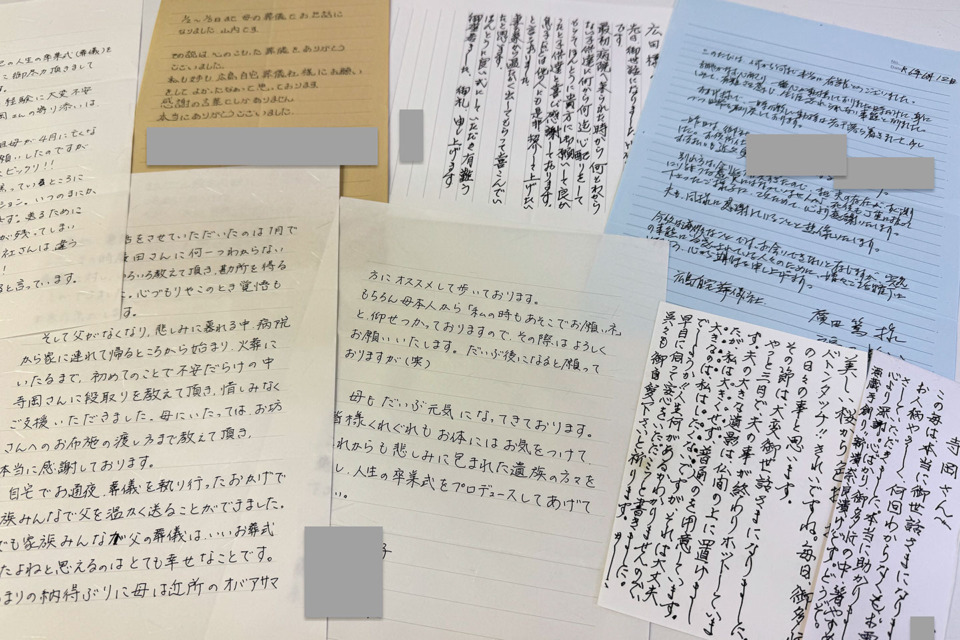



元々、廣田は全国各地で葬儀会館を運営する大手葬儀社に20年間勤務、当時は広島の責任者を務めていました。
ある日、母が脳梗塞で倒れたことがきっかけで様子が変わります。母は半身麻痺、要介護5と診断され、母のサポート役になるはずの父は癌が見つかり、闘病生活へ。
自宅が大好きで、病院嫌いであった母のため、廣田は自宅で母と一緒に暮らす道を選択しましたが、仕事と介護の両立は困難でした。
「自宅で母の介護を続けたい。」
「勤め先にあまり迷惑はかけられない。」
20年お世話になった会社を退職し、介護に専念する苦渋の決断を致しました。



それから月日が流れたある日、
「母がもしも亡くなった時、葬儀はどうする?」
ふと疑問が浮かびました。
「母が喜ぶのは、このままこの家から送り出すことだろう。」
「じゃあ、どこの葬儀社に依頼する?」
廣田は、これまでの経験上、自宅で葬儀を希望しても、多くの葬儀社(現場担当者)は内心嫌がること、「自宅葬できます」と謳っている葬儀社であっても、現場担当者は、あれこれ理由をつけて葬儀会館での葬儀を勧めてくるとわかっていました。
「それでも自宅でやりたいと言えば・・・、家族にとって満足のいく葬儀にはならないかもしれない。」
広島の葬儀社なら幾つも知っているはずなのに、母の自宅葬を快く引き受けてくれそうな葬儀社は浮かびませんでした。
他の葬儀社様を否定しているつもりはありません。広島には、今日もご遺族のために一生懸命頑張っている方はたくさんいらっしゃいます。
でも誰が担当でも心の底から私たち家族の気持ちに寄り添ってくれる葬儀社はあるのか。
誰が担当でも「自宅葬を叶えてあげよう」を最優先で頑張ってくれる葬儀社はあるのか。
誰が担当でも「手間」、「時間」、「お金」などの労力を惜しまず、ご家族へ一心に奉仕できる人間が集った葬儀社はあるのか。
そう考えると全幅の信頼でお任せ出来る葬儀社は、思い当たりませんでした。

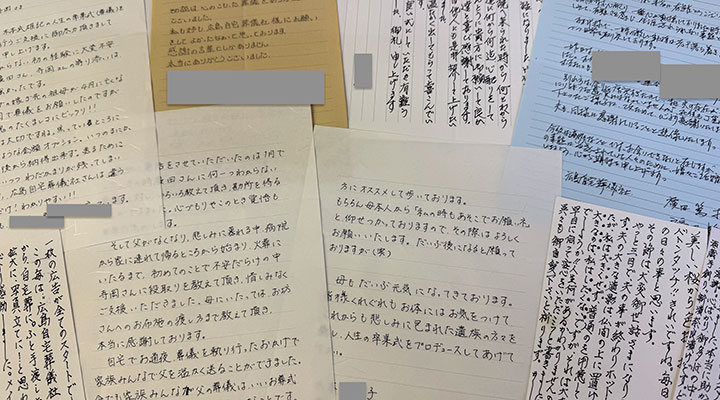

母にとって最良な答えは何か、考えた結果、
「母の葬儀は自分がやるしかない」
葬儀の仕事も母の勧めで始めたもの、成長した姿を見てもらおう。
母の葬儀だけでなく、同じように自宅葬を希望する方の一番の味方になろう。介護の苦労や気持ちもわかってあげられる自分ならお役に立てるかもしれない。
広島自宅葬儀社は、ここから始まりました。一緒にやろうと集まったメンバーは、人柄を最も重視。
それぞれ性格は異なりますが、誰もが「手間」「時間」「お金」を惜しまず、ご家族へ一心に奉仕できる、世間一般で言われる、「いい人」です。誰もが心の底からご遺族様の気持ちに寄り添える優しい心と、ご遺族のためなら何だって叶えてあげたい情熱を持った、頼もしい集団です。
当初は自宅葬のみの取り扱いでしたが、「自宅葬は考えていないけれど、葬儀は広島自宅葬儀社にしてもらいたい」
おかげさまでこのようなお声をかけていただく機会が積み重なって、今では、自宅葬だけでなく、直葬、葬儀場での家族葬、お寺・集会所で行う家族葬を広島県内全域でお手伝いさせていただく葬儀社となりました。
昨今、生活するだけでも大変と感じる世の中になりつつあります。こんな時だからこそ、利益よりもお役に立つことが最優先。
お金をかけなくても心のこもった良いお葬式は出来るという安心を、広島県の皆様へ届けることも、私たちの存在意義だと考えています。
これからも誠実に、正直な情報を皆様へお届けしてまいります。いつまでも初心を忘れず、広島自宅葬儀社は、生まれ育った広島で、どんな葬儀社よりも寄り添い、不安のない葬儀と明日への一歩をお支えいたします。
ご相談は無料
24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも
フリーダイヤルへご連絡ください。
「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は
メールでのご相談も可能です。
ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
