ご依頼・ご相談の方はこちら
ご相談は無料
24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも
フリーダイヤルへご連絡ください。
「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は
メールでのご相談も可能です。
ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
広島県内には数多くの火葬場があります。それぞれの場所で設備や大きさは異なりますが、およその流れは同じです。
他県では火葬を済ませてから葬儀を行う地域もありますが、広島県は葬儀を終えてから火葬の流れになります。
この記事では、お葬式が終わって出棺した後、火葬場ではどのような流れで進むのか、
そしてどのようなことに注意していけば良いのかをアドバイスさせていただきます。
葬儀場から火葬場へ向かう場面を出棺(しゅっかん)と言います。
喪主は霊柩車、その他のご親族は自家用車、マイクロバスなどで火葬場へ向かいます。
火葬場へ到着すると、斎場職員が出迎えてくれます。
霊柩車から棺を降ろされ、斎場職員が棺を火葬炉まで運びます。
故人が火葬炉へ入る前に最後のお別れが行われます。
お別れの方法は火葬場により異なりますが、主に焼香(玉串奉奠)を行います。
この際にご対面出来る火葬場と出来ない火葬場があります。
お別れの後に火葬炉へ向かう故人をお見送りします。
火葬終了までおよそ1時間15分〜1時間30分かかります。
この時間は少し心休まる時間にもなります。
現在多くの火葬場が、待合室を設けているところが多く、施設内も綺麗であることから、この待ち時間に食事をする方が多いです。
食事は火葬場でお買い求めするのではなく、火葬場へお弁当を持ち込む方が多いです。
多くの葬儀社が、段取り、配膳までを代行してくれます。
斎場職員から収骨時間の知らせが入ると、収骨室へ移動します。
喪主をはじめ、親族が交代で遺骨を骨壷内に収めます。
一つ一つ丁寧に説明してくださる職員の案内を聞きながら行いましょう。
広島では全ての遺骨を収骨はせず、一部の遺骨のみ骨壷に収めます。
収骨を終えると火葬場を出発です。
ここで解散し、各々が帰路へ着く場合もありますし、葬儀場・自宅に戻ってから初七日法要を行う場合もあります。
ここからはそれぞれの場面での注意点を解説していきます。
まず火葬場へ向かう際に気をつけたいことです。
これは本当の話ですが、あるお葬式でA火葬場へ向かったのですが、ご親族のお一人だけB火葬場へ向かってしまいました。
火葬場の場所は事前に確認し合っておきましょう。
火葬場へ行く手段は、どうするのか。自家用車で対応する場合は、誰の自家用車を出すのか、合計何台出すのか、そこまで決めておきましょう。そして出発の時も何台で出発したのか確認は必須です。
理由としては、自家用車が何台出たのか把握していないと、火葬場到着時に点呼が出来ないからです。
誰が火葬場へ向かうのか、合計何名なのか、出発時に把握しましょう。
こちらも把握していないと火葬場で点呼が取れません。
・コロナ禍では人数を最小限
コロナ禍では、多くの方が火葬場へ向かうことは避けましょう。
最低限の人数で行くことが求められていますので、協力をしましょう。
広島県ではお寺様が、火葬場へ同行される場合もあります。
火葬前に、火葬炉の前で読経を行なっていただきます。
予め同行される予定なのかどうか、確認が必要です。
火葬場へ着くと、まず全員揃っているのか、点呼が必要です。
火葬炉の前で最後にお別れの時間があります。
これに渋滞で遅れて間に合わない、道に迷って間に合わないということもあります。
間に合わない方を待ちたい心情はとても理解出来ますが、正直待つことは困難です。
予め予約した時間を守らないと施設全体に迷惑がかかってしまいます。
ですから、後から遅れてしまう人を出さない工夫と、後から遅れてしまうことは最後のお別れには参加出来ないことを予め認識しておくことが必要です。
火葬炉の前で最後のお別れはありますが、棺に蓋が開いて対面できるとは限りません。
近年、対面出来る火葬場は広島県も少なくなっています。
心残りのないようにお葬式でしっかりご対面しておきましょう。
また、この場面で対面が出来るのかどうか、事前に葬儀社スタッフへ確認しておきましょう。
火葬場では、待ち時間が1時間15分〜1時間30分あります。
待ち時間に食事をする方が多いのですが、コロナ禍では極力控えるよう求められています。
どうしても食事を行う場合は、隣の人との会話をせず静かな会食をしましょう。
お弁当を食べる場合、お茶はどうするのか。事前に確認しておきましょう。
火葬場に無料で設置されている所もあれば、自分達でやかんに湯を沸かしてお茶を作る所もあります。
火葬場で有料のペットボトルを購入する方、葬儀場からキーパーにお茶を入れて持ち込む方もいらっしゃいます。葬儀社に確認をするとよいでしょう。
帰りは遺骨を持つ人と遺影写真を持つ人が必要になります。
誰が持つのか確認をしておきましょう。
斎場職員からいただく埋葬許可証は、再発行が出来ません。
納骨する時に必要な書類になりますから、紛失しないように大切に保管してください。
誰がどこへ保管するのか、周囲も知っておくと良いと思います。
火葬場から葬儀場へ戻って初七日法要がある場合、自宅へ戻る場合もあります。
場合によってはお寺へ寄って初七日を行うこともあります。
参加する方で共有を図りましょう。
親が認知症になってしまったとしても、それを理由に子世代が銀行のお金を管理したり、親所有の不動産を売却したりといったことは、簡単にはできません。
とはいえ、自分でさまざまな判断ができなくなってくる親の財産を、なんとか守ってあげたいと思う子どもは多いでしょう。
親が元気なうちに任意後見制度を利用しておくのがおすすめです。
後見制度の種類や利用方法、親に「利用しよう」と話を切り出すときに参考となるフレーズをご紹介します。
超高齢化社会を迎えた今、認知症になってしまうのは、誰にとってもありえることです。
厚労省によると、2025人には65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されており、シニアはもとより子世代においても、認知症は他人事ではない、重要なテーマといえるでしょう。
認知症になると、記憶力や判断能力の低下により、金銭管理が正しくできなくなる恐れがあります。
「年金の支給日に、スーパーでお金を使い切ってしまった。
しかも生の魚や肉を大量に買うなど、結局は使い切れず捨てなければならないものばかり」
「特殊詐欺に巻き込まれ、大金を失ってしまった」
そんなトラブルが起こっています。
大事な老後資金を守るため、子どもが「一肌脱ごう」とお金を管理しようとしても、親が認知症になってからでは、できることがあまりありません。
親名義の預貯金を子どもが引き出すのは簡単ではなく、認知症ともなればなおさら「後見人を立てて、また来てください」といわれる可能性は高いでしょう。
子どもといえども、銀行にとっては「利用者本人以外の人」。
本人でも、正式な代理人でもない人に利用者の預貯金を引き渡すのはできないという考えからです。
もっとも、「認知症の親のお金を引き出したい」という子世代の相談が増加したこともあり、銀行業界の対応は柔軟になりつつあります。
2021年には、一般社団法人全国銀行協会が、金融取引の代理等に関する考え方をまとめた指針を出しています。
そこには、高齢の顧客や子世代などの代理人と金融取引を行う際のポイントが記載されています。
参考:金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について
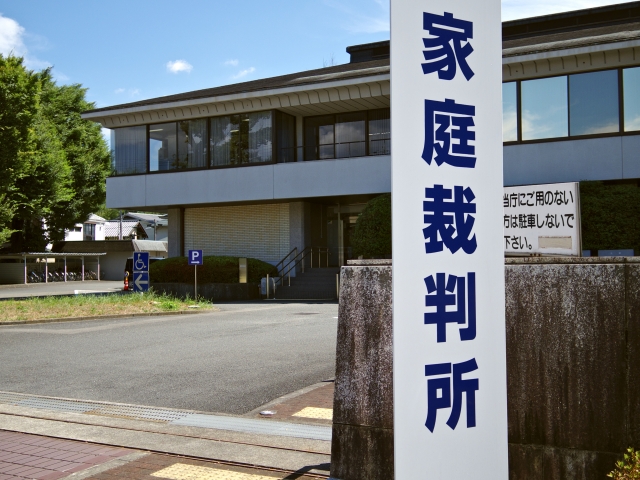
銀行の対応が今後柔軟になる可能性があるとはいえ、実際の対応は、各銀行によってさまざま。
不安な人は、早めに対策をしておいた方がいいでしょう。
親の正式な後見人になれば、親の財産を適切に保護したり、重要な手続きや契約を補佐したりすることが可能になります。
認知症者のほか、子どもや脳に障がいを持った人などの後見人を決める制度は「成年後見制度」といわれ、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
成年後見制度のうち、法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になってから利用する制度です。
本人は後見人を自ら選べないため、家庭裁判所によって後見人が選任されます。
このとき、必ずしも身内が後見人に選ばれるとは限りません。司法書士、弁護士といった専門職が選ばれることもあります。
任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、本人の意思で後見人や後見内容を決めておく制度です。
本人が後見人を決めるのですから、子世代を指定しておけば、認知症になった際には子世代がしっかりと財産を管理することが可能になります。
以上のように、認知症になってから対策しようとすれば法定後見制度を利用するしかなくなり、家族が後見人に選ばれない場合もあります。
親の財産管理を第三者へ一任することに、抵抗を感じる人も少なくないでしょう。
可能であれば、任意後見制度を選択したいところです。
任意後見制度を利用する場合、流れは以下の通りです。
本人の判断能力が確かなうちに、契約を結びます。
まずは、後見人と契約内容を決定した上で公正証書を作りましょう。
契約内容は、「財産の管理はどうするか」「介護をどこで受けたいか」「病気になったらどの病院で治療を受けるか」などの視点から、なるべく具体的に決定します。
契約内容がまとまったら公証役場へ行き、公正証書を作成します。
公正証書が作られたら、法務局へ出向き、後見登記の依頼を行います。
本人が認知症などになり、判断能力が低下した時点で、契約内容を実行するため任意後見監督人選任の申立てを行います。
任意後見監督人とは、本人の財産が後見人によって適切に管理されているかを監督する立場です。
司法書士、弁護士といった専門家が選ばれることが多いでしょう。
申立て書類を管轄の家庭裁判所に提出し、任意後見監督人が選ばれるのを待ちます。
任意後見監督人の選任がなされたら、任意後見人は本人の財産を、責任を持って管理し、そのほか健康支援などを行います。
任意後見制度を利用する際には、以下の3点について注意しましょう。
法定後見制度であれ、任意後見制度であれ、成年後見制度の第一目的は、本人の権利を守ることです。
親と子どもという関係性であっても、子どもが後見人になるのは「親のお金を管理するため」だけではなく「本人の財産を守り、金銭的にも身体的にも保護や支援を行うため」であることを、しっかり認識しましょう。
後見人になったその日から、本人の財産を動かすときには、例え少額であっても記録が必要です。
財産目録を作成し、定期的に財産の管理状況を任意後見監督人へ提出することになります。
同居家族であればなおさら、財布を分けて管理するのは難しいもの。
しかし、監督人にしっかり報告するために、「本人のための費用は本人の財産から」を徹底したいものです。
任意後見監督人へ、毎月報酬を支払う必要があります。
相場は、一ヶ月あたり1万円から3万円程度で、管理財産の金額によって違う場合も。最初にきちんと確認しておきましょう。
親に「認知症になったときのために、今のうちに後見契約を行っておこう」と切り出すのは、とても難しいものです。
しかし、いざ親が認知症になってしまうと、任意後見制度を選択できなくなり、子世代が後見人になれない可能性があります。
まずは親が「認知症」に対してどれほど不安を抱えているのか、知ることから始めましょう。
例えば、以下のようなフレーズで親の反応をうかがってみるのはいかがでしょうか。
先述のように、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されています。
こういった情報や、ニュースの関連記事をきっかけに話題を振ってみると、親が認知症についてどう思っているかがわかるでしょう。
あくまで「心配している」をベースに、高額な買い物や電話の詐欺などのトラブルに巻き込まれていないかを探ります。
「●●さんの家、詐欺の電話がかかってきたって」など、近隣の情報を使うのもいい手です。
まだまだ元気な親にそんな声をかけると、「いやいや、自分だってどうなるか分からないよ」と、謙遜の言葉が聞こえることも。
「この前も、○○の用事を忘れた」など、自分の今を開示してくれるかもしれません。
判断能力が鈍ると瞬時に小銭を数えられなくなるため、お札を出しておつりをもらうことが多くなり、財布が小銭で膨らんでゆくというのは、よく知られたエピソードです。
買い物のついでなどに、話を振ってみるのもいいでしょう。
任意後見制度は、最初の手続きこそ面倒で月々の報酬もかかりますが、親の生活を子どもが直接保護するため有効な方法です。
なお、親のお金を適切に管理するためには、任意後見制度のほかに、金融機関が取り扱う家族信託を利用する方法もあります。
いずれにせよ、「子どもの自分が楽になるため」ではなく「親の生活を安全、安心にするため」の制度利用だということを忘れずにいましょう。
家族みんながずっと笑顔であるために、親が元気なうちから対策するのが大事です。
広島県福山市にある火葬場、沼隈斎場についてご紹介させていただきます。

・住所 広島県福山市沼隈町大字常石7134番地1
・TEL (084)928―1069
・駐車場 20台
・斎場受入時間 9:30〜16:00
・休館日 1月1日、1月2日
・12月31日は正午までの受入となります。
●交通のご案内

・タクシーの場合
JR山陽本線 松永駅から20分
JR山陽本線 福山駅から30分
・自家用車の場合
山陽自動車道 福山西ICから25分
福山市沼隈支所から6分
福山市西部市民センターから20分
福山市内在住の方 12歳以上 8,000円
福山市外在中の方 12歳以上 24,000円
福山市内在住の方 12歳未満 5,000円
福山市外在中の方 12歳未満 15,000円
ご利用の際の注意事項と棺の中に入れてはいけないものをご案内させていただきます。
・出棺時間を厳守しましょう、予約時間に合わせて到着をお願いします。
・斎場の職員より火葬執行印を押印した「死体(死胎)火葬(埋葬)許可証」をいただきます。墓地などの納骨の際に必要になりますので、紛失しないよう大切に保管してください。
故人様を偲んで愛用品などを、棺に収めたいというお気持ちは理解しておりますが、火葬中のご遺骨の損傷、有害物質の発生、火葬時間の延長に繋がります。
下記のものは、棺の中に入れないようにご注意ください。
・化学繊維製品・プラスチック類(グローブ・玩具・釣竿・ぬいぐるみなど)
・ガラス類、金属製品(酒瓶・ビール瓶・指輪・腕時計・メガネなど)
・燃えにくいもの(厚い着物・アルバム・衣類・寝具・果物・ドライアイスなど)
・危険物(電池・ガスライターなど爆発性のあるもの)
※ペースメーカーには、リチウム電池が入っており「破裂事故」を起こす可能性があり、大変危険です。取り出せない場合はその旨を事前に斎場職員に伝えましょう。
墓地などへ納骨をする際に、墓地管理者へ提出する「死体(胎)火葬(埋葬)許可証を係員からいただきます。
納骨まで大切に保管しましょう。
当日に分骨を希望される場合、斎場職員にお申し付けください。
分骨証明書(納骨の際に必要)を発行します。(手数料300円かかります)
※墓地または納骨堂に納骨した後に分骨を行う場合は、納骨している墓地の墓地管理者が証明することになります。
福山市沼隈斎場 葬儀受付相談 TEL 0120-564-594
福山市沼隈斎場で火葬をご検討中の方、葬儀についてのご相談を、24時間365日いつでも承ります。
■ご火葬のみ(直葬)プラン
葬儀一式70,000円(税込77,000円)
・ご搬送 ご逝去場所〜霊安室へお預かり安置
・ご搬送 霊安室〜火葬場
・搬送シーツ
・棺(布団など一式)
・骨壷(骨箱、風呂敷など一式)
・ドライアイス
・死亡届手続き代行
■火葬料8,000円
(福山市民8,000円 福山市民以外の方24,000円)
■総合計85,000円
※事前にご相談いただいた方は、上記価格より5,000円割引させていただきます。
■プランの流れ
お迎え〜霊安室へ搬送。霊安室でのご対面は出来ません。
翌日、火葬予約時間に合わせて沼隈斎場にお越しいただきます。
火葬前には、炉前で短時間のお別れするお時間がございます。
■対応地域
福山市全域
■オプションになるもの
・花束 5,500円(税込)
・お別れ花 22,000円(税込)
・遺影写真 19,800円(税込)
・お寺様による炉前読経 16,500円(税込)
※別途お布施35,000円が必要となります。
詳しい詳細は、下記からホームページでご覧ください。
詳細は下記からご確認いただけます。
この記事では広島の葬儀を20年見てきた筆者が、広島の家族葬はどんな流れで進んでいくのか。
具体的に知りたい方へ時系列と共にわかりやすく解説させていただきますのでご覧ください。
現在、広島県の葬儀は7割くらいが家族葬と言われています。
葬儀の主流が家族葬になっています、特別なものではなくなっています。
通常の葬儀と異なるのは、人数の大小のみであり、流れ自体は通常の葬儀と変わりません。
そして広島県に住む方の多くは、昔から安芸門徒と言われるくらい浄土真宗の門徒様が多い地域です。
したがって葬儀の流れは、この浄土真宗の流れに沿った形で生まれているのが特徴です。
家族葬の日程は、通夜の日、葬儀の日と2日間で行われることが多いです。
広島県内の火葬場は、友引でも営業をしています。元旦以外は稼働しているところが多く、ほぼ年中無休と言えます。
ですから火葬場の都合で日程がずれることが少ないため、すぐに通夜・葬儀となるケースが多いのが特徴です。
しかし例えば夕方6時に訃報が発生した場合、火葬は死亡後24時間経過しないと出来ません。つまり翌日夕方6時以降でなければ火葬は出来ないことになります。
夕方6時以降になると今度は火葬場が稼働していません。
ですから翌々日の火葬から可能となります。
この場合は3日間で行われます。
いつまでに葬儀を済ませてくださいという決まりはありません。
決まっているのは、24時間経過しないと火葬をしてはいけませんということです。
ですから遠方の親族がいる場合など、親族が集まるのに時間が必要な場合は、日程を考慮する方もいらっしゃいます。
せっかく家族葬で親族だけで見送るのだから、慌てずドタバタとあまりしたくない。
ゆっくり送りたいという方には、1日目はゆっくり準備期間にして、2日目に通夜、3日目に葬儀と3日間で行うことをおすすめします。
家族葬を行う際は、職場や学校へ断りを入れて休む方も多いと思います。
葬儀が終わり次第、なるべく早く復帰しないといけない事情のある方の場合、通夜・葬儀の日程を極力早める方もいらっしゃいます。
その場合は最短の1日目に通夜、2日目に葬儀というスケジュールが良いでしょう。
3日目で行う場合、1日目を広島では仮通夜と言います。
冒頭で申し上げたように広島の方は、浄土真宗の方が多い地域です。
そのため、1日目はお寺様に枕経をあげていただいて終了とする方も多いです。
あえてその枕経を通夜の時刻同様の時間帯に行い、仮通夜とする場合もあります。
1日目はせっかく日程的に1日時間の余裕が生まれるわけですから、有効に時間を使いたいものです。
例えば準備に時間が欲しい方は、準備時間にあてましょう。家族葬であれば弔問への応対などに追われる心配もないため、ゆっくり故人様のそばで過ごす時間を大切にするのも良いでしょう。
また、お棺に入れて差し上げたいものの準備や、昔のアルバムを見ながら思い出を語り合うのも良いでしょう。
広島県の家族葬はどのような流れで進むのか、一つずつご説明させていただきます
お亡くなりになられて臨終を迎えると医師からの死亡判定を受け、お体は清拭という処置をしていただきます。
施設で用意される浴衣にお着替えの場合もありますし、事前にこれを着せてあげて欲しいという服があれば、前もって職員へ預けておくのも良いでしょう。
葬儀社へ連絡し、お迎えに来ていただきます。
ご自宅、もしくは葬儀会館など故人を安置する場所を決める必要があります。
葬儀社がその場所までご安置のお手伝いをいたします。
ご安置が終わると葬儀社が宗派に合わせた枕飾りを行います。
ご自宅で、仏壇が無いという方でも、ご安心いただいて大丈夫です。
最初にお勤めいただく読経として枕経があります。
枕元で行う読経なので枕経と言われます、お亡くなりになられてすぐに行う場合が昔は多かったのですが、家族葬が増えている現在は、少し様子が変わってきています。
1すぐに枕経をしていただく
2仮通夜として夕方行っていただく
3お寺様の都合に合わせて行っていただく
4通夜式の時に枕経を一緒に行う
家族の希望をお寺様に伝え、お寺様の都合も伺いながら調整します。
そのため、ご安置後に葬儀社と一緒にお寺様へ連絡する形が良いでしょう。
準備の多くは葬儀社が行います。
家族葬でご家族が行う準備はそれほど多くありません。
尚、葬儀会館でもご自宅で家族葬でも準備物は変わりません。
1親族への日時の連絡
2会社、学校を休む場合、関係各所への連絡
3司式者(寺院など)への連絡
4お布施、火葬料などの現金の用意
5写真の用意(遺影写真を作るため)
6印鑑の用意(認め印、死亡届を役所へ提出で必要)
7葬儀場に飾ってあげたいもの用意(思い出の写真、愛用品など)
※葬儀会館で家族葬の場合、この他に通夜の晩、宿泊するための準備物(着替え、礼服など)が必要になります。
家族葬の通夜は、参列者への接待などがなく、集まるのは親族のみです。
そのため、通夜は読経が中心になります。
進行はお寺様、葬儀社によって行われるため、ご家族がやらなければならないことは、式の最中に焼香を行う程度です。
通夜式終了後に親族代表挨拶を行う方もいらっしゃいますし、そんなに仰々しくする間柄でもないからと、挨拶を省略する方もいらっしゃいます。
集まる方々との関係性で決められたら良いでしょう。
挨拶を行う場合は、葬儀社が例文を用意していることも多いので参考にしてください。
広島の家族葬では葬儀の日も式自体は、通常の葬儀と変わらず進行をします。
式の最後にお別れの献花がありますが、一般参列者がいない親族のみで行われる時間になるため、とても温かい時間になります。
お別れに時間が十分取れることも特徴です。
通夜式同様に挨拶を行う場合、省略する場合があります。ご家族の判断で決められると良いでしょう。
火葬場へ向かう際、喪主は霊柩車へ乗車します。家族葬の場合、その他の親族は主に自家用車で対応することが広島県では多いです。
自家用車の場合、火葬場から直接、帰宅できることも、時間的都合のある方にとってメリットです。
道中迷わないように、予め場所の確認を忘れずに行いましょう。
自家用車で対応が難しい場合、必要あれば葬儀社がマイクロバス、ハイヤー、ジャンボタクシーなどを手配してくれますので、ご相談ください。
火葬場で1時間半ほど待ち時間を経て、収骨を行います。
待ち時間を利用してお弁当を用意するご家族もいらっしゃいます。
親族に通夜・葬儀・そして火葬場と同行していただいたお礼も兼ねて食事を振る舞われる場合、時間的に中途半端になるため、全て終わってから食事にする場合もあります。
広島で行われる家族葬の場合、精進料理、精進落としという風習的な意味合いは薄れ、普通に昼食として位置付けられている印象です。
収骨の際に納骨の時に必要な埋葬許可証をいただきますので、大事に保管しましょう。
広島の家族葬では、葬儀当日に初七日法要を行うケースが多いです。
いくつかパターンがありますので紹介させていただきます。
1収骨後、葬儀会館・自宅へ戻って初七日法要を行う場合
2収骨後、お寺へ移動して初七日法要を行う場合
3葬儀告別式の最中に初七日法要も一緒に済ませてから出棺する場合
4文字通りご逝去から7日目に初七日法要を行う場合
ご家族の希望をお寺様にお伝えしてみるのは構いませんが、あくまでお寺様のお考えによって決まりますので注意が必要です。
本来はご逝去から7日目に行われる法要が、簡略化され当日に行われるようになりました。
どこまで簡素化を許すのか、お寺様も難しいご判断に迫られていることにご理解をお願いいたします。
初七日も無事終破ると、四十九日法要後に納骨をお考えになる方が多いです。
納骨までの期間、自宅でご遺骨を安置するための簡易祭壇を葬儀社が設営してくれます。
これを後飾りと言います。
広島ではお鉢さん(仏飯)を供える風習がありますが、その他にも故人が好きだった食べ物、愛用品などを飾ってあげると故人様も喜ばれると思います。
四十九日まで毎朝、「今日も行ってきます」など声をかけ、お念仏されると良いでしょう。
広島の家族葬を移動で見てみたいと思います
病院→葬儀会館(打ち合わせ)→自宅(準備)→葬儀会館(通夜・葬儀)→火葬場(収骨)→葬儀会館(初七日)→自宅(後飾り)
病院→自宅(打ち合わせ・準備・通夜・葬儀)→火葬場(収骨)→自宅(初七日・後飾り)
自宅で行うと移動が少ないため、負担が少なく、お別れの時間もしっかり持てます。
大変そうに見える自宅での葬儀ですが、実は最後の時間を愛着ある我が家で家族だけでゆっくり過ごすことが可能です。
興味のある方は弊社のホームページをご覧ください。
・主に2日間〜3日間で行われる
・通常の葬儀と流れ自体は変わらない
・家族葬の場合、式の中で親族代表挨拶を省略する場合もある
・広島の家族葬の流れは、「臨終」→「安置」→「枕経」→「通夜」→「葬儀」→「出棺」→「収骨」→「初七日」→「後飾り」となる場合が多い
・枕経は通夜の時に行われることもある
・初七日は葬儀の時に行われることもある
広島では、茶の子と言えば香典返しをイメージします。
しかし全国的には「茶の子供」という起源から、お茶に添えるお菓子という意味になるのが一般的です。
この記事では広島の方へ茶の子(香典返し)を行う際に、熨斗はなんでも茶の子ではいけないということを知っていただくため、宗教ごとの違いを記載させていただきましたので、ご覧ください。
葬儀の際にいただいた香典に対するお礼は、四十九日を目安に行うことが一般的で、品物に挨拶状を添えて送ります。これを香典返しと言います。
その香典返しのお礼を広島県の方々は、当たり前のように「茶の子」と言います。
「茶の子でタオルは好きじゃないけえ、他にええのないん?」
この言葉は広島県民にしか、残念ながら通じません。
私も現場で「茶の子はいつごろ返したらいいんかいね?」とおっしゃる喪主様を不思議そうに見る名古屋のご親族様が印象的でした。
当たり前に言われる「茶の子」ですが、実は注意しないといけない点があります。
それは「茶の子」は仏式で行われたお葬式で香典返しをする場合の呼び名です。
四十九日は仏事です。香典の儀も同じで、神式では香典ではなく玉串料と呼び名が変わります。
茶の子は仏事でのお返しで用いるので、お礼を送る際の熨斗には気をつけましょう。
では神式で葬儀を行った広島の方が香典返しをする場合、どのような熨斗にすれば良いのか。それは「偲び草」となります。
神式のお葬式は全体の3%と言われています。
ですから広島の97%は「茶の子」を使用する可能性が高く、「偲び草」は使用機会が少なくなります。
そのため、うっかり茶の子を使用してしまうミスが葬儀でも香典返しでも起こりやすいのが広島の特徴です。
正しく偲び草が用いられているか確認をしましょう。
キリスト式の場合も「偲び草」が用いられることが多いです。
本来、キリスト教に香典返しの慣習はありませんが、日本では仏式の影響で贈り物をされる方が多いです。
ですから正しい熨斗というのはありません、よく用いられるのは「偲び草」「志」です。
偲び草も志も「お礼」という意味があります。
お亡くなりになられてから四十九日までの期間は忌中、またの名を中陰と言います。
四十九日を迎えることを「忌明け」、そして中陰が満つることから「満中陰」とも言われます。
全国的に、香典返しのお礼で「満中陰志」の熨斗を使うことが多いのもそのためです。
無事に四十九日を迎えることができましたという意味があるのです。
他にも「粗供養」「志」が使われています。
どの熨斗にするべきか迷った時は、マナーをご心配な方には「志」が万能です。
仏式でも神式、キリスト式でも無宗教でも使えます。そして日本全国地域を問いません。
どの熨斗にするか迷った時、お返しする相手様が広島県民の場合は「茶の子」をおすすめします。茶の子は仏式で行う香典返のお礼と申し上げましたが、それ以上に香典返し=茶の子のイメージがとても強く根付いています。
お相手に香典返しだと認識していただけやすいのは、広島では茶の子に勝るものはありません。
散骨を海で行いたいなら、さまざまな選択肢があります。
ほんの数十年前は「違法ではないか」と思われていた散骨ですが、「亡くなったら大海に眠りたい、そして自然に還りたい」と希望する人が増え、散骨を行う業者がたくさんできてきました。
散骨を海でやりたい人に向けて、手順や費用相場、メリットとデメリットをお伝えします。
散骨を海で行うことは、「海洋散骨」と呼ばれています。
業界団体等によると、海洋散骨の認知度は8割を超え、年間推計で国内2万5000件が行われているとされています。
実は、散骨は数十年前まで違法と思われてきました。
昭和の大スターであった石原裕次郎が1987年に亡くなったとき、兄の石原慎太郎氏は「弟がこよなく愛していた海に還してあげたい」と海洋散骨を希望しましたが、「散骨は難しい」とされ、叶わなかったほどです。
しかし、1991年に市民団体が公開散骨を行った際、法務省は「葬送のための祭祀として、節度をもって」行われる限り、遺骨遺棄罪には当たらないと見解を示しました。
これにより散骨は、徐々に弔いの方法として認められるようになりました。
現在、散骨業者は東京だけでも30社ほどがあり、全国展開している会社も見られるようになりました。散骨業者を紹介する会社などを含めると、窓口はたくさん見つかります。
この状況をかんがみ、2021年には厚生労働省が事業者向けに「散骨に関するガイドライン」を出しました。
ガイドラインを守る業者に依頼できれば、安心・安全な海洋散骨が可能になります。
散骨を海で行うときの手順は、以下の通りです。散骨を行う人には制限がないため、遺族などが自分たちの手で行うことも可能です。
ただ、「手順通りにできるか不安」「自分たちで船をチャーターできない」と感じる人は、散骨業者に依頼しましょう。

まずはどこの海に散骨するかを決めます。散骨場所を決めるポイントは、以下の3つです。
・本人が希望している海があれば、優先する
思い出の場所に還りたいと考えているなら、何より優先しましょう。
しかし、次の2つの点から考えると、叶わない場合もあります。
・人に迷惑をかけない場所にする
海水浴場や養殖場、漁業を行っている湾内など、人に迷惑がかかってしまう場所は避けましょう。
フェリーや遊覧船からの散骨も、行ってはいけません。
このガイドラインを守るため、散骨業者は岸から離れたところまで船を出します。
・条例違反にならないようにする
散骨禁止条例を敷いている市区町村があります。
その自治体内で散骨してしまうと、条例違反になります。
一目で遺骨と分かるような姿のままで散骨を行うと、後で遺骨を発見した人から「遺骨の遺棄では?」「何かの犯罪かもしれない」と疑われてしまうかもしれません。
供養として散骨していることを示すため、遺骨を粉状に砕きます。
この粉骨を自力で行うのは大変です。
乳鉢などを使い、供養の一環として行う人もいますが、依頼する散骨業者に相談すれば、別料金でパウダー状に粉骨してくれます。
散骨の日程を決め、参加者に知らせます。
散骨の人数に決まりはありませんが、乗船できる人数は限られるため、散骨業者や船をチャーターする会社に問い合わせましょう。
参加者には、天候によっては海に出られず延期となることも、忘れずに伝えます。
散骨のとき、僧侶からの読経が欲しい人は、つきあいのあるお寺や、依頼する散骨業者に相談しましょう。
散骨の前日までに、散骨の準備を済ませておきます。
・服装
散骨時には、礼服ではなく、平服が好ましいとされています。
喪服では、船に乗るとき目立ってしまうためです。
また船上は足下が悪いので、スニーカーなど動きやすい靴を履きましょう。
・副葬品
遺骨を撒いた後、お花やお酒を撒いて供養とする人がいます。
お花は茎を取り除き花弁だけにする、ビニールや瓶は海に捨てないなど、環境負荷を考えて副葬品を用意しましょう。
・お布施
散骨に僧侶を呼んだ場合には、お布施を包みます。
散骨当日は、海岸から離れた場所まで船を出し、遺骨を撒きます。その後、副葬品を海へ入れ、黙祷を捧げましょう。
散骨を海で行う場合、次の4つの方法があり、それぞれ費用相場が変わってきます。(お布施は別途必要となります。)
一家族だけで海へ向かい、散骨することを個人散骨といいます。
個人散骨の費用相場は、25万円から30万円です。
複数の家族と予定を合わせ、船に同乗して散骨することを合同散骨といいます。
船のチャーター代を折半できるため、個人散骨より割安です。費用相場は10万円~20万円ほどです。
業者に遺骨を預け、業者の都合が良い日に散骨してもらうことを、委託散骨といいます。
委託散骨では、家族は同行しません。費用相場は、骨壺1つあたり5万円ほどです。
先に紹介した手順にのっとり、自力で散骨を行う人もいます。
船のチャーター料金が主な出費になります。船舶を所有している人なら、費用負担は生じません。
散骨を海で行うメリットは、以下の6つです。
海に強い憧れがある人にとって、海への散骨は魅力的なものでしょう。亡くなったら自然に還りたいと考えている人にも適しています。
承継者が必要となる一般的なお墓は、100万円から200万円といった単位のお金がかかります。
墓石ではなく樹木を墓標とする樹木葬は、一般的なお墓よりは安価ですが、散骨のほうが安く済みます。
お墓を維持していくために、お墓掃除や供養を行う人を立てる必要はありません。
身寄りのない人や、子世代にお墓で負担を掛けたくない人にぴったりです。
今あるお墓を撤去して、お寺など墓地の管理者へ返還することを「墓じまい」といいます。
お墓の継承者が不足している現代において、墓じまいをする人は増えてきています。
墓じまいの後、先祖の遺骨を供養する方法として、散骨は有効です。
散骨は、どんな宗教の人でも行うことができます。
「お寺の檀家を抜けた。以後はどこかのお寺の檀家になりたくない」「無宗教葬をしたい」といった人に適しています。
陸で散骨を希望する場合、他人の土地へ勝手に遺骨を撒くことはできませんから、選択肢は限られます。
海洋散骨にも場所の縛りはもちろんありますが、陸での散骨ほどではありません。
散骨を海で行うデメリットは、以下の6つです。
先ほど紹介した手順や、厚労省のガイドラインに沿った散骨をしないと、周辺の人々とトラブルになる恐れがあります。
散骨に対する感情は人ぞれぞれで、散骨を忌避する人もいますから、慎重に行わなければなりません。
また、業者を探す際には、ガイドラインを守れているか、実績は十分かなど、信頼性に注目しましょう。
散骨することを嫌う親族も、いないとは限りません。
とくに故人の兄弟や子どもなど、近親者からNGが出た場合には、例え故人の希望であっても、実施は難しいかもしれません。
反対者がいるなら「全ての遺骨ではなく、遺灰を少しだけ散骨して、あとはお墓に納骨する」など、分骨も提案してみましょう。
散骨は本人ではできないので、どうしても子世代などに託すことになります。
一時的に負担をかけてしまうことに、ためらう人もいるでしょう。
生前から業者を決めておく、お金を準備しておくなどしたうえで遺言し、残される人の負担を減らすことが重要です。
全ての遺骨を散骨してしまうと、後でどんなに遺骨を取り戻したいと思っても叶いません。
後悔しないためにも、少しだけ遺骨を残しておいて、小さな骨壺で供養したり、遺灰を込められるブレスレットを活用したりするのがおすすめです。
命日やお盆、お彼岸など、今までならお墓参りをしていた時期に「お参りしたいけれど、どこに手を合わせたら良いか分からない」と感じることがあります。
命日に船で散骨地点まで行ったり、「海はどこまでもつながっている」と近くの海へ行って手を合わせたりするご遺族もいらっしゃいます。
船に慣れていない人は、船酔いが心配です。酔い止めを使う、風が強く船が揺れそうなときは無理せず延期するなどの工夫で、船酔いを最小限にとどめましょう。
以上、海での散骨について解説しました。海洋散骨にはいくつかのマナーがあります。
とくに自力で散骨したいという人は、ガイドラインを熟読するなどしてトラブルのないようにしましょう。
普段あまり聞くことのない枕経という言葉、聞いたことはあるけれども詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では広島にお住まいの方へ広島の枕経について解説させていただきます。
枕経は、ご逝去後お亡くなりになられた方へ対して行う最初の読経を枕経と言います。
故人の枕元で行い、宗派によって呼び名も異なります。
起源は中世の時代、死の際にあるご本人と共に念仏した臨終行儀にあると言われています。
枕経の意味は、宗派によっても異なりますが、広島で多い浄土真宗の場合は、故人はたとえ亡くなっていても死後24時間以内は、まだ耳が聞こえているという考えが前提にあります。
耳が聞こえている内に、最後に故人へ御仏の読経を聴いていただこうという意味があります。
最後は家族の会話やテレビから聞こえる音ではなく、有難い仏の声を聴いていただこうということです。
その他の宗派では、成仏を勧め、悪魔を祓う意味などもありますが、基本的に亡くなった方の枕元、御本尊へ向かって読経するものです。
枕経を行うタイミングは、お亡くなりになられた場所から葬儀会館あるいは自宅へご安置してからとなります。
安置後に寺院へ連絡して枕経がいつ行われるか決まります。
主に3つのタイミングで行われます。
一つ目は、ご安置後にすぐにお寺様に来ていただいて枕経を行うケースです。
昔は、広島県のどこでも亡くなるとすぐに枕経が行われるのが通例でした。
耳が聞こえているうちに行わないといけないという意識から、すぐに行わないという解釈に変わっていたのだろうと思われます。
この名残は地域によっては、今も残っております。
例えば、ご安置した時間が夜中3時だった場合、このような時間帯に枕経はさすがに厳しいので、朝が来てからお寺様へ連絡して、ご都合が良い時に枕鏡を行っていただきます。
稀に24時間何時に連絡しても構わないという寺院様もいらっしゃいますが、その殆どの場合、前もってそういう事態になるかもしれない事を事前にご家族から伺っています。
ただ、すぐに行わないというものではなく、24時間以内であれば良いのですから、急ぐ必要はありません。
ご家族様、寺院様もお互いにとって無理のない時間帯で行うとよいでしょう。
最近多くなっているのが、通夜式の時に枕経を一緒に行っていただくケースです。
これは家族、寺院、双方にメリットがあるから多くなっています。
家族としては、枕経の準備が必要なくなること。通夜に合わせて準備を行えば良いので、時間的負担が軽減されます。
寺院側としては、お勤めに参加する回数が減る、手間が軽減されるという事です。
一度のお葬式で3度も4度もお越しいただくのは申し訳ないという気持ちから、遠慮して「通夜式の時に枕経も一緒に行ってください」と寺院に伝えるご家族様もいらっしゃいます。
お寺様が枕経でお越しになると決まれば、準備はどうしようかとなります。
しかしご家族が行う準備はそれほど多くありませんので、ご安心ください。
枕元で枕飾りを行いますが、こちらは葬儀社が宗派に合わせた形で行ってくれます。
お寺様を自宅に招いて枕経となる場合、読経後にお茶をお出しできる準備をしておくと良いでしょう。
枕経の時間が決まれば、親族全員に来ていただく必要はありません。
その時に集まれる家族で行うことが多いです。
枕経は、枕元の故人へ行う読経という解釈で良いと思いますので、皆が無理して時間を割いて集まる必要はありません。
通夜から参列いただくようにしましょう。
広島では仏飯(ぶっぱん)のことを「お鉢さん(おはちさん)」と言います。
私もこの業界へ入りたての頃は、「おはちさんがない!」と叫ぶご家族様に対して、わけがわからずあたふたした事もありましたが、広島ではどこへ行っても皆さん「おはちさん」とおっしゃるので驚きです。
他の宗派では茶碗にご飯を盛って端を立てる。一膳飯という風習もありますが、広島では馴染みがありません。
浄土真宗に限らず仏壇にある仏飯器にお鉢さんを盛るのが通例です。
葬儀会館で枕経を行う場合は、葬儀社がお鉢さんを用意してくれます。
お鉢さんはご安置後にご用意が望ましく、枕経までに間に合うと良いでしょう。
枕経の服装は、喪服でなくて結構です。その時の服装のまま参加いただいて結構です。
しかしあまり華美な服装は避けたほうが無難だと思われます。
数珠があればご用意ください。
広島県では、枕経のお布施相場は、宗派に関わらず1万円〜2万円です。
多くの方は、1万円を包んでいらっしゃいます。
急に行われる場合、お布施を包む袋、あるいは現金の準備が整っていない事もあります。
お布施を包む袋は、葬儀社が事前に用意している場合が殆どです。
現金のご用意が難しい場合は、枕経の時にお布施をお渡しするのではなく、通夜式の際に通夜のお布施と一緒にお渡しする形を取ります。
枕経が葬儀会館あるいは自宅で行われる場合、お寺様に時間を割いて足を運んでいただくお礼にお車代をお渡しします。
相場は距離によりますが、5千円〜1万円が相場となります。
枕経は近年、省略して通夜の時に一緒に行われる事も多くなりました。
しかし亡くなるとすぐに行うのは当たり前という地域も残っています。
菩提寺が無い方は、枕経を行うタイミングに関しては、通夜の時に一緒に行う形が多くなると思われます。
しかしそれでもすぐ行って欲しい場合は、葬儀社へ相談してみましょう。
菩提寺がある方は、お亡くなりになったことを連絡する際、「枕経はいつ行えば良いでしょうか?」と相談するのも結構ですし、ご心配であれば、事前にいつ行うことになるかを相談しておくのも良いと思います。
広島県福山市金江町にある福山市西部斎場についてご紹介させていただきます。

・住所 広島県福山市金江町藁江字茶臼山7604−2
・TEL (084)930―1450
・駐車場 60台
・斎場受入時間 9:30〜16:00
・休館日 1月1日、1月2日

●交通のご案内

・タクシーの場合
JR山陽本線 備後赤坂駅より6分
山陽新幹線 福山駅より21分
・お車の場合
福山西ICより20分
福山市役所より18分

・火葬炉 6基
・お別れ室 2室
・収骨室 2室
・待合ロビー
・待合室(和室) 2室
・おむつ交換台、ベビーベッド

| 福山市内在住の方 | 12歳以上 | 8,000円 |
| 福山市外在中の方 | 12歳以上 | 24,000円 |
| 福山市内在住の方 | 12歳未満 | 5,000円 |
| 福山市外在中の方 | 12歳未満 | 15,000円 |
利用における注意事項と棺の中に入れてはいけないものは下記の通りです。
・出棺時間を厳守、時間に合わせて到着をしましょう。
・待合室での食事は、原則禁止とされていますのでご注意ください。(飲料や軽食類は認められています。)
お弁当を用意される喪家様は、持ち帰り用のお弁当としてご用意されています。
・斎場職員より火葬執行印を押印した「死体(死胎)火葬(埋葬)許可証」を、お渡しします。墓地などの納骨の際に必要になります。大事に保管しましょう。
故人様を偲び愛用品などを、棺に収めたいというお気持ちは理解できますが、火葬中のご遺骨の損傷、有害物質の発生、火葬時間の延長に繋がりますので、下記のような副葬品は、お棺の中に入れることは禁止されています。
・化学繊維製品・プラスチック類(グローブ・玩具・釣竿・ぬいぐるみ)
・ガラス類、金属製品(酒瓶・ビール瓶・腕時計・指輪・メガネ)
・燃えにくいもの(厚い着物・衣類・寝具・ドライアイス・果物)
・危険物(ガスライター・電池など爆発性のあるもの)
※ペースメーカーには、リチウム電池が入っていますので、事故が起こると大変危険です。
前もって取り出せない場合は、その旨を斎場職員にお知らせください。

福山市西部斎場内に、葬祭会館が併設されています。
通夜・葬儀が可能となっており、火葬場までの移動がないため便利です。
公営施設のため、福山市の方は低価格でご利用いただけます。
利用限度は24時間となっています。
例えば18時から通夜式、葬儀が翌日10時の場合は、通夜の始まる3時間前の午後3時から利用、最長翌日の午後3時までとなります。
したがって通夜当日に、通夜開式2〜3時間前から利用する形になるのが一般的な利用方法です。
式場(最大120席)控室(30畳)
| 基本使用料 | 超過使用料(1時間) | 使用限度額(24時間) | |
| 福山市在住の方 | 49,230円 | 9,840円 | 98,460円 |
| その他の方 | 98,460円 | 19,680円 | 196,920円 |

・食事、仮眠が可能です。
・入浴施設はありません。
・ガスコンロ、冷蔵庫、湯呑み、グラスがあります。
・茶葉、ゴミ袋は各自で用意が必要です。

福山市西部斎場 葬儀受付相談
TEL 0120-564-594(24時間365日対応)
福山市西部斎場で葬儀のご相談を24時間365日承っています。
福山市民の方は低価格でご利用いただけますので、特に松永方面の方にとってはご葬儀の式場として利用するのにおすすめです。
福山市西部斎場の葬儀場で家族葬を行なった場合の料金は下記の通りです。
■福山市西部斎場で通夜・葬儀を行った場合の料金例
| 葬儀場で家族葬二日プラン | 280,500円 |
| 葬儀場の使用料 | 98,460円 |
| 福山市火葬料 | 8,000円 |
| 合計 | 386,960円 |
■福山市西部斎場で葬儀告別式のみ行った場合の料金例
| 葬儀場で家族葬一日プラン | 236,500円 |
| 葬儀場の使用料 | 49,230円 |
| 福山市火葬料 | 8,000円 |
| 合計 | 293,730円 |
・葬儀に必要なものは基本的に全て含まれています。
・供花物、弁当、会葬品などはオプションで承ります。
・お寺様へのお布施は含まれていません。
※控室で宿泊可能ですが、寝具は別途手配が必要になります。(2組までサービス。3組目から1組5,500円)
プランの詳細については、下記からご確認いただけます。
福山市西部斎場では、火葬予約がいっぱいで希望日に火葬ができないということは、殆どありません。
火葬予約が混雑していて希望通りの時間に予約が取れず、時間の調整を余儀なくされることはありますが、日取りまで変更いただかなくても、時間調整さえできれば解決することが殆どです。
火葬の予約待ちという現象が起きやすいのは、年始の時期になります。
この時期以外であれば、何日も待つことはないと思います。
福山市西部斎場では、火葬の直前に、炉前ホールで故人様と最後のお別れができるお時間がございます。
短い時間ではありますが、対面してお別れができます。
福山市西部斎場では、火葬の待ち時間に休憩ができる待合ロビーがございます。
そちらでゆっくりご休憩いただけますが、現在はお弁当を用意して食事を行うことはできません。
どうしても何かしらのおもてなしをしたい場合は、茶菓子であれば認められていますので、お茶菓子で対応いたしましょう。
福山市西部斎場は葬儀場としてご利用いただけます。
小規模な家族葬から大規模な一般葬まで対応できる式場があり、通夜葬儀の2日間利用、葬儀のみ1日だけの利用も可能です。お食事もできます。
福山市西部斎場は、駐車場から炉前ホール〜待合室〜収骨室まで、一切の段差もなく、階段やエレベータもない、バリアフリー対応の建物です。
車椅子の無料貸し出し、身障者用のお手洗いも完備しています。
足が不自由な方でも不安なくご参加いただける施設になっています。
「生前に母に葬儀はしなくていい、墓もいらないと言われた。言われた通り読経無しにして、無宗教でやろうと思うのですが、どうしたらいいですか?」
先日、こんな質問をいただきました。
後に残る家族を思い発した言葉なのだろうと推測出来ますが、本心はどうだったのか、聞くことは叶いません。
ご自身の言葉を尊重するのが一番だとは思いますが、注意も必要です。
この記事では、後々困らないように無宗教の葬儀をお考えの方にアドバイスをさせていただきます。
無宗教の葬儀というのは、文字通り宗教色のない葬儀スタイルです。
自由とも言えますが、その反面流れに身を任せて行える葬儀ではなく、自分達で考えることが必要とされます。
無宗教で故人を送るということは、葬儀だけではなく、その後の供養にも影響を及します。
仏式であれば、葬儀に読経があり、初七日、四十九日と法要がありますが、無宗教の場合は決まったものがありません。
葬儀社への支払いは安く済みますし、お坊さんへのお布施も省けるので圧倒的に安価で葬儀を行うことができますが、「四十九日はどうしたらいいの?」「戒名はなくていいの?」と次々に心配事が浮かぶ場合があります。
今までたくさんの無宗教の葬儀をお手伝いさせていただきましたが、心配事のご相談は葬儀よりも葬儀後に多かった印象です。
無宗教で行うということは、決まりがないことを意味します。
「お供え物は何がいい?」「焼香の回数は何回が普通?」「納骨はいつ行ったらいい?」
誰に聞いても教えてくれません。
「あなた自身が納得する方法で行ってください」が正解となります。
故人に尋ねても残念ながらお返事は返ってきません。自分で納得する形は何か、見つけて決めていかなければならないのです。
私は決して、無宗教の葬儀を否定しているわけではありません。
しっかりお考えにならずに執り行うのは危険だとお伝えしたいのです。
無宗教で葬儀を行うには、下記の2つの覚悟が必要だとアドバイスさせていただきます。
葬儀はしなくていいと言われたから無宗教で葬儀を行うのではなく、葬儀後の供養も考えてから決断しましょう。
法要はするのかしないのか、納骨方法はどうするのか、などです。
できればご本人と生前にそこまでお話し出来ていることが一番です。
無宗教で葬儀を行った方が、葬儀後にお寺様に簡単に読経をあげていただき、戒名だけいただくケースもありました。
無宗教だから戒名をもらってはいけないということはありません。
もらわなくても良いということです。
全てが自由なので、ご自身が納得する形を模索して決断する覚悟をお持ちください。
ご本人、ご家族が無宗教で葬儀を行うことで一致したとします。
それでも周囲の親族が「非常識なことを」「なぜそんな粗末に扱ったの?」「本人はあなたに気を遣って言っていただけ、鵜呑みにするもんじゃない」「かわいそうに」などとおっしゃる場合も想定されます。
このような声にも負けずに毅然とした態度をとる覚悟が必要です。
覚悟を持つには、ご本人の言葉は何よりも大切な拠り所となるでしょう。
ですからできればご本人とあなただけでなく、ご本人が心許せる方にも思いを知っていただきましょう。
ご本人の口から話してもらえば、その方々も良き理解者となって、葬儀の際にはあなたを守ってくれる存在になるはずです。
最後に私が過去にお手伝いさせていただいた無宗教の葬儀をご紹介させていただきます。
ご参考にしていただきご自身の一番良い形を模索してみてください。
無宗教の葬儀は、自由ですから、ご家族で全て決めることができます。
奥様が亡くなり、70代のご主人が喪主だったある日のお葬儀です。
通常通り通夜、葬儀の日時を決めて、親族、ご近所の方へ通知を行いました。
香典は辞退され、無宗教で行うこともお伝えしました。
通夜は18時から行われ、参列者は20名でした。
会場は、宴会場のように座卓テーブルを四角で囲い、それぞれのテーブルに各自着席しました。
最初に喪主が参列者へお越しいただいたお礼、亡くなるまでの経緯を話し、その後参列者皆様から一言ずつお言葉を頂戴しました。
通常の葬儀であれば、喪主が参列者へ挨拶、弔辞を行う方が故人へ挨拶の程度です。
しかしこの通夜では、参列者全員が皆の前で故人を含めて全員へ向けて一言、これまでの思い出などを語ったのです。
20名いれば、20のエピソードが聞けました。みんなで故人を偲ぶ、とても温かい空間になりました。
葬儀では、みんなで生前のビデオを見て、故人が好きだった歌を歌って、最後に献花をしてお別れとなりました。
故人が60代の女性、喪主はご主人、お子様が3人、5人家族のお母様の葬儀でした。
故人は宗教色を嫌い、読経はいらないから薔薇の花で飾って欲しいという要望がありました。
通夜の食事は、お母様特製のカレーのレシピを長女様が真似して作り、ご親族へ振る舞いました。
葬儀では、亡くなられたお母様に対して、次女様がバイオリンを生演奏、長男様はお母様との思い出、お母様の自慢できるところ、溢れる思いを参列者へたくさんお話されました。
最後はリクエストのあった赤い薔薇の花びらを、棺の中いっぱいに敷き詰めて、ご家族で記念写真を撮ってからご出棺となりました。
いずれのケースも、事前にご家族がはっきりとした葬儀のイメージを持っていました。
当初は具体的なイメージは無かったのかもしれませんが、事前に尋ねて来てくださり、私がご相談を承った結果、イメージをどんどん膨らませていただけました。
特に決まりがない無宗教の葬儀では、葬儀社のアドバイスも必要になると思われますので、お考えの方には、お近くの葬儀社へご相談してみてはいかがでしょうか。
一社と言わず、ご希望を尊重して親身にアドバイスをしてくれる葬儀社が見つかるまで何社か当たって見ることをおすすめします。
一生に一度きりのものですから、あなた様が後悔のないお見送りができることを心より願っています。
新型コロナウイルスが流行し、これまでは屋外ではマスク着用は不要、屋内では原則着用とされていたマスクですが、政府の発表により令和5年3月13日以降、マスク着用は個人の判断が基本となりました。
詳細は厚生労働省発表の「マスク着用について」をご参照ください。
屋内でのマスク着用が個人の判断となったことで、今この時期にお葬式へ参列する機会があれば、マスクを着用するべきなのか、しなくても良いものなのか、お悩みになる方も多いのではないでしょうか。
また、葬儀と言えば黒を連想しがちなため、黒いマスクをして参列すると良いのだろうか?それとも白がいいのだろうか?
疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
この記事では、葬儀参列の際のマスクについて、実際に葬儀に携わっている私が解説させていただきます。
新型コロナウイルスの位置付けが5類になったことで、日常生活を取り戻した現在、マスクを外して外を歩く方も増えています。
現在のマスク着用率はコロナ禍に比べて1/3に激減しているそうです。
そんな時だからこそ、葬儀に参列する際は「まだマスク着用がマナーなのかな?」
疑問に思う方も多いと思われます。
結論から言えば、お葬式の場面では、場面によっては今も殆どの方がマスクを着用されています。
例えば控室で家族だけで過ごす場面はマスクを外されている方が多いです。
一方で儀式の最中や他の家の方とも会う確率の高い火葬場ではマスク着用率が高い傾向です。
気心知れている気を遣わない間柄ではマスクを外し、周囲へ気を遣う場面ではマスクを着用するという使い分けをされている方が多い印象です。
また、高齢者の方の中には日常的に感染予防としてマスク着用を続けている方もいらっしゃいます。
葬儀の場は不特定多数の方が集まる場でもありますから、感染予防としてのマスク着用は継続いただければと思います。
多くの斎場、葬儀社の職員は引き続きマスク着用をしているところが殆どです。
令和4年5月23日に政府が新たに示したマスク着用の考え方は、下記の通りです。
| 身体的距離が確保できる | 身体的距離が確保できない | |
| 会話を行う(屋内) | 着用を推奨する | 着用を推奨する |
| 会話を行う(屋外) | 着用の必要はない | 着用を推奨する |
| 会話を行わない(屋内) | 着用の必要はない | 着用を推奨する |
| 会話を行わない(屋外) | 着用の必要はない | 着用の必要はない |
葬儀の場面、斎場での場面は屋内になります。
葬儀では葬儀中に参列者同士の会話はありませんが、葬儀中は読経が行われます。
そして葬儀前後には参列者同士の会話などその場に集う方々の会話が屋内であります。
葬儀といえば、参列者がさまざまな地域からお越しになるのが特徴です。
そのため、感染すると広範囲に広がってしまうのが葬儀においてのリスクと言えます。
また、幅広い年代の参列がある場所で、高齢者の参列も日常的にある場所のため、マスクを着用した方が良い場所とも言えます。
このような理由から屋内での会話を伴う場所として、感染拡大防止の観点からマスク着用が推奨されています。
マスク着用がお葬式のマナーとされる理由は、周囲への配慮です。
一番飛沫の拡散を抑える効果が高い不織布マスクは、布製、ウレタン製に比べて、吐き出し飛沫量も吸い込み飛沫量も少ないので、こちらが最善です。
しかし現在では布製、ウレタン製を選ぶ人も増えています。
コロナ禍では殆どの方が葬儀においては不織布マスクを着用されていましたが、コロナが5類に移行して以来、布製、ウレタン製を着用する参列者も増加傾向です。
色は白が良いです。白の不織布マスクが最適です。
急なお葬式でも用意がしやすく、手に入れやすい。そして一番無難だと言えます。
黒でも構いませんが、黒は若い世代に人気でカジュアルな場面でもよく使われるため、葬儀の場では周囲にカジュアルな印象を与えてしまう可能性があります。
肌の色に合わせて目立たないようにベージュをお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
コロナ禍の葬儀では、マスクしていますよと一目でわかるほうが相手に安心感を与えるという理由で、ベージュよりも白がおすすめでしたが、現在はベージュでも構いません。
しかし、ベージュも黒同様にカジュアルな印象を与えてしまう可能性はあります。
結論としては、白が無難、色は白でも黒、ベージュでも構いません。
本来のマスク着用の意味を考えれば、マスクをするならば、色よりも、不織布のマスクでお願いしたいということです。
最近では、参列者は家族だけという家族葬であれば、マスクを着用しない葬儀も普通にあります。
それでも葬儀中はマスクをしなかったが、火葬場ではマスクを着用するご家族もいらっしゃいます。
家族だけの空間、不特定多数の方と過ごす空間でマスクの使い分けです。
冒頭でも申し上げましたが、マスクをする場面、しない場面の使い分けが出てきているのが今のお葬式です。
つまりすぐに取り出せるようにしておくことなどの工夫が必要です。
代えのマスクを数枚持っておくなどの準備がおすすめです。
豊橋技術科学大学の研究結果で、下記の結果が出ています。
| 吐き出し飛沫量 | 吸い込み飛沫量 | |
| 不織布製 | 20% | 30% |
| 布製 | 18〜34% | 55〜65% |
| ウレタン製 | 50% | 60〜70% |
このようなデータから、不織布マスクは、感染予防効果が高く、感染拡大を防ぐには欠かせません。
お葬式は、他県からも人が集まる場で、クラスターの発生する可能性も秘めています。
少しでもリスク軽減するために、不織布マスクがおすすめです。
ご相談は無料
24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも
フリーダイヤルへご連絡ください。
「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は
メールでのご相談も可能です。
ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
