ご依頼・ご相談の方はこちら
ご相談は無料
24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも
フリーダイヤルへご連絡ください。
「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は
メールでのご相談も可能です。
ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
葬儀を行う際、お寺へ包むお布施の相場は気になるものです。
この記事では日蓮宗の葬儀を行う方へ、日蓮宗のお布施金額相場について解説させていただきます。
ますは日蓮宗のお布施相場一覧を下記でご確認ください。
枕経から葬儀まで、20万円〜50万円が相場と言われています。
| 御布施 | 御車料 | 御膳料 | |
| 枕経 | 1万~2万 | 5千 | |
| 通夜 | 2万~3万 | 5千 | |
| 葬儀導師 | 15万〜30万 | 5千 | 5千 |
| 葬儀副導師 | 10万〜20万 | 5千 | 5千 |
| 初七日 | 2万〜3万 | 5千 | |
| 週参り | 3千〜7千 | ||
| 四十九日 | 2万〜5万 | 5千 | 5千 |
| 祥月命日 | 3千〜7千 | ||
| 百箇日 | 1万〜3万 | 5千 | |
| 盆・彼岸 | 1万〜3万 | ||
| 一周忌 | 2万〜5万 | 5千 | 5千 |
| 三回忌 | 2万〜5万 | 5千 | 5千 |
| 入仏式 | 1万〜3万 | 5千 | 5千 |
| 納骨 | 1万〜3万 | 5千 | |
| 墓石建立 | 1万〜5万 | 5千 |
日蓮宗の葬儀において、お布施相場は20万円〜50万円と言われていますが、
なぜこのように幅があるのか。
この疑問について解説をさせていただきます。
一番の要因は、葬儀によってお勤めするお寺の人数が異なります。
お寺が1名であれば1名分のお布施となり、2名であれば2名分のお布施が必要となります。
お一人違えば10万円単位で相場は変わりますので、この差は大きいと言えます。
例えば葬儀に際して、お寺が2名でお勤めだったとします。
ご住職と、ご住職の息子様がお勤めの場合もあれば、ご住職と別のお寺の住職の2名でお勤めの場合もあります。
住職と息子様の場合は、導師の相場+副導師の相場がお布施となります。
この場合、副導師のお布施は、導師の半分が目安です。
一方で住職と別の住職の場合は、導師の相場+副導師の相場と一見同じですが、実際に副導師へ包む金額は、導師の半分にはなかなかしづらい難しい面があります。
立場が違えども同じご住職という立場ですから、半分よりも多くなることが多いです。
このようにお勤めする方の格によっても相場は変動します。
地域によっても相場は異なります。
一般的に東京都市部及び関東方面の相場が高く、地方の相場が低い傾向があります。
少なからず地域性も要素の一つとしてありますが、地域性よりもお寺自体の個性による部分が大きな要素でしょう。
日蓮宗の場合、地域よりもお寺の個性や性格による部分が大きいです。
日蓮聖人が開祖の日蓮宗は、6人の弟子達が想いを継いで世に広めていきますが、その後もさまざまな派に分かれていきます。
同じ日蓮宗の中にもさまざまな考え方のお寺がありますので、相場も変わってまいります。
日蓮宗の葬儀は、お寺が2名以上でお勤めすることも珍しくありません。
その理由を解説させていただきます。
日蓮宗の葬儀では、鳴り物が登場します。
「ポクポク」と音がするのが杢魚(もくぎょ)ですが、日蓮宗では「カンカン」と少し高い音を奏でる木柾(もくしょう)というものを使用します。
「南無妙法蓮華経」を唱えながら木柾を叩きます。
そして妙鉢(みょうはち)という、シンバルのような音を奏でる鳴り物も登場します。
木柾を叩きながら、読経を唱える、そして時には妙鉢を鳴らす。
なかなか一人で行うのは本来難しいものなのです。
そのため葬儀の日は、2名以上のお勤めで行うことが本来の形なのです。
「葬儀を少人数の家族葬で行うのに、なんでお寺が2名も必要なんだ」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
たしかに2名でお勤めであれば、その分用意するお布施の額も上がります。
しかしお寺からすれば、お布施が欲しいから2名でお勤めをするのではありません。
しっかり葬儀でお勤めを果たし、責務を全うしたいと考えるからこそ、2名で行いたいとなる場合もあるのです。
とはいえ、近年葬儀の小規模化が進み、家族葬が主流なのは、お寺様も理解していらっしゃいます。
お一人で葬儀のお勤めを行ってくださるお寺も多くなってきました。
時代に合わせて、本来の形とは異なるやり方に変え、時には少し妥協をしてくださっている部分もあるでしょう。
お一人でお勤めが普通、二人でお勤めは多いというのは誤った認識で、お二人以上でお勤めが普通、お一人でお勤めの場合は、遺族のために譲歩してくださっているとの認識が良いと思います。
日蓮宗の葬儀では、お布施以外にも下記のものが必要になります。
日蓮宗では戒律がないため、戒名のことを法号(ほうごう)と言います。
一般的に戒名を授かる際に、戒名料が必要となりますが、日蓮宗の場合も法号を授かるのに必要となります。
文字数やランクによって異なってきます。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
葬儀のお勤めをするために足を運んでくださるので、交通費として御車料を用意します。
一般的に1回のお参りにつき5千円〜1万円が相場です。
往復分のガソリン代と想定して、5千円にするか1万円にするか、どちらかで検討しましょう。
タクシーでお越しになる場合は、往復分のタクシー代が目安となります。
また、お寺の送迎を遺族が自分たちで行うケース、葬儀をお寺で行う場合は、御車料をご用意する必要はありません。
葬儀の日や法要の場で読経後にお寺様と一緒に会食を行うのが当たり前だった時代もありましたが、現在は御膳料をお渡しして済ませることも多くなっています。
お寺とご一緒に会食を行う予定である場合、御膳料を用意する必要はありません。
その代わりにお寺様分の食事を忘れずに手配をしておきましょう。
終活をしたいと考えていても、いつ、何から手をつけたらいいか分からないという人は多いでしょう。
「終活のやることリスト」を作っておけば、取り組みやすくなります。
この記事では、終活でやるべきこととして優先順位の高いものから9つをリストアップし、解説しています。
ぜひ参考にしてください。
2022年、楽天インサイトが20代から60代を対象に行った調査によると、終活を「実施している」「近いうちに始める予定」「予定はないが、時期が来たら始めたい」と、実施する意向のある人は約7割となりました。
とくに60代女性は92.3%と、高い数値を示しています。
しかし、最も実施意欲の高かった60代女性でも、終活を「実施している」と答えたのはわずか12.5%。
終活したいとは思っているものの、まだ始めていないという人が多いという結果になりました。
なお、終活で今後する予定があること、興味があることとしてトップに輝いたのは「家の中の荷物整理」(60.9%)。
次いで「パソコンやスマートフォンなどのデータ整理」(39.8%)、「財産整理」(31.9%)となっており、「終活を始めるなら、まずは身の回りの整理から」と考えている人が多いようです。
しかし「家の中の荷物整理」は、とくに高齢の人にとってはかなりの体力仕事になります。
「やりたいけれど、どうにも腰が重くて」と感じるのも当然のことです。ここでつまずいてしまう人も、多いのではないでしょうか。
実際には、どんな順番で何をやっていけば終活がスムーズに行くのでしょうか。
以下、終活のやることリストとしてご案内していきます。
エンディングノートとは、自分で自分の身の回りのことができなくなったとき、他の人に希望を託すためのノートです。
亡くなってしまったときのほか、急に入院が必要になったときや、認知症になってしまったときなどにも役に立ちます。
エンディングノートには、入院時や葬儀時の連絡先リスト、葬儀・お墓の希望、保険や預金の預け先、家族へのメッセージといった項目があり、まさに「終活でやるべきこと」が網羅されています。
まずは終活で何をすべきかを網羅的に把握するためにも、エンディングノートを入手するのがおすすめです。
エンディングノートはたくさん出版されており、書店やネットで多くの種類を目にすることができるでしょう。
実際に手に取って、書きやすいと感じるものを購入するのが一番です。
また、葬儀社などが終活イベントで配布しているエンディングノートであれば、無料で手に入ります。
「まずは項目だけでも確認したい」「後で本格的に書くための下書きとして」と考え、まずは無料版を入手してみるのもいいでしょう。
親族や友人関係を把握するために、連絡先リストをつくりましょう。
「親族関係の電話番号は電話帳に記録している」「友人関係の電話番号はスマホの連絡帳に入っている」など、連絡先がバラバラの場所に保管されていませんか。
いざというとき、あなた以外の家族が連絡先リストにアクセスできるよう、一括したリストをつくっておきましょう。
この時点で、エンディングノートへ実際に連絡先を記載する必要はありません。
手書きでも、PCなどでデータ化しても構いません。
大事なのは、あなたが倒れたとき、あなた以外の家族がきちんとその連絡先リストにアクセスできることです。
預金通帳や保険証などを集め、財産リストをつくりましょう。
骨董品や貴重品について記録するのも忘れてはいけません。
他にも不動産や車など、財産として数えられるものは全てリストアップしておきます。
すると、残された家族が遺産を把握するのに役立ちます。
財産リストをつくる過程で「この通帳はもうしばらく使っていない」「保険が満期になってしばらく経つ」「受け取り手のいない貴金属や着物は遺品として残すより、現金化しておいた方がよいのでは?」などと、処分した方がよいものについて気がつくときがあるはずです。
気がついたときが処分どき。残してしまうと家族が困るようなものは、解約したり売却したりして現金に換えておきましょう。

財産リストをつくると、自分の所有している全財産の金額が把握されます。
ここで、生きている間の生活プランを考えましょう。
シニアになると年金収入だけになるなど、手に入る現金の金額が限られてきます。
年金と、これまで貯蓄してきた金額だけで生活できるのか。
また、今の家で一生を暮らすのか、どこかのタイミングで施設に入る方がよいのか。
この時点でシニア以降のライフプランを描いておくと、エンディングノートをスムーズに書き進められます。
ライフプランをたてるときには、配偶者や子世代を交えてしっかり話し合いましょう。
家計の把握や老後にいくらかかるかが分かりづらいと感じたら、ファイナンシャルプランナーなどプロの手を借りるのもおすすめです。
今後のライフプランが決まると、エンディングノートを誰に託すかが明確になります。
子どもと同居すると決めた人は同居する子どもに託すのが一番ですし、年下の配偶者と2人暮らしであれば、託す人としては配偶者が第一の候補に挙げられます。
また、エンディングノートを託せる身内がいないなら、司法書士や行政書士などといった専門家と身元保証契約や死後事務委任契約を結ぶのが安心です。
身元保証契約とは入院や手術時に身元保証人となってもらう契約、死後事務委任契約とは葬儀やお墓の手配、死後の手続といった死後事務を行ってもらう契約を指します。
とはいえ、専門家と契約を結べば、何かとお金がかかるもの。
予算不足が不安な人は、友人や入所予定の施設に、いざというとき身元保証人になってくれないか相談してみましょう。
地域の福祉サポート施設が相談に乗ってくれる場合もあります。
託す人を決めたら、エンディングノートづくりに取りかかります。
自分に何かあったとき、誰がどのように動いてくれるのかをイメージしながら書くと、エンディングノートはぐっと書きやすくなります。
エンディングノートを書いていると、「葬儀やお墓の準備をしなければ」「きちんとした遺言書を準備しておかなければ」など、さまざまなことに気づくはずです。
やりやすいと感じることから取りかかりましょう。
子どもとの同居や施設への入居といった引っ越しの予定があるなら、徐々に不用品を片付けていきましょう。
引っ越し先の間取りに合わせて家財をダウンサイジングするのが理想です。
「亡くなるまで自宅で」と決めた人は、家全体をシニアの生活にふさわしいスッキリしたコーディネートに変える必要があります。
足腰が弱くなってくると、少しの段差でもつまずいたり、床置きになっている細々したものに足を取られたりして転んでしまう可能性が高くなるためです。
シニアになってからの転倒は骨折のリスクが高く、回復せずにそのまま寝たきりとなってしまうケースが多々あります。
家財運びに自信のない人は、子どもや知人の手を借りるほか、引っ越し業者の模様替えサービスなどを利用しましょう。
シルバー人材センターに相談し、比較的体力に自信のあるシニアにお手伝いを依頼するという手もあります。
パソコンやスマホの中にあるデータ、SNSなど各種サービスのアカウントなどを全て把握し、整理することを「デジタル終活」といいます。
エンディングノートを書く際に取り組んでいる人もいるかもしれませんが、デジタル終活の項目がついていないエンディングノートもあるため、取り組んでいない人はここで行っておきましょう。
デジタルデータは、目に見えません。
よって残された人が遺品整理をするときに見逃す可能性が高く、またパスワードがかかっているPCやスマホはそもそも開くことができないので、データの管理もままなりません。
パソコンやスマホの中を整理するほか、残される家族に必要なデータを出力しておいたり、パスワードを知らせておいたりして情報共有に努めましょう。
また、利用しているインターネットサービスのアカウントやパスワードを書き出しておき、自分の死後に家族がサービスの解約やアカウント削除をできるようにしておくのも重要です。
すでに使っていないサービスがあったら、この機会に解約しましょう。
自分の希望を託して初めて、終活が形になります。託すべき人にエンディングノートのありかを教えておきましょう。
以上、終活のやることリストについて解説しました。
今後の自分のライフプランが定まって初めて、終活は現実味を帯びてきます。
終活をするなかで「これからの自分」について考える時間を設け、未来を豊かなものにしましょう。
終活について興味を持ち始めた方は、幅広いジャンルを網羅している、シニアのための終活情報メディア「ひとたび」もおすすめです。
興味のある方は、ご覧になってみてください。
禅宗(曹洞宗・臨済宗)のお布施はどのくらいなのだろう?
疑問を持つ方にも予め相場を知っていれば安心に繋がります。
この記事では禅宗のお布施金額について解説させていただきます。
まずは下記の早見表をご確認ください。
曹洞宗・臨済宗ともにお布施の金額相場は下記の通りです。
| お布施 | お車料 | お膳料 | |
| 枕経 | 10,000~20,000 | 5,000 | |
| 通夜 | 20,000~30,000 | 5,000 | |
| 導師 | 150,000〜300,000 | 5,000 | 5,000 |
| 副導師 | 100,000~200,000 | 5,000 | 5,000 |
| 初七日 | 20,000~30,000 | 5,000 | |
| 週参り | 3,000~7,000 | ||
| 四十九日 | 20,000~50,000 | 5,000 | 5,000 |
| 祥月命日 | 3,000~7,000 | ||
| 百箇日 | 10,000~30,000 | 5,000 | |
| 盆・彼岸 | 10,000~30,000 | ||
| 一周忌 | 20,000~50,000 | 5,000 | 5,000 |
| 三回忌 | 20,000~50,000 | 5,000 | 5,000 |
| 入仏式 | 10,000~30,000 | 5,000 | 5,000 |
| 納骨 | 10,000~30,000 | 5,000 | |
| 墓石建立 | 10,000~50,000 | 5,000 |
曹洞宗・臨済宗の葬儀のお布施相場は20万円〜50万円となります。
先ほど上記でご覧いただいた早見表でも、金額にかなりの幅があります。
一体なぜなのかを解説させていただきます。
一つ目は、お勤めするお寺の人数によって価格が大きく異なります。
曹洞宗・臨済宗の葬儀では、通常最低2名以上のお勤めで行われます。
お一人でお勤めの場合は20万円になりますが、お二人でお勤めの場合は、2名分のご用意が必要になるため、相場は30万円以上になるでしょう。
2つ目の理由は、曹洞宗・臨済宗では2名以上でお勤めされる場合が多いのですが、2名とも住職の場合もあります。
ある住職が別のお寺の住職に副導師として葬儀のお手伝いを依頼する場合です。
この場合、お二人とも住職なので相場は高くなります。
一方で住職がご自身のお寺の息子様を副導師として手伝いを依頼する場合もあります。
この場合、別のお寺の住職がいらっしゃるケースよりは相場が下がります。
地域によってもお布施の相場は異なります。
上記の早見表よりも相場が高い地域もあるはずです。
目安として参考にしていただき、お住まいの地域が実際どうなのかは、お近くの葬儀社に尋ねてみるのも良いでしょう。
曹洞宗・臨済宗の葬儀は、お寺が3名以上でお勤めすることも珍しくありません。
これはなぜなのかを解説させていただきます。
曹洞宗・臨済宗は、鳴り物を使用します。
「チーン」、「ドン」、「シャーン」と葬儀場に響き渡る音は特徴的です。
「チーン」は印金(いんきん)、「ドン」は懺法太鼓(せんぼうだいこ)、「シャーン」は妙鉢(みょうはち)という仏具になります。
「チーン、ドーン、シャーン」とお一人で道具を持ち替えながら読経をする姿を想像してみてください。
急いで持ち替えないとタイミングがズレてしまいますし、慌てずにやれば、今度は間延びして、リズムがおかしくなってしまいます。
つまり一人でお勤めするのは、本来不可能なのです。
一生に一度のお葬式。大切なご家族を亡くした遺族のためにしっかりと責務を果たしたい。本来あるべき形で葬儀のお勤めとしたいと思うのは、葬儀の司式者として当然です。
決してお布施が欲しいからでも、豪華な葬儀をしたいからでもないのです。
曹洞宗・臨済宗の葬儀を行おうとすれば、お勤めする方が2名以上の葬儀になってしまうものなのです。
ちなみに3つの鳴り物を一人ずつが持てば3人になります。それに導師を加えた合計4名でお勤めする形を「片鉢(かたはち)」と言います。
この4名で行う形でさせ簡略した形式なのです。
歴史を辿れば元々は、3種類の鳴り物を2人ずつが持ち、それに導師を加えた合計7名の形を「両鉢(りょうはち)」が本来と言われています。
家族葬で行うのにお寺は2名でお勤めになった、お布施が高くなるから困るという声を聞くこともありますが、お寺からすれば本来7名を2名で行っているのです。
家族葬だと理解した上で簡略してくださっているのです。
このような理由から曹洞宗・臨済宗の葬儀をお一人でお勤めする場合、ご遺族からすれば用意するお布施は少なくて済みます。
しかしお寺からすれば、本来不可能なことを可能にするために、どこかを省く割り切りが必要になるのです。
「本当は、○○が必要なんだけどなあ」
このように思っていらっしゃることもあるでしょう。
依頼する側は、そこをお寺に求めている自覚は必要です。
家族葬が主流になった今、割り切って協力的に行ってくださるお寺もあります。
一方でそれは間違っている、出来ないとおっしゃるお寺もあります。
お付き合いのあるお寺がある方は、そのお寺の考えにしたがって行いましょう。
曹洞宗・臨済宗では、お布施以外にも下記のものが必要になります。
葬儀の式進行では、仏弟子になるための戒名を授かる「授戒」がメインイベントになります。
戒名料をいただく際は謝礼として戒名料が必要になります。
お布施とは別にもう一つ袋を用意してお渡しします。
相場は5万円〜50万円とランクや文字数で異なります。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
交通費としてお車料を用意しましょう。
お車で来られる場合は、往復分のガソリン代と考えると良いでしょう。
相場は5千円〜1万円、タクシーでお越しになる場合は往復分の料金を想定してご用意する必要があります。
ご家族が送迎を行う場合、お寺で葬儀を行う場合は、用意をする必要はありません。
お寺様と一緒に会食をしない場合は、お膳料を用意しましょう。
昔は法要後にお寺様も一緒に会食を行うのが一般的でした。
現在は、お膳料を渡して済ませる方も多くなっています。
相場は5千円です。
広島県世羅郡世羅町にある火葬場、やすらぎ苑をご紹介させていただきます。

平成2年に建てられた「やすらぎ苑」は、築30年以上経過していますが、管理が行き届いているので現在も清潔感を保ち、最後の場に相応しい場所となっています。
自然に溶けこんだ静かな環境は、心を落ち着けて静かに過ごすのに適しています。

・住所 広島県世羅郡世羅町大字寺町138-1
・TEL 0847-22-5302(世羅町役場町民課)
・駐車場 普通車30台、身障者用2台
・火葬炉、炉前ホール、待合ロビー、待合室(和室)、講中室、収骨室

●交通のご案内
世羅高原ふれあいロードを目指して進むと、道沿いに「やすらぎ会館せら」が見えてきます。
こちらはJA尾道市が運営する葬儀会館です。
名称が似ているため、間違えやすいのでご注意ください。
やすらぎ苑火葬場は、やすらぎ会館せら手前の側道へ入ると到着します。

・タクシーの場合
JR備後三川駅から14分
JR吉舎駅から19分
・自家用車の場合
世羅町役場から11分
世羅ICから15分
甲奴ICから17分
| 世羅町民の方 | 12歳以上 | 20,000円 |
| それ以外の方 | 12歳以上 | 30,000円 |
| 世羅町民の方 | 12歳未満 | 14,000円 |
| それ以外の方 | 12歳未満 | 30,000円 |
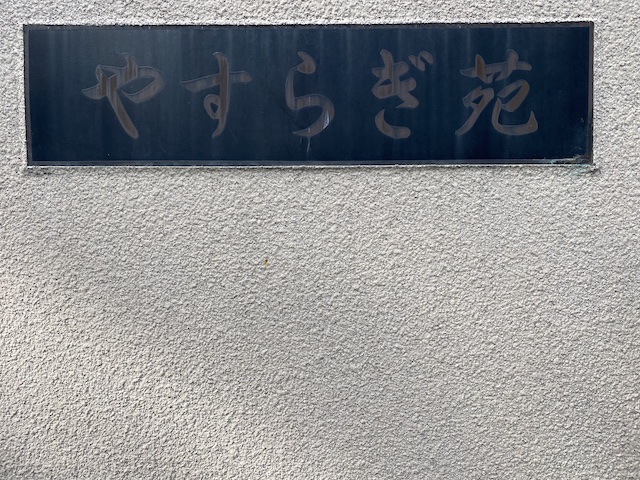
■注意事項
火葬の待ち時間は1時間半前後です。
他のご遺族の迷惑にならないようにお互いが静かに過ごしましょう。


■棺に入れてはいけないもの
火葬の妨げになるもの、環境に悪影響を及ぼすもの、危険物は副葬品として棺の中に入れることは出来ません。
主なものは下記になります。
・ビン類、ガラス製品
・金属製品
・プラスチック製品
・分厚い着物、毛布、布団
・ペースメーカーなどの医療器具
世羅町やすらぎ苑葬儀受付相談
TEL 0120-564-594(24時間365日対応)
世羅町やすらぎ苑で火葬、世羅町で葬儀・家族葬・一日葬・直葬のご相談を24時間365日承ります。
ご火葬のみ70,000円(税込77,000円)〜家族葬260,000円(税込286,000円)。
低価格で真心を込めてお葬式のお手伝いをさせていただきます。
・広島初の自宅葬儀専門葬儀社。
・地域最安値で高品質なサービス。
・料金はプランを選ぶだけのわかりやすい定額料金。
・社員は全員広島生まれ広島育ちの完全自社対応。
詳しくは下記からご覧くださいませ。
お葬式をどこで行うか、検討する際に近くの葬儀場をお探しになる方は多いと思います。
利便性が高いと感じるのが理由だと思いますが、近いことに魅力を感じる方は、自宅葬も選択肢に入れた方が良いこともあります。
その理由を解説させていただきます。
近くの葬儀場を探す理由を見つめ直してみましょう。
最初から「葬儀は葬儀場で行うもの」というイメージを持っていらっしゃる方も多いはずです。
今は葬儀会館で行うことが当たり前になっている時代、致し方ないのかもしれません。
自宅で葬儀を行うのは難しい、大変そうというイメージから、葬儀を行うなら葬儀会館とお考えの方も多くいらっしゃいます。
自宅の代わりとなる葬儀場を探すとなれば、「自宅から近い葬儀場」へ行き着くのも自然な流れだと言えます。
実際に葬儀を行ったご遺族様から伺ったアンケート結果では、葬儀場を選んだ理由の第一位は「家から近かったから」です。
では実際に近くの葬儀場で葬儀を行った場合、どういったメリットがあるでしょうか。
下記をご覧ください。
家から近いということは、移動距離も短く、移動時間も短縮されます。
遠いよりも近いというのは便利です。
近いというのは、忘れ物をしてもすぐに取りに帰ることができるというメリットがあります。行き来をするのも苦にはなりません。
家族だけでなく、近隣の方々も参列する場合は、遠いよりも近いほうが参列しやすいはずです。
このように近くの葬儀場で得られるメリットというのは、近くで解決できるコンビニの利便性に似通っています。
近くの葬儀場で得られるメリットは近いから便利であるということが主ですが、近いから得られる利便性を突き詰めていくと、一番は移動がないことになります。
自宅葬は移動がありません。
人によっては最も利便性が高いとなり得る可能性があるので見てみましょう。
自宅で葬儀であれば、移動する必要がなくなります。
移動に伴う時間が発生するのは、出棺して火葬場へ行く時だけになります。
近くの葬儀場であっても、葬儀会館で過ごす為の準備をしなければなりません。
礼服だけでなく通夜の晩に宿泊する家族は、翌日の着替えや身の回り品の用意など、宿泊準備が必要になります。
自宅であれば、このような準備を行う時間や手間も発生しません。
近隣の方にとって、近くの葬儀場よりも自宅のほうが近いということもあります。
徒歩で参列することができる場合もあるでしょう。
近くの葬儀場は、近くてなんでも解決できるのが便利ですが、自宅葬は移動することなく、家の中で全て完結します。
人によっては最も楽な形になり得るのです。
近くの葬儀場が真っ先に選択肢に上がっていた方も、もしも自宅葬がイメージのように大変ではないとわかった場合、どうでしょうか。
自宅葬という考えが全くなかった方も、選択肢の一つとして検討し始める方もいらっしゃるかもしれません。

一般的に多くの方が自宅葬から連想するのは、上記のような映像ではないでしょうか。
大きな白木祭壇、壁ぎわに黒白の幕が貼られ、座布団が並べられる。
いつもの自宅とは違う装いで、大掛かりなイベントに映ります。
近所や親族の方々が自宅に来られることを想像するだけで大変そうだと思いがちです。

現在の葬儀は、多くが家族葬になっています。
それは自宅葬も例外ではありません。
そのため先ほどご覧いただいたような自宅葬は、現在は少なくなり、多くが家族葬になります。
上記の画像のように、飾り付けに1畳分のスペース、お棺が1畳分のスペース、合計2畳分のスペースがあれば自宅で家族葬が行えます。
家族葬ですから近所の方々は参列を遠慮され、家族と近い親族のみで行われます。
10名〜15名で行うケースが多くなっています。
現在主流の家族葬であれば広い式場を必要としませんので、実は自宅でも出来る場合が多いのです。
また葬儀場の施設や設備にかかる費用が発生しないため、一般的に葬儀場で行うよりも葬儀代が安くなる傾向があります。
自宅で葬儀を行うのが難しくない理由は、下記の記事で詳しく解説していますので、よかったら合わせてご覧ください。
家から近い葬儀場、移動がない自宅葬、違いはこれだけではありません。
自宅葬には近い、遠いでは得られないメリットがあります。
現在のコロナ禍では、日常生活において、他人との接触を極力避けたいという心理が働く方も多いと思います。
葬儀でも葬儀会館よりも自宅のほうが感染リスクを最小限に抑えられると、自宅葬を希望する方も増えています。
特に自宅で行う一日葬は、人が集まるのが一度となりますので、安心して葬儀を行えると需要が伸びています。
お葬式に慣れている人は少ないでしょう。人は人生で喪主を経験するのは1回〜2回と言われています。
初めての方であれば、不安はつきものです。
このように不慣れなことを行うのですから、葬儀を行う場所まで不慣れな場所になるとどうでしょうか。
勝手がわかる一番落ち着く自宅であれば、不慣れなことでも対応できます。
安心できる場所で送ることは、ゆっくり最後の時間を過ごすことができて、お見送りにも好影響をもたらします。
最後の場所をどこで過ごすか、残された家族の都合だけでなく、本人の希望がどうだったのかという視点も大事です
人生で一番長い時間を過ごした場所、自宅で送ってあげることが、親孝行になる場合もあるでしょう。
入院生活が長く続き、自宅に帰ることができなかった方もいらっしゃいます。
本当は自宅で最後を迎えたかったという思いを持っていたとしたら、残された家族が叶えてあげるのは素晴らしいことです。
とはいえ自宅よりも葬儀場の方が良いと感じる方も多いと思います。
確かに便利な場所ですので、ここで葬儀場のメリットを今一度確認してみましょう。
・希望に応じて色んなスタイルの式場がある
・椅子席の会場だから長時間でも楽
・不慣れなことでも、任せておけば大丈夫という安心
・参列する方々用の駐車場があるから安心
・食事の準備や洗い物もしなくて済む
・家の中を見られることはない
・周囲に知られず葬儀を行うことも可能
これらが葬儀場で葬儀を行うメリットになります。
葬儀場によっても仕様が異なるため、吟味する必要があります。
「近く」というのは、あくまで判断材料の一つとして捉えましょう、最優先ではありません。
このように葬儀場選びで「近い」というのは利便性を感じやすく、葬儀場を選ぶ上で一つの判断材料になりますが、実際には「近い」には思ったほどのメリットはありません。
場合によっては自宅葬の方が良いとなる場合もあるのです。
では自宅葬が一番良いのかというとそうでもありません。
葬儀は、一生に一度のセレモニーですから、ご自身の置かれた状況や考えによってベストな選択は変わります。
「近い」で選ぶものではなく、慎重に選ぶ必要があります。
最後に正しい葬儀場の選び方をご紹介させていただきます。
葬儀場を選ぶ際、場所と料金は気になるところです。
ネットで各社を比較することは、葬儀でも可能ですが、例えば家電を購入する場合と葬儀では異なる面があります。
家電の場合は、購入すると手元に商品が自分のものとして残ります。
葬儀の場合は、購入しても手元に何か残るわけではありません。
よく遺骨だけが残ると言われますが、そのくらい実体として残るものは少ないのです。
そのため、精神的な満足感が得られるかどうか、ここがとても大きな要素になってくるのです。
精神的な満足感を左右するのは、人的サービスの質です。
ハード面で比較しがちな葬儀社選びですが、最も大事なのはソフト面です。
葬儀社スタッフのサービスの質は、葬儀の良し悪しをかなりの比重で左右します。
興味のある葬儀場があった場合、必ず一度事前に相談へ伺ってみることをおすすめします。
対応の良さそうな会社だなと感じれば、もしもの時に依頼するという形が良いでしょう。
「近いから頼んだけど、よくなかった」となるのを未然に防ぐことができます。
こちらについては、正しい葬儀社の選び方という記事もありますので、よかったら下記からご覧ください。
広島県世羅郡世羅町で低価格な葬儀、家族葬・一日葬・直葬であれば広島自宅葬儀社へお任せください。
広島自宅葬儀社は、広島初の自宅で家族葬を行う専門葬儀社です。
長年過ごしてきた家族の思い出がたくさん詰まったご自宅で、家族葬を行うお手伝いをさせていただいています。
実際に弊社へご用命いただいた場合のお支払い例や世羅町の火葬料、世羅町のお布施相場をご案内させていただきます。
お葬式の準備を行う際の参考になれば幸いです。

世羅町のご自宅で行う家族葬であれば、広島自宅葬儀社へのお支払いは¥265,000(税込¥291,500円)。
これ以上にかかる追加費用はございません。(世羅町への火葬料は別途必要になります。)
少人数の家族葬であれば葬儀場を利用しなくても自宅で可能です。
住み慣れた自宅で通夜・葬儀を行う家族葬は、ご家族の記憶に残る心温まるお葬式になります。
準備は弊社が全て行いますので、ご家族様は、ゆっくりと最後のお時間を自宅でお過ごしいただけます。
また、お付き合いのあるお寺で通夜・葬儀を行うこともできますし、自宅から近くにある集会所で通夜・葬儀を行うお手伝いも、同料金で対応させていただきます。

通夜式を行わず、葬儀告別式のみであれば広島自宅葬儀社へのお支払いは¥210,000(税込231,000)です。
通常は通夜式、葬儀告別式と2回儀式がありますが、こちらのプランは通夜式を省略して、葬儀告別式のみを行う一日葬プランです。
読経は1度になります。通夜の日は儀式がありませんのでご家族のみでゆっくりお過ごしいただけます。
親族で集まる機会は1度で良いとお考えの方や、日程的都合で一日で葬儀を終えたい方々に選ばれています。
また、通夜・葬儀を行うのに比べて料金も安価になっています。
三次市の病院でお母様がお亡くなりになられたとの一報を受け、広島自宅葬儀社がお迎えにあがらせていただき、世羅町のご自宅まで搬送をさせていただきました。
お母様が自宅へ帰るのは久しぶりとのこと、ご家族皆様に喜んでいただけました。
1日目のお母様、長男様、長女様が一緒に家族水入らずで過ごすお時間が、自然とこれまでを振り返ることができたり、感謝を伝えることができたり、様々な思いを消化出来る大切な時間になったと思います。
翌日はご親族様にもお集まりいただき、地元のお寺様に荘厳な読経をいただいた後、世羅町やすらぎ苑へ霊柩車でお送りさせていただきました。

火葬式プランは読経を省略した形で、最後の時間を自宅で家族だけでお過ごしいただき、翌日出棺となるプランです。
弊社へのお支払いは¥130,000(税込143,000)です。
ずっと家に帰りたかった、家に帰らせてあげたかったという思いを持つご家族に喜ばれています。
自宅で共に過ごす最後の時間が、かけがえのない思い出として残っていきます。
読経もお願いしたい方は、別途お布施3.5万円で火葬炉前で行う読経を依頼することもできます。

火葬のみを行う必要最小限の直葬プランであれば、弊社へのお支払いは65,000円(税込71,500円)〜90,000円(税込¥99,000)です。
2種類の方法から選択いただきます。
1つ目は、自宅にご安置後、翌日出棺となる方法です。
仏具などを省いた最小限のプランになりますが、最後の時間を自宅で過ごすことができます。
火葬までの時間は形式に捉われず、自由な形でお過ごしいただけます。
料金は90,000円(税込99,000円)。
2つ目は、臨終場所にお立ち会いいただき、その後は弊社にお任せとなります。
ご家族は翌日火葬場へお越しいただき弊社と合流する形です。
火葬場でお見送りを行って収骨を行い、終了です。
事情があって極力、簡単に葬儀を行いたい方向けのプランとなります。
料金は65,000円(税込71,500円)です。
葬儀に際して、プラン料金以外に別途火葬料が必要になります。
■世羅町の火葬料
| 世羅町在住の方 | 12歳以上 | 20,000円 |
| それ以外の方 | 12歳以上 | 14,000円 |
| 世羅町在住の方 | 12歳未満 | 30,000円 |
| それ以外の方 | 12歳未満 | 30,000円 |
■世羅町の火葬場
世羅町やすらぎ苑
広島県世羅郡世羅町大字寺町138-1
TEL 0847-22-1111(世羅町役場)
駐車場 30台
詳細は、下記の記事でご確認いただけます。
葬儀に際して、読経をお願いする場合は、別途お布施も必要になります。
世羅町のお布施金額は浄土真宗の場合、12万円〜20万円、浄土真宗以外の宗派では15万円〜25万円が相場になります。
これはお勤めの人数で変わってきます。
また浄土真宗以外の宗派では、戒名を授かりますので、戒名料が必要になります。
戒名料は、お寺様へ直接お尋ねください。
相場は5万円〜30万円、ランク、文字数で異なります。
お付き合いのあるお寺がない場合、弊社でご紹介させていただくことも可能です。
また、お布施の相場については下記の記事を詳しくご確認いただけます。
広島自宅葬儀社は世羅町の下記全域でお葬式のお手伝いをさせていただきます。
・青近 ・青水 ・青山 ・赤屋
・伊尾 ・伊折 ・宇津戸 ・小国
・小世良 ・小谷 ・上津田 ・賀茂
・京丸 ・黒川 ・黒渕 ・甲山
・三郎丸 ・重永 ・下津田 ・津口
・寺町 ・田打 ・徳市 ・戸張
・中 ・中原 ・長田 ・西上原
・西神崎 ・東上原 ・東神崎
・別迫 ・堀越 ・本郷 ・安田
・山中福田 ・吉原
広島自宅葬儀社はどんな特徴があるのか、ご紹介させていただきます。
冒頭で申し上げた通り、自宅で行う家族葬、自宅葬を専門にした葬儀社です。
最後の時間を自宅で過ごすことに最も価値があると考え、自宅で家族葬、一日葬、火葬式のお手伝いをさせていただいています。
不慣れな葬儀を自宅という最も落ち着く場所で行うことで、安心できます。
広島県最安値の料金となっています。
低価格なのは、葬儀会館で行う葬儀ではないため、施設や設備にかかる費用がありません。
安価な価格でお葬儀をご提供できるので、価格に反映させていただいています。
世羅町の方もどのプランを選択しても定額料金、追加費用をいただくことはありません。
実際やってみたら思ったより高かったということもありません。
誰もがわかりやすい料金体系なので、安心して葬儀を行うことができます。
広島の葬儀業界20年で得た経験とノウハウをご家族様のために尽くします。
自宅葬に対するどんなご要望もお任せください。
1級葬祭ディレクターが対応させていただきます。
葬儀会館で葬儀を行うのが主流ですが、以前は自宅で葬儀を行うのが当たり前の時代がありました。
自宅で行うのは大変だからというイメージがありますが、実際はそんなことはありません。
お飾りは1畳分のスペース、ご安置は故人様がお休み出来る布団1枚分のスペースがあれば可能です。
人生で一番長くいた場所、自宅から送り出せることはとても素敵なことだと思っています。
ご家族に囲まれて最後の時間を過ごす。
自宅葬は故人との最後の思い出になる優しい時間になるはずです。
弊社は24時間365日いつでも対応可能です。
世羅町の皆様のために全身全霊でお手伝いさせていただきます。
ご心配なご家族様がいらっしゃる場合、ご不安やお悩みもあるかもしれません。
その場合は、無料でメール相談、電話相談、資料請求、訪問相談など、ご希望の形でご相談を承りますので、ご遠慮なくご相談ください。
詳細は、下記からご確認くださいませ。
葬儀に参列する機会というのは、なかなかあるわけではありません。
いざ参列する準備を始めた時に数珠がない、どこかで購入しようとお考えになる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では数珠はどこに売っているのか、またどこで買うべきなのか。
あなたのご要望に合わせた最適な方法をアドバイスさせていただきます。
普段、数珠を買おうと思って買い物をする機会がないため、お気付きになってないだけで、実は数珠はさまざまな店舗で販売されています。
代表的な店舗は下記の通りです。
・仏具専門店(三村松など)
・紳士服店(青山・はるやま)
・ホームセンター(コーナン、ダイキ)
・ディスカウントショップ(ドン・キホーテ)
・ショッピングセンター(イオン、ゆめタウン)
・100円ショップ(ダイソー、Can Do)
お店に到着しても、どのあたりに数珠の売り場があるのか、わからないものです。
店員に尋ねても、店員さんが把握していなくて戸惑ってしまうこともあります。
そんな場合は、仏具コーナーがない場合、主に文具コーナー(香典袋の近く)、紳士服コーナー(黒ネクタイの近く)を探してみましょう。
では価格はどのくらいするのでしょうか。
買ったことがない方にとって、価格は気になるものです。
結論から言えば2,000円の予算があれば、多くの店舗でお買い求めいただけます。
価格帯は1,000円台〜2,000円台が一番多いボリュームゾーンです。
3,000円台以上の数珠は、しっかりした作りでこだわりのある物が多い印象です。
数珠は本来108の玉数から出来ていて、宗派ごとに定められた正式な数珠があります。
しかし一般的によく利用されているのは、どんな宗派にも対応出来て、かつ玉数も108ではなく、22玉、20玉、18玉など少なくなっています。
このような数珠は「略式数珠」と言われ、一方で本来の数珠を「本式数珠」と言います。
一般的に数百円〜数千円の多くは略式数珠、1万円以上のものは本式数珠の可能性が高いと言えます。
数珠の素材は、琥珀、真珠が最も高く、次に高価なのが天然石、天然木、木の実と続きます。アクリル、ガラスが安価な素材となります。
仏具専門のため、品揃えの豊富さは圧倒的に一番です。
種類が多いため価格帯も幅広く、1,000円台〜100,000円以上の数珠まで揃っています。
品質も圧倒的に一番です。種類が豊富なため、ご要望に応じた物をご用意していただけるでしょう。

価格帯は3,900円、4,900円、5,900円、6,900円と専門店に次いで豊富な品揃えです。
男性用、女性用ともに種類が選べるのが良い点です。
好き嫌いが分かれないオーソドックスな使いやすい色、形状が用意されているので、数がありすぎると迷ってしまうという方にはおすすめです。
品質も良く、ずっとお使いいただけるでしょう。
ただし、略式数珠のみ取り扱っているので、本式数珠が欲しい方は専門店に行きましょう。

男性用、女性用と取り扱いがあり、急な葬儀や取り急ぎのご不幸ごとなら十分対応出来ます。
価格帯は1,580円、1,880円、1,980円の3種類、色は4種類から選べる形です。
一生物として使うには品質的に若干不向きな印象です。

価格帯は2,000円前後の商品が1種類だけのことが多いです。
問い合わせてみたのですが、各店舗に男性用か女性用、どちらか1種類しか置いていないことが多く、店舗によっては取り扱っていない店舗もありました。
お買い求めの場合は電話で事前確認が必須です。
1280円のアクリル樹脂製の色違いが2種類ありました。
品質は簡易的なものといった印象です。お時間があるなら専門店をおすすめします。
店舗数が多いので利便性が高いと感じる方もいらっしゃるはずです。
時間がない場合、価格が安い数珠をお探しの方にはおすすめです。
価格は驚異の100円です。
クオリティも100円の商品とは全く思えない、しっかりしたものです。
お求めやすさで言えばダントツ一番です。
今とりあえず数珠が欲しいという方にはおすすめ出来ます。
私は見た時に「こだわらなければ、これでいい」と思いました。
マイナス点は、ガラス製のものが多いようで、落としただけで砕けてしまう恐れがあることです。
お店の方がおっしゃるには、回転の良い商品ではない為、売り切れの場合はすぐに再入荷がされないこともあるそうです。

| 費用 | 品質 | 種類 | 手軽さ | 専門性 | |
| 仏具店 | ¥1,000~¥100,000以上 | ◎ | 50種類以上 | △ | ◎ |
| 紳士服店 | ¥3,900~¥6,900 | ◎ | 5~10種類 | △ | × |
| ホームセンター | ¥1,500~¥2,000 | ○ | 3~4種類 | ○ | × |
| ディスカウントストア | ¥2,000 | ○ | 1種類 | ○ | × |
| ショッピングセンター | ¥1500 | △ | 1〜2種類 | ◎ | × |
| 100円ショップ | ¥100 | △ | 1種類 | ◎ | × |
ここからは状況別におすすめ店舗をご紹介したいと思います。
時間がない場合、上記の中から最寄りの店舗を探しましょう。
最も早いのは、参列する葬儀場で数珠を揃える方法です。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
とにかく安い数珠が欲しい方は100円ショップをおすすめします。
100円と告白しない限り、とても100円とは思えない品質です。
落としてしまうと割れやすいガラス製なので注意が必要ですが、安物を持っていると恥をかくことはまずありません。
夜間に数珠を揃えたいとき、残念ながらコンビニには置いていません。
しかしドン・キホーテであれば数珠を夜間でも購入できるかもしれません。
在庫があるかどうかお問い合わせしてから、店舗へ行くと良いでしょう。
種類は選べませんが、2,000円でお買い求めいただけます。
とにかく夜間に解決したい場合は、こちらの方法がおすすめです。
私はお急ぎの方で、近くに仏具専門店が無いという方を除いた全ての方に、仏具専門店で数珠を購入することをおすすめします。
(決して仏具専門店に頼まれたセールスではありません)
仏具専門店は価格帯が豊富で1,000円台からあるのです。
つまりホームセンターやショッピングセンターと同様の価格帯から専門店でも選ぶことが出来るのです。
同じ価格なら専門店の方が、種類が多いので、お気に入りの数珠を見つけやすくなります。
専門店だから種類が多いので、きっと自分に合った数珠を見つけることが出来ます。
数珠は色合いだけではなく、素材、サイズも色々あるのです。
普段、靴のサイズがみんな違うように、手の大きさも人それぞれ異なるものです。
自分の手の大きさに合った数珠を手に持つことは、愛着が湧きますし、落として紛失する可能性を軽減します。
冒頭で本来は宗派ごとに正式な数珠があると言いましたが、その本式数珠がたくさん揃っているのが仏具専門店です。
お子さんに数珠を持たせたい時は、仏具専門店一択です。
お子様の年齢に応じたサイズの数珠をお買い求めいただけます。
専門店の一番のメリットは、数珠の専門家が在籍していることです。
1,000円〜10,0000円以上の数珠から、あなたの希望する条件や状況に応じた最適な数珠を提案してもらえることです。
一般的な価格帯は5,000円〜10,000円とのことです。
お時間のある方は、一度お店を覗いてみてください。
葬儀の際に用意したお布施は、葬儀にかかった費用として相続税申告の際に相続財産から差し引けます。
差し引けるのはわかっていても領収書がない場合、どうしたらいいのかお悩みになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事ではお布施の領収書のもらい方、対処法について解説させていただきます。
相続税法では、相続人が支払った葬儀費用を相続財産から差し引くことができます。
お布施も葬儀にかかった費用として扱われますので、つまりお布施も相続税申告の際は控除が可能なのです。
この場合のお布施とは、臨終〜葬儀終了までの期間中に発生したお布施になります。
葬儀が終わった翌日以降のお布施、例えば四十九日など法事のお布施は含まれません。
お布施が控除されるとわかれば、領収書が欲しくなるものですが、ほとんどの方は領収書が手元にない状態のはずです。
葬儀当日にお布施の領収書が無くても、慌てなくて大丈夫です。
私は過去1500件以上の葬儀をお手伝いさせていただきましたが、葬儀の場面で領収書のやりとりを行っているのを筆者は見たことがありません。
お寺様からすれば、お布施はお気持ちで金額が決まっていないもの、遺族から当日お布施がいくら包まれるのか、知る由もありません。
前もって領収書を用意することは困難なため、この時点で領収書が無いのは当然なのです。
では葬儀後も領収書が無い状態が続くご遺族が多いのはなぜなのか。
これには理由が2つあります。
1つ目は、お布施は報酬ではないため、寄付の扱いとなり、領収書を発行する義務がないからです。
2つ目は、ご遺族から依頼を受けていないから発行していないのです。
領収書がない時の対処法は2つあります。
お寺様がご遺族から依頼を受けていないため、領収書を発行していないのであれば、依頼をしましょう。
多くのお寺様は、快く発行してくださるでしょう。
私が過去にお手伝いさせていただいた葬儀の中には、会社の創業者をお見送りする社葬も何度かありましたが、会社が施主になる葬儀の場合、全てにおいて事後処理のために領収書が必要になります。
その時は、決まってお布施の領収書をお寺様へお願いしたものです。
一般の方の葬儀であっても「相続の手続きで必要だから」とご遺族から何度も相談を受けました。
その度に「お寺様へお願いしてみましょう」と案内させていただきましたが、今のところお断りされた記憶はありません。
しかし中には領収書の発行は難しいとお断りされる場合もあるようです。
その場合は、ご自身で記録に残しましょう。
パソコンでWordやExcelを使って、箇条書きに残す。
それを印刷するだけで十分です。
いつ、どこで、誰の葬儀で、いくら支払ったのか、を抑えておきましょう。
必要なのは下記のポイントです。
・支払い日
・葬儀の場所
・誰の葬儀
・寺院の名前
・寺院の住所
・寺院の連絡先
領収書をもらう手順は下記の通りです。
時期は、葬儀終了後、なるべく早めに行いましょう。
連絡は電話で構いません。
葬儀でお世話になったお礼をまず伝え、それから領収書の発行を依頼しましょう
領収書の受け取り方法を確認しましょう。
自宅まで郵送いただくのは、お寺の手間を増やすことになるため、可能であればご挨拶をかねてお寺へ訪問するのが良いでしょう。
先方の都合に合わせて対応を心がけましょう。
お寺へ訪問することになった場合、菓子折りを持参する必要はありません。
手ぶらで結構です、葬儀でお勤めいただいた感謝の気持ちを伝えるだけで十分です。
四十九日の日程が気になる方は、合わせて日時を相談しておくのもよいでしょう。
お布施の領収書の宛名、金額、日付は確認しておきましょう。
その他にどんなものが葬儀にかかった費用とみなされるのか、見ていきましょう。
見落としているものがあるかもしれません、確認することで気づく場合もあります。
・死亡診断書の発行料
・故人の捜索、故人の搬送にかかった費用
・火葬、埋葬、納骨にかかった費用
・通夜・葬儀にかかった費用
・通夜・葬儀にかかった飲食費
・会葬御礼代
・寺院へ支払ったお布施・戒名料
・香典返しの費用
・仏壇・位牌の購入代金
・墓石・墓地の購入代金、墓地の借入れ代
・墓石への彫刻代
・葬儀後日に行われた法事代
・通常葬儀に発生しない費用
広島県東広島市豊栄町にある火葬場、豊浄苑(ほうじょうえん)をご紹介させていただきます。

豊浄苑は、火葬を行う施設と葬儀を行える施設が併設されているのが大きな特徴です。
県道沿いに立地し、平面駐車場も広いため、お車でお越しの方に利便性が高い施設です。
付近は静かな環境で、最後の時間を過ごす場所として相応しいものとなっています。

・住所 広島県東広島市豊栄町清武2665
・TEL (082)432-2563(豊栄支所地域振興課)
・駐車場 普通車50台
・開場時間 8時30分〜17時00分
(棺の受け入れ9時00分〜15時00分)
・休場日 1月1日
・火葬炉、お別れ室、収骨室、待合室、葬儀場、控室

●交通のご案内

安芸高田市から東広島市を結ぶ広島県道29号吉田豊栄線沿いに豊浄苑はあります。
・タクシーの場合
JR芸備線 向原駅から14分
JR山陽本線 西条駅から33分
・自家用車の場合
東広島市豊栄支所から7分
ジュンテンドー豊栄店より7分
道の駅湖畔の里 福富から10分
西条ICから28分
東広島市在住の方 12歳以上 ¥10,000
それ以外の方 12歳以上 ¥30,000
東広島市在住の方 12歳未満 ¥5,000
それ以外の方 12歳未満 ¥15,000

■注意事項
・施設の利用時間は9時〜17時ですが、火葬時間が2時間必要なため、受付時間は午後3時までとなっていますのでご注意ください。
午後3時までに到着できるようにしましょう。
・待合室での湯茶はセルフサービスとなっていますので、使用後は洗浄して元の場所へ収めましょう。
・通夜で豊浄苑を利用される場合、寝具が必要な方は各自で用意が必要になります。
■棺に入れてはいけないもの
・ビニール・プラスチック類
・ガラス製品
・金属製品
・布団・毛布、暑い着物
・書籍・果物など燃えにくいもの
・コルセット・ペースメーカーなどの医療器具
豊浄苑には通夜・葬儀を行う事ができる葬儀場があります。
公営施設のため、地域住民の方であれば、どなたでも低価格で利用することが出来ます。
利用する際は、祭壇、生花など葬儀に必要な物品は、葬儀社に依頼する必要があります。
■豊浄苑葬儀場の利用時間
・通夜 午後5時〜翌日午前9時まで
・葬儀 午前9時〜午後3時まで
・通夜から葬儀 午後5時から翌日午後3時まで
■豊浄苑葬儀場の使用料
| 東広島市の方 | それ以外の方 | |
| 葬儀のみ | ¥31,420 | ¥62,850 |
| 通夜・葬儀 | ¥62,840 | ¥125,700 |

東広島市豊浄苑葬儀受付相談
TEL 0120-564-594 (24時間365日対応)
東広島市豊浄苑で行う葬儀についてのご相談を24時間365日受け付けています。
豊浄苑でのご葬儀をシンプルでわかりやすい定額料金でお手伝いさせていただきます。
| 豊浄苑で家族葬プランA | ¥280,500 |
| 葬儀場使用料 | ¥62,840 |
| 東広島市火葬料 | ¥10,000 |
| 合計 | ¥353,340 |
プランには通夜・葬儀に必要なサービス、物品は全て含まれています。
※お布施、戒名料は含まれていません。
| 豊浄苑で家族葬一日プラン | ¥247,500 |
| 葬儀場使用料 | ¥31,420 |
| 東広島市火葬料 | ¥10,000 |
| 合計 | ¥288,920円 |
豊浄苑で一日葬(葬儀告別式のみ)行った場合は、税込288,920円になります。
プランには葬儀に必要なサービス、物品は全て含まれています。
※お布施、戒名料は含まれていません。
詳細は、広島自宅葬儀社のホームページからご確認いただけます。
ご相談は無料
24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも
フリーダイヤルへご連絡ください。
「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は
メールでのご相談も可能です。
ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
