ご依頼・ご相談の方はこちら
ご相談は無料
24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも
フリーダイヤルへご連絡ください。
「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は
メールでのご相談も可能です。
ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
広島県東広島市安芸津町にある火葬場、安芸津斎場をご紹介させていただきます。

山の中にある安芸津斎場は見晴らしが良く、瀬戸内海を一望できます。
最後の時を静かに過ごせる環境が整っていること、最後に瀬戸内海を見渡せるのは、海辺の町、安芸津町にとって相応しい場所であります。

・住所 広島県東広島市安芸津町風早10029-11
・TEL 0846-45-1102(安芸津支所地域振興課)
・駐車場 普通車20台、身障者用1台
・営業時間 9時〜17時
※到着時間は15時まで
・休場日 1月1日
・火葬炉、お別れ室、待合室、収骨室
※ペットの火葬は東広島市では行なっていません。民間の業者へ依頼しましょう。

●交通のご案内

お車でお越しの際は、団地の中を通って火葬場へと向かいます。
団地を抜けた後の入り口が間違えやすいのでご注意ください。
入口を右側へ進み、あとは一本道ですが、道幅が狭く離合できない場所もありますので、安全運転で行きましょう。

・タクシーの場合
新幹線東広島駅から19分
JR安芸津駅から6分
JR風早駅から8分
・自家用車の場合
東広島市安芸津支所から6分
ゆめマート安芸津から8分
西条ICから31分
| 東広島市在住の方 | 12歳以上 | 10,000円 |
| それ以外の方 | 12歳以上 | 30,000円 |
| 東広島市在住の方 | 12歳未満 | 5,000円 |
| それ以外の方 | 12歳未満 | 15,000円 |
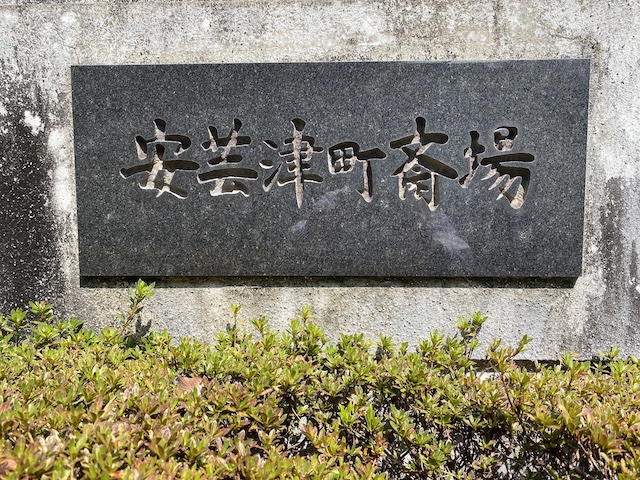
■注意事項
・火葬開始から終了までは、約1時間30分となります。
収骨のご案内が来るまでは、待合室でお待ちください。
・お茶などの飲食をされた場合は、ゴミを各自で持って帰りましょう。
■棺に入れてはいけないもの
一般的に棺に入れてはいけないものとされるのは、燃えないもの、燃えづらいもの、環境を悪化させるもの、危険物などです。
主な例は下記の通りです。
・腕時計、アクセサリーなど
・玩具、人形など
・分厚い着物、厚い布団、毛布、厚い書籍
・コルセットやペースメーカーなどの医療器具
・ビール瓶、缶、化粧品、ライターなど
安芸津斎場葬儀受付相談
TEL 0120-564-594(24時間365日対応)
安芸津斎場にて火葬をご検討中の方、葬儀については広島自宅葬儀社へご相談ください。
家族葬・一日葬・直葬をわかりやすいシンプルな定額料金でお手伝いさせていただいています。
◾️自宅で家族葬(通夜・葬儀)
・255,000円(税込280,500円)
◾️お寺で家族葬(通夜・葬儀)
・255,000円(税込280,500円)
※お寺によっては、使用料がかかる場合もございます。
◾️自宅で一日葬(葬儀のみ)
・210,000円(税込231,000円)
◾️火葬式(自宅安置)
・130,000円(税込143,000円)
◾️直葬
・65,000円(税込71,500円)
詳しい詳細は、下記からホームページでご覧ください。
急なお通夜や葬儀への参列となった場合、数珠がない場合があります。
気づいた時には、時間があまりない場合は焦ってしまうものです。
そんな時にどのように解決したらよいかを解説させていただきます。
数珠の由来は、お釈迦様が「百八の実を繋いで、いつも手にして三宝(仏・法・僧)を唱えれば、煩悩が消え災いもなくなる、心身も楽になるでしょう」と語ったことが始まりでした。
数珠は本来108の珠で出来ており、それは108の煩悩を現したものでした。
現在は108の珠で作られた数珠は少なくなり略式の数珠が多くなっていますが、現代でも仏式の葬儀では、数珠を持つことで仏様、故人様と心を通わせることができるということで大切な法具として扱われています。
つまり仏式のお通夜や葬儀に参列するなら数珠はあったほうが良いと言えます。
しかし絶対にないといけないものではありません。
ないからマナー違反、マナーが悪いと葬儀場で批判を受けることはまずありません。
数珠を持って参列しているが葬儀場で笑いながら雑談している方と、数珠は持っていないけれどご遺族の悲しみに寄り添い、故人様へ手を合わせ、ご冥福をお祈りされている方は、どちらがマナー違反でしょうか。
一番大切なのは、ご遺族の気持ちを考え、気持ちに寄り添った行動をすることです。
それでも数珠がないのは恥ずかしい、時間もないけれど何とか解決したいという方へ、これから解決方法を解説させていただきます。
まず急なお通夜や葬儀へ参列で時間がない場合、数珠を購入するのに費やす時間もないでしょう。ここでまず考えていただきたいことは、あなたがこれからどこへ行くのかです。
行き先である目的地で解決できるなら、寄り道にはならないため、時間がなくても解決できる1番の近道となるはずです。
つまり葬儀場で解決することを試みましょう。
行き先の葬儀場の連絡先を調べて、まず電話をしましょう。
電話をして、その場所に数珠が販売しているか、尋ねてみましょう。
大抵の葬儀場では、数珠が販売されています。
私が葬儀会館へ勤務していた頃は、毎日のように「すいません、数珠はありますか?」と参列者が窓口に尋ねて来られていました。
このようなことが葬儀会館では毎日のようにあるのです。
それだけ需要があるのであれば、普通の葬儀会館であれば対応をします。
数珠を置いていない葬儀場は少ないとはずです。
ですからまずは問い合わせてみましょう。葬儀場にあれば1番の時短になります。
葬儀場に問い合わせてみて、数珠が販売されていることがわかれば、葬儀場で購入すれば一番の時短になります。時間がなくても解決できる最速の方法です。
葬儀会館では、男性用、女性用、子供用と数種類置いてあることが多いです。
あくまで参列者の緊急用と認識しているため、価格もそんなに高いものは置いていません。
かつ100円ショップで販売されているような安物でもなく、作りもしっかりしています。
1000円台〜3000円台が主流です。
あまりに頻繁にこのようなことがあるため、葬儀場によっては貸し出し用のレンタル数珠を置いてある所もあります。
例えば家に帰れば自分の数珠はあるけれども、今日は急だったから数珠がないという方、
あるいは数珠を買うお金を持ち合わせていない方、数珠を買ってまで解決したくない方は、貸し出し用の数珠で対応しても問題ありません。
数珠は他人が使っていたものを使うのはマナー違反、一人一人が自分の数珠を持つものだという考えもありますが、数珠は念珠とも言うことから、自分の魂を表すものだという考えからです。
自分の魂であるのなら、葬儀がない時も肌身離さず持っておかねばなりません。
そのような時代もあったのかもしれませんが、現代で肌身離さず毎日数珠を持っている方は、どのくらいいらっしゃるでしょうか。
葬儀へ参列する時だけ数珠を持つ方と、貸し出し用数珠で対応する方に差があるとは思えません。
私が以前勤務していた葬儀会館では、数珠を貸して欲しいという声は、毎日のようにありました。
しかし数珠が売れなくなるからという理由で、貸し出し用数珠を置いていない葬儀場もあります。
自分のを持つべきだというのは、現代では建前と感じる所以です。
貸し出し用があるのであれば、選択肢に入れて構いません。
葬儀場に問い合わせてみて数珠が置いていないとなれば、ここで初めて寄り道をして数珠を買うのか、数珠なしで参列するのかを考えましょう。
寄り道して数珠を買う場合、一番確実なのはホームセンター、紳士服の青山、はるやま、そして仏壇店です。
しっかり吟味したい方は種類が豊富な仏壇店がおすすめです。
何でもいい、とにかく今の危機を早く乗り切りたい方は、最短で行ける所でお買い求めください。
時間的に猶予がない、厳しい場合、私は数珠なしで参列も選択肢の一つです。
「数珠を忘れてしまった人」となるのではなく、「急な参列で時間がなかった人」と堂々としていれば大丈夫です。
故人様、ご遺族様への思いがあれば、数珠がなくても心を通わすことはできるものです。
「あの人、数珠を持っていなかったよ」と周囲で噂になることはまずありません。
数珠がない自分には耐えられないという周囲の目を気にする方は心配無用です。
数珠なしで参列でも問題ありません。
しかし数珠がないと仏様に申し訳ないという方は、なんとかして用意する方向で行動しましょう。
兄弟(義理の兄弟)の葬儀へ参列することになった時、香典をいくら包むべきなのか。
香典の金額相場や注意点を1級葬祭ディレクターの筆者が解説させていただきます。
日本人の平均寿命は、男性81歳、女性87歳です。
多くの場合、兄弟(義理の兄弟)とあなたの年齢差は少なく、同年代の方が多いでしょう。
同年代である兄弟の葬儀が発生するというケースは、あなたもご兄弟もある程度年齢を重ねた状況にある場合が多く、主に70代以降から身近に起こり得る事として考えられます。
同じ屋根の下で生活を共にしているケースは少なく、世帯を別にして生活している場合が多いものです。
そのため葬儀の場面では兄弟であっても香典を用意する必要があります。
葬儀の場において、義理の兄弟への対応は実の兄弟と全く同じです。
葬儀場でも兄弟夫婦が隣同士で着席しているはずです。
序列は全く同じで、香典金額相場も全く同等の扱いをします。
香典金額の相場は下記を参考にしてください。
40代以降の方の香典金額相場は3〜5万円です。
あなたが現役でご活躍されている場合は5万円が相場です。
70代・80代など定年して年金生活者の方は3万円でも問題ありません。
香典は無理のない範囲で行うものです。
20代・30代でご兄弟の葬儀に遭遇することはあまりないかもしれませんが、相場としては30代の方は5万円、20代の方は3万〜5万円が相場になります。
年齢と共に収入が上がっていきますので、相場も上がっていきます。
ご兄弟が結婚されていた場合は、配偶者が喪主をされるでしょう。
ご兄弟が独身の場合は、あなたの両親が喪主になるでしょう。
葬儀場の受付係を通して香典を渡しても構いませんし、直接手渡しでも構いません。
あなたが既婚で配偶者と葬儀へ参列する場合、香典は1人分で構いません。
香典は世帯で一つ用意するものであるため、二人分用意をする必要はありません。
香典袋は1つ、名前の記載は夫婦の連名でも構いませんが、世帯主の名前一つであることが多いです。
世帯主の名前のみが記載されていても、夫婦で出した香典という意味合いになります。
2人で用意したものだからと1つの香典袋に二人分の香典を用意して、金額を2倍にする必要はありません。
夫婦で用意する場合も、一人で用意する場合も金額は同じとなります。
団塊世代の方など、ご兄弟が多くいらっしゃる方もいるでしょう。
その場合、香典金額は兄弟みんな同じにして統一したほうが無難です。
誰がいくらの香典を包んだのかは、香典帳に記録されます。
葬儀後に遺族がつい口を滑らせてしまえば、兄は少なかった、弟は少なかったと後々言われてしまうことや、陰口を言われてしまう恐れが出てくることもあります。
意図せずそのような事態になってしまったなら、後々後悔することになります。
皆が同じ金額であれば、噂も立ちません。
香典を包む前に相談出来れば良いでしょう。
ずっと幼少期を一緒に過ごしてきた大切な兄弟の葬儀です。
香典だけでなく、他に何かしてあげたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、供花を送るなどがおすすめです。
「兄弟一同」とご兄弟で一緒に花を送る場合、各個人が花を送る場合もあります。
供花を送るのが当たり前ではなく、気持ちで行うものですから、送りたいと思った方が行えばよいものですが、複数兄弟がいらっしゃる場合は、注意が必要です。
供花を送るならみんな送る、送らない場合はみんな送らないと統一したほうが無難です。
兄の供花はあるけれども、弟の供花はないという葬儀場になり、周囲が違和感を感じる事態になってしまいますので、こちらも兄弟で話し合って決めましょう。
兄弟(義理の兄弟)の葬儀で香典を渡す必要がない場合をご紹介します。
亡くなったご兄弟が独身で、両親も二人ともすでに他界している場合、あなたが喪主をする可能性が高いです。
あなたが喪主をする場合は、葬儀を行う側になり、香典をいただく立場になりますので、香典を準備する必要はありません。
その代わり、故人がお金を残していない場合、葬儀費用を負担しなければならない可能性があります。
葬儀に際して香典をお断りするケースも珍しくなくなりました。
そのような場合には、香典を準備する必要はありません。
以上、兄弟(義理の兄弟)の香典について解説しましが、香典の準備の仕方、マナーについて詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
親の葬儀へ子供である自分は香典を包む必要があるの?
遺族だから必要ないのかな?
この記事ではそんな疑問に対して解説させていただきます。
まず親の葬儀(義理の親の葬儀)であなたが喪主であれば香典を包む必要がありません。
喪主として葬儀の実行責任者になり、葬儀費用の負担をする立場になった場合は、香典を包む立場ではなく、香典をいただく立場になります。
例えばあなたの母(父)がお亡くなりになられ、あなたの父(母)が喪主をする場合は、あなたは喪主ではありませんので、香典を包む立場になります。
あなたが次男で長男が喪主をする場合も、あなたは喪主ではありませんので、香典を包む必要があります。
人がいつ亡くなるのかは誰にもわかりません。突然訪れた葬儀にも関わらず、遺族は大きなお金が必要となります。
香典は、葬儀費用の足しにしてくださいという意味もあり、日本人特有の助け合いの精神と親和性が高く、長年引き継がれてきた風習になります。
つまり喪主でない場合は、葬儀費用を負担する喪主の母(父)を助ける、喪主の長男を助ける意味合いがあります。
葬儀費用を負担してもおかしくない立場であることから、葬儀費用を負担しない代わりに包む香典のため、金額が一般の方々や親族よりも高額になることが多いです。
親へ包む香典金額の相場は、あなたの年齢によって変わってきます。
年齢と共に平均年収が上がる傾向から、年齢を重ねるにつれて香典相場も上がっていくイメージで捉えていただければと思います。
20代、30代、40代、それぞれ親の葬儀でいくら香典を包むのが平均値なのか、見ていきましょう。
あなたが20代であれば親(義理の親)への香典は3万円〜10万円が相場です。
あなたが30代であれば親(義理の親)への香典は5万円〜10万円が相場です。
あなたが40代以降であれば、親(義理の親)への香典は10万円が相場です。
あなたがご結婚されている場合、親の葬儀へ夫婦で参列となるでしょう。
その場合、香典は二人分必要ではありません。
香典は1世帯で一つするものです。
ですから香典袋は一つだけ用意して、香典を包んでください。
名前はあなただけの名前でも夫婦で出した香典という意味合いになりますし、お二人の連名で記載されても構いません。
そして包む金額を2倍にする必要もありません。
親へ香典を包むケースは、あなたが喪主ではない場合です、そして包む理由は葬儀費用の負担をする喪主を助ける意味合いだと先述しました。
それを踏まえて香典を包む必要がない時が2つあります。
1つは、親の葬儀費用を喪主の長男(長女)と折半すると決めている時です。
この場合、喪主は長男(長女)ではありますが、葬儀費用の支払いに関しては、喪主とあなたは同じ立場、支払う立場になります。
そのため香典を包む必要はありません。
2つ目は、喪主が香典を辞退すると決めている場合です。
その際は香典を包む必要はありません。
例えば父(母)が亡くなり母(父)が喪主の場合、年齢を重ねてもあなたと親は親子の間柄です。つい子供の立場で甘えたくなるものです。
香典もおろそかにしても構わないかなと思いがちですが、世帯を持っているのなら一人の大人として香典は用意したほうが賢明です。
渡す時は、葬儀の受付を通しても構いませんし、直接渡しても構いません。
渡した後に親が受け取れないとおっしゃる場合もあります。
その際は、無理に渡さず、金銭以外の形でフォローに徹しましょう。
葬儀だけでなくその後の生活環境の変化、事後の手続きなど色々出来ることはあります。
例えば喪主があなたのお兄様、お姉様だった場合、香典を包む必要があるのは、あなたが葬儀費用を負担しないとなっている場合です。
香典を包むかどうかの前に葬儀費用をどう負担するかを話しあっておくことが良いと思います。
話してわかることがあるはずなので、先入観や思い込みで「○○だと思っていた」という事態は避けましょう。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
例えば喪主の兄(姉)が香典をお断りしている、且つ喪主が葬儀費用は自分が負担すると決めている場合もあるでしょう。
この場合は、一応香典を用意して直接喪主に渡してみることをお勧めします。
香典お断りした理由は、おそらくあなたに向けたものではなく、一般参列者や親族のことを考えての判断のはずです。
葬儀費用の負担もなく、香典も包めないのはやり場がなく困る方もいらっしゃるでしょう。
その心情をそのまま伝えて香典を渡してみるとよいでしょう。
気持ちが伝われば、喪主も悪い気持ちにはならないものです。
家族や親族の誰かが亡くなったとき、悲しみと同時に頭へ浮かぶのが「会社で認められる休暇日数は?」「学校は何日休めるのか?」といった疑問でしょう。
一般的な事例をご紹介した上で、実際に休みたい日数が忌引き日数を超過してしまう時の対処法も解説させていただきます。
忌引きとは、家族や親族の訃報に接したとき、数日間のあいだ学校や会社を休んで静かに喪に服すことを指します。
現代では実質お葬式の準備や参列にほとんどの時間を費やすことになっていますが、古くから日本は「亡くなった人の近親者は死のけがれに触れているから、行動を慎まなければならない」という考え方がありました。
また、「しばらくは喪った家族を想い、冥福を祈るために集中すべき」という考え方もありました。
このことから、大事な人を亡くした人のために、企業や学校には休暇が設けられているのです。

忌引き日数は法律で決まっているわけではなく、それぞれの企業によって規定があります。
また、亡くなった方があなたにとって誰にあたるのか、関係性によっても日数が変わってきます。
一般的な目安は、以下の通りです。
| 亡くなった人が誰にあたるか | 血族の場合 | 姻族の場合 |
| 父母 | 7日 | 3日 |
| 配偶者 | 10日 | |
| 祖父母 | 3日 | 1日 |
| 子 | 5日 | 1日 |
| 孫 | 1日 | |
| 兄弟姉妹 | 3日 | 1日 |
| 伯叔父母 | 1日 | 1日 |
※生計を一にする姻族の場合は血族に準じる
「亡くなった日から」「逝去の翌日から」など、いつから始まるかは、企業によって違います。
また、忌引きが有給にあたるか、それとも欠勤扱いにならないだけで無給の休暇かといったことも、企業の判断に委ねられています。
そのため、あくまで上記は参考情報としてご覧いただき、実際の勤め先にご確認ください。
「忌引きで休める日数」と「実際に休まなければならない日数」には、開きがある人が多いでしょう。
何日取れるかに関わらず、「通夜や葬式が終わるまで休みたい」という人が多数いるためです。
一昔前、亡くなってからお葬式が終わるまでの日数は、3〜4日程度でした。
しかし現代では高齢多死社会の中、特に関東では火葬場の稼働率が上がって予約が取りづらくなっている地域が多数見受けられます。
加えて遺体の衛生保全技術も進み、亡くなってから葬儀まで一週間も日にちが空くことも珍しくありません。
遠方で葬儀がある場合は、移動日も考えなくてはいけません。
すると休まなければならない日数は、さらに長くなります。
また、祖父母を亡くした場合の忌引き日数は「3日間」ですが、前述のように亡くなってから3日のうちに通夜・葬儀、火葬まで済ませられるケースは、西日本では可能かもしれませんが、関東ではそう多くありません。
東京などでは3日間でお葬式を終えることは困難を極めます。
臨終から通夜当日までの間は、通学・通勤するという選択も可能ですが、同居していた祖父母が亡くなってしまったら、勉強が手につかないお孫さんもいるでしょう。
よって、規定の日数を超過したいと申し出る人も少なくありません。
その場合どうすればよいのか、立場の違いも合わせ、次項で解説します。
忌引きの日数は、学校の規則によって異なるため、学生手帳などで確認しましょう。
もしも定められた日数よりも休みたい場合は、学校へ連絡を入れる際にその旨を伝えましょう。
忌引きが延長になるか、欠席扱いになるか、確認しましょう。
なかには昨今の事情により、タブレットでの遠隔参加を出席扱いにしてくれる学校があるかもしれません。
それなら儀式のある日以外は欠席せずに済むでしょう。
長く休むことによる学業への影響が不安であれば、申し出てみるのも1つの手です。
就業規則で忌引きの日数を確認しましょう。
日数が足りないときは、次のような対応が考えられます。
直属の上司に自分の希望を伝え、よく話し合うことが必要です。
1.有給休暇をプラスして長く休む
どうしても長く休まざるを得ないときに有効です。
2.テレワークを行い、出勤扱いにしてもらう
遠方でのお葬式となった場合など、儀式のない日はパソコンを使って作業や伝達事項を行い、仕事をするという対応が考えられます。
3.半休を利用して、儀式のない日や時間帯に出勤する
忌引き休暇を半日単位で利用可能な場合に有効です。
通夜や葬儀の日まで、半日は出勤にあてるという対応をとれば、忌引きのとれる日数自体は延びます。
どの場合も休むなと言われることは少ないはずです。
焦点は、超過日数分をどのように処理するかという点になります。
有給休暇になるのか、ならないのか。
ならない場合にあなたがどのような対応をするかになってきます。
そして罪悪感を持つことはありません。
パートやアルバイトが忌引きを取れるかどうかは、やはり会社によって違います。
就業規則をしっかり確認しましょう。
その上で直属の上司に相談します。
「○日まで休ませて欲しい」と希望を伝えるのが良いでしょう。
もし、定められた日数よりも長く休みを取りたい場合には、上記「正社員」の項で伝えた1~3を参考にしてください。
もしかしたら、正社員には忌引きが認められていても、パートやアルバイトには認められず、無給や欠勤となってしまうかもしれません。
ただ、最近では厚労省により「同一労働同一賃金」が叫ばれており、正社員とパートやアルバイトの間の不合理な待遇差の解消が目指されています。
今後もこの取り組みが進めば、正規と非正規の福利厚生の格差は縮まっていくと考えられます。
電話一本で忌引き休暇を取ることはできますが、書類上の手続きも後で必要になります。
事実を記録として残し、処理を行うためです。
1.直属の上司や学校の担任、学務課などに電話連絡
まずは家族・親族が亡くなったこと、そして忌引き休暇が欲しいことを会社や学校に申し出ます。
メールよりも電話で連絡し、指示を仰ぐようにしましょう。
連絡すべき人は、会社であれば直属の上司、学校であれば担任の先生です。
大学生は学務課等に連絡し、担当部署を教えてもらいます。
2.必要書類の入手
忌引きの申請は電話で一旦は終了します。
葬儀が終わって出勤あるいは登校する際に残りの手続きを進めるケースが多いです。
たとえ葬儀の最中であっても手続きを終えないと認めないという会社は少なく、事情を汲んでくれるでしょう。
葬儀が終了すると必要な書類を提出しなければなりません。
多くの場合、必要になるのは会社や学校ごとに用意されている申請書と、葬儀日程を知らせる文書など実際に葬儀があった事実を証明するものです。
証明書は葬儀社へ相談すると作成してくれます。
3.可能なタイミングで必要書類を提出
必要な書類が揃ったら、可能なタイミングで会社や学校に提出します。
期日を設けていない場合が多いですが、忌引きが明けて初めて出勤、登校する日に提出するなど早めの対応を心がけましょう。
葬儀を終えて出勤する際は、上司や同僚など、関係者へ丁寧な挨拶をしましょう。
伝えるべきことは、以下の2点です。
■無事葬儀が終わったことの報告
「おかげさまで、滞りなく葬儀が終了いたしました」
■迷惑をかけてしまったことのお詫びと感謝
「みなさまには仕事面で多大なるフォローをいただき、誠にありがとうございました」
通例により、関係部署に感謝の気持ちとして手土産を配る職場もあることでしょう。
また、そのような慣習がなくても、お世話になった気持ちを示したいというときは、個包装の菓子折などを持参しましょう。
喪主を務めた場合など葬儀後の事務手続きで休みが欲しい時もあります。
この場合、忌引きにはなりませんが、有給休暇を取るか、公休の時に対応するかになってきます。
葬儀後の手続きは、「2年以内に行ってください」など期限の長い手続きがほとんどです。
そのため慌てず落ち着いて一つ一つ処理をしていけば良いものですが、それでも休みが欲しい場合は、事情を説明して相談してみましょう。
よくあるのが、土日が公休の方です。
休日に対応しようにも、役所が土日休みのため、何も出来ないということが起こります。
その際は、平日に休みを取りたい旨を相談してみましょう。
葬儀の日程が決まったら、すぐに会社や学校に連絡します。
大事なのは、忌引きの日数確認はもとより、「いつからいつまで休みを取りたいのか」をハッキリ伝えることです。
それによって、相手の対応も違ってきます。
もし、「分かりました、ゆっくり休んでください」と言われても、全ての日数を忌引きとして認められたという意味ではないかもしれません。
「規定によるとこの日までは忌引きが取れるようですね。次の日からは欠勤になってしまいますか?」
「忌引きの間は有給でしょうか?」といった確認をすることで、意図しない欠勤や無給による休暇を回避できるでしょう。
現代の忌引き規定と葬儀事情には乖離があり、後々の処理の問題はありますが、お葬式が終わるまで休めるという点は昔も今も変わらないものです。
お葬式が終わるまで休むことはできるだろうかという不安は覚えなくて大丈夫です。
希望を伝え、まずは相談してみましょう。
広島県府中市にある火葬場、上下斎場翁苑をご紹介させていただきます。

一番大きな特徴は火葬設備だけでなく、通夜・葬儀を行える葬儀場を併設している点です。
葬儀場は希望者が使用料を支払って利用するシステムです。
詳しくは後ほどご説明させていただきます。
設備も新しく無縁・無臭の火葬炉を完備した環境に優しい施設となっています。
駐車場が広いのも特徴です。

・住所 広島県府中市上下町上下253-2
・TEL 0847-62-3833
・駐車場 普通車70台
・火葬炉、炉前ホール、収骨室、待合室、葬儀場、親族控室
●交通のご案内

お車でお越しの際は、セブンイレブン府中上下店を目印に国道432号線を道なりに向かってください。
国道432号線沿いのセブンイレブン前に上下斎場翁苑への入口があります。
・タクシーの場合
JR上下駅から5分
JR備後矢野駅から10分
・自家用車の場合
府中市上下支所から5分
甲奴ICから15分
尾道北ICから30分
| 府中市内在住の方 | 12歳以上 | 20,000円 |
| 府中市外在住の方 | 12歳以上 | 50,000円 |
| 府中市内在住の方 | 12歳未満 | 11,000円 |
| 府中市外在住の方 | 12歳未満 | 28,000円 |
ご利用の際は、下記にご注意ください。
■注意事項
・火葬時間は約1時間30分となります。収骨時間の案内が来るまでは、待合室でお待ちください。
・他の家の方もいらっしゃる場合がありますので、静かに過ごしましょう。
■棺に入れてはいけないもの
燃えないもの、燃えにくいもの、環境に良くないもの、危険物などは副葬品として棺の中に入れることは出来ません。
下記が棺に入れることが出来ない物の一例です。
・金属類
・プラスチック類
・瓶、缶類
・着物、布団、毛布など
・スイカ、メロンなどの果物類
・ペースメーカーは爆発する危険性があります。取り出せない場合は、斎場職員に事前にお知らせください。
上下斎場翁苑には通夜・葬儀が可能な葬儀場が併設されています。
ただし、斎場は葬儀場の場所をお貸しするだけになります。
祭壇、お棺、生花など葬儀に必要な備品は、ご家族様が葬儀社へ手配するようになります。
葬儀社へ「上下斎場で葬儀を行いたい」と伝え、段取りをお任せするのが良いでしょう。
葬儀〜火葬、収骨まで車での移動がなく、霊柩車を必要としません。
全て一箇所で行えるのが特徴なため、現地集合、現地解散という方法に利便性を感じる方におすすめです。
| 府中市在住 | それ以外の方 | |
| 通夜・葬儀で利用 | 66,000円 | 132,000円 |
| 葬儀のみ利用 | 33,000円 | 66,000円 |

■上下斎場翁苑 葬儀受付相談
TEL 0120-564-594 (24時間365日)
上下斎場翁苑で葬儀のご相談を24時間365日承ります。
府中市の皆様にわかりやすい料金体系で安心、低価格なお葬式をお手伝いさせていただいています。
下記は、上下斎場翁苑で葬儀を行なった場合の価格例になります。
◾️上下斎場翁苑で家族葬(通夜・葬儀)
| 葬儀場で家族葬プラン | 280,500円 |
| 葬儀場使用料 | 66,000円 |
| 府中市火葬料 | 20,000円 |
| 合計 | 366,500円 |
・葬儀場で通夜・葬儀終了までに必要な物品・サービスは全てプランに含まれています。
・通夜の晩は宿泊も可能です。
・寺院へのお布施、戒名料は含まれていません。
上下斎場翁苑で家族葬(葬儀告別式のみ)
| 葬儀場で家族葬一日プラン | 247,500円 |
| 葬儀場使用料 | 33,000円 |
| 府中市火葬料 | 20,000円 |
| 合計 | 300,500円 |
・通夜式を省き、葬儀場で葬儀のみ行うプランです。
自宅で一晩過ごし、翌日葬儀のみ葬儀場を利用するという方法になります。
自宅で通夜を過ごすのが難しい方は、1日目から上下斎場で過ごし、翌日葬儀告別式のみ行う方法も可能です。
その場合、上下斎場の使用料が33,000円→66,000円になります。(その他の料金は変わりません)
・寺院へのお布施、戒名料は含まれていません。
お葬式は、故人の最後の旅立ちです。
適切な準備と計画により、故人の願いを尊重し、遺された人々が故人を心から偲ぶことのできる葬儀を行うことができます。
ご家族様へ家族の一員のように寄り添い、心温まるご葬儀を誠心誠意取り組ませていただいています。
分からないこと、不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談下さい。
広島県山県郡北広島町で低価格なお葬式、家族葬・一日葬・直葬であれば広島自宅葬儀社へお任せください。
広島自宅葬儀社の料金プランは、いずれもわかりやすい定額料金。
北広島町全域を低価格で真心込めてお手伝いさせていただきます。
弊社の料金プラン、北広島町の火葬料や寺院のお布施相場をご紹介させていただきます。
広島自宅葬儀社の料金プランは、シンプルでわかりやすい定額料金。
プラン価格=広島自宅葬儀社へのお支払い額、わかりやすいのが特徴です。
●下記でご紹介させていただくそれぞれのプランには、お葬式に必要なものは全て含まれています。
●プランに、北広島町の火葬料、寺院へのお布施は含まれていません。
●ご家族様がオプション品をご注文しない限り、追加費用はかかりません。

自宅で通夜・葬儀を家族葬で行う形式は¥255,000円(税込¥280,500)となります。
住み慣れた我が家で行う自宅葬は、大変なイメージがありますが、家族葬であれば接待・準備に追われることもありません。
一番落ち着く自宅で、ゆっくり故人様と最後のお別れに専念できます。
また、葬儀への参列は遠慮するが、一言お別れの挨拶だけしておきたいというご近所の方々にとっても葬儀会館よりも近く、足を運びやすいメリットがあります。
葬儀会館の場合は、支度や移動が伴いますが、自宅での葬儀であれば支度も移動もありません。
火葬場へ行くご出棺のお時間までゆっくり自宅でお過ごしいただけるもの特徴です。
葬儀の準備・進行は全て弊社にお任せいただけます。
この他にご家族様がお付き合いのあるお寺で行う家族葬、ご自宅の近くの集会所で行う家族葬も同料金でお手伝いさせていただいています。

通夜・葬儀と2日間で行う従来の形ではなく、通夜式を省いて葬儀告別式のみ行う形の一日葬プランは¥210,000(税込¥231,000)です。
1日目は宗教的儀式がありませんので、礼服を着用する必要もなく、ご家族でゆっくりお過ごしいただけます。
ご親族が集まるのは葬儀告別式のみになりますので、コロナ禍では感染リスクが軽減されると需要が増えています。
ずっと千代田の病院で療養中だったお母様。
長女様が同じ北広島町内在住、次女様は広島市内に在住でした。
久しぶりに自宅へ帰らせてあげたい、そして自宅でお葬式をしてあげよう、そして弊社へご依頼となりました。
久しぶりに家族で集まって最後の夜を自宅で過ごし、翌日葬儀告別式を行いました。
最後に親孝行が出来てよかったとおっしゃっていただけました。
| 一日葬プラン | 231,000円 |
| 北広島町火葬料 | 28,000円 |
| お布施 | 70,000円 |
| 合計 | 329,000円 |

宗教的な儀式はしないけれども、自宅で最後にお別れをしてから出棺するのが火葬式プランです。
こちらのプランには仏具やお別れ用の花、火葬終了後に遺骨を安置するお飾りがセットについています。
低価格でお葬式が行えること、最後の時間を自宅でゆっくりお過ごしいただけるのがメリットです。
家に帰らせてあげたかったというご家族から好評です。
料金は¥130,000円(税込¥143,000)となります。
ご希望の方は、お布施35,000円で火葬炉前で行う簡単な読経をお願いすることもできます。

弊社で一番安価なプランは直葬プラン¥65,000円(税込71,500円)〜90,000(税込¥99,000)です。
ご事情があってお葬式にお金をかけられない方、低予算で葬儀を行いたい方に選ばれています。
方法は2種類からお選びいただけます。
■方法1 自宅で一晩過ごして翌日ご出棺
ご逝去後、ご自宅にご安置させていただきます。
それから一晩自宅でお過ごしいただき、翌日ご出棺となります。最後の時間を自宅でお過ごしいただけるのがメリットです。
自宅直葬プランは90,000円(税込99,000円)となります。
■方法2 臨終に立ち会い〜火葬場でのお別れに立ち会い
ご逝去後、弊社にて故人様をお預かりさせていただきます。
翌日火葬場で弊社と合流いただき、火葬場にて最後のお別れを行っていただきます。
極力全てを葬儀社にお任せしたいというご家族に選ばれています。
こちらの直葬プランは65,000円(税込71,500円)となります。
弊社への費用だけでなく、お葬式には火葬場を使用する際の火葬料が必要になります。
下記でご確認くださいませ。
| 北広島町内在住 | 12歳以上 | 28,000円 |
| それ以外の方 | 12歳以上 | 56,000円 |
| 北広島町内在住 | 12歳未満 | 23,000円 |
| それ以外の方 | 12歳未満 | 46,000円 |
北広島町には、千代田地域に慈光苑、豊平地域に光寿苑、芸北地域に浄寿苑、3つの火葬場があります。
最も利用されているのは千代田にある慈光苑です。
一番新しく綺麗、火葬設備が新しいこともあり、時期によっては他の火葬場が修理期間中、慈光苑のみ稼働ということもあります。
■慈光苑(千代田地域)
広島県山県郡北広島町壬生笹井河内606
TEL 050-5812-1854(北広島町役場町民課)
詳細は下記の記事でご確認いただけます。
■光寿苑(豊平地域)
広島県山県郡北広島町戸谷731-1
TEL 050-5812-1122(豊平支所)
詳細は下記の記事でご確認いただけます。
■浄寿苑(芸北地域)
広島県山県郡北広島町細見10141-16
TEL 050-5812-2110(芸北支所)
詳細は下記の記事でご確認いただけます。
この他にもお寺様に読経を依頼する場合、別途必要になるものがお布施です。
北広島町のお布施相場は、臨終から葬儀終了まで浄土真宗が平均10万円〜15万円、その他に御車料、御膳料1〜2万円が相場です。
他宗派の場合は、18万円〜23万円、その他に御車料、御膳料として2万円が相場です。
この他にも戒名料が必要になります。戒名料につきましては、お付き合いのあるお寺様に直接お尋ねください。
相場は5万円〜20万円、ランクや文字数などで異なります。
お布施相場についての詳細は、下記でご確認ください。
北広島町の下記エリアは下記になります。(あいうえお順)
・阿坂 ・有田 ・有間 ・筏津 ・石井谷 ・板村 ・今田
・今吉田 ・岩戸 ・後有田 ・雲耕 ・移原 ・大字
・大暮 ・大塚 ・大利原 ・大元 ・奥中原 ・奥原
・海応寺 ・上石 ・苅屋形 ・川井 ・川小田
・川戸 ・川西 ・川東 ・木次 ・草安 ・蔵迫
・荒神原 ・小原 ・古保利 ・才乙 ・志路原 ・下石
・新氏神 ・新郷 ・新庄 ・惣森 ・空城 ・高野
・田原 ・都志見 ・土橋 ・寺原 ・戸谷 ・中祖
・中原 ・中山 ・長笹 ・南門原 ・西宗 ・西八幡原
・橋山 ・春木 ・東八幡原 ・細見 ・本地 ・政所
・溝口 ・南方 ・壬生 ・宮迫 ・宮地 ・舞綱
・丁保余原 ・吉木 ・吉見坂 ・米沢
北広島町にお住まいの皆様のお役に立てるように、北広島町で一番低価格な葬儀を実現している葬儀社になります。
葬儀だけでなく、その後の納骨のこと、遺品整理のこと、相続のこと、葬儀後のことでお困り事があれば何でもサポートさせていただきます。
万が一の場合は、24時間365日ご対応させていただいていますので、いつでもご遠慮なくご相談ください。
何よりも優先して迅速に対応させていただきます。
弊社の詳しい詳細は、下記ホームページでご確認いただけますのでご覧ください。
広島県府中市にある火葬場、「府中・新市斎場やすらぎ苑」をご紹介させていただきます。

最新設備による無縁・無臭の火葬炉を完備している環境に優しい斎場です。
府中市と隣接する福山市新市町の方々が主に利用されています。
自然の中に調和する綺麗な斎場になっています。

・住所 広島県府中市広谷町563-7
・TEL 0847-40-0675
・駐車場 普通車35台、バス3台、車椅子1台
・火葬炉、お別れ室、待合ホール、収骨室
●交通のご案内

・タクシーの場合
JR高木駅から4分
JR鵜飼駅から6分
・自家用車の場合
府中市役所から9分
福山市 新市支所から4分
府中市 天満屋から10分
尾道北ICから23分
| 府中市・新市町に在住の方 | 12歳以上 | 20,000円 |
| それ以外の方 | 12歳以上 | 50,000円 |
| 府中市・新市町に在住の方 | 12歳未満 | 11,000円 |
| それ以外の方 | 12歳未満 | 28,000円 |

ご利用の際は、下記にご注意ください。
■注意事項
火葬における待ち時間はおよそ1時間30分です。
その間は収骨のご案内があるまで待合室でお待ちください。
■棺に入れてはいけないもの
下記のものは副葬品として棺の中に入れないようにご注意ください。
火葬の妨げになる場合や、事故を起こす恐れがありますのでご協力をお願いします。
・ビール瓶、缶類、プラスチック類
・ライター、スプレー缶
・時計、ゴルフクラブ、メガネ
・燃えにくいもの(厚さのある毛布、布団、着物、ぬいぐるみ)
・医療器具(ペースメーカー、コルセット)
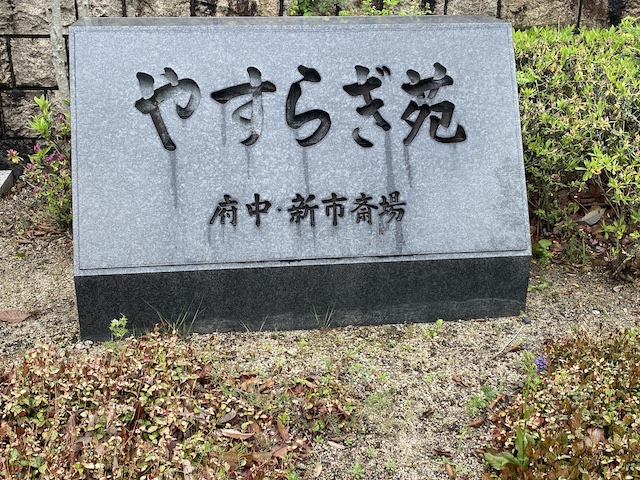
■府中・新市斎場やすらぎ苑葬儀受付相談
府中・新市斎場やすらぎ苑で火葬葬儀受付相談 TEL 0120-564-594(24時間365日対応)
府中・新市斎場やすらぎ苑にて火葬をご検討中の方で、葬儀についてお困りごとやお悩みごとがありましたら、いつでもご相談ください。
家族葬(通夜・葬儀)26万円、直葬(火葬のみ)7万円、わかりやすいシンプルな定額料金でお手伝いさせていただいています。
ご火葬のみ(直葬)プラン
葬儀一式70,000円(税込77,000円)
・ご搬送 ご逝去場所〜霊安室へお預かり安置
・ご搬送 霊安室〜火葬場
・搬送シーツ
・棺(布団など一式)
・骨壷(骨箱、風呂敷など一式)
・ドライアイス
・死亡届手続き代行
■火葬料20,000円
(府中市・新市町の方20,000円 それ以外の方50,000円)
■総合計97,000円
※事前にご相談いただいた方は、上記価格より5,000円割引させていただきます。
■プランの流れ
お迎え〜霊安室へ搬送。霊安室でのご対面は出来ません。
翌日、火葬予約時間に合わせて府中・新市斎場やすらぎ苑にお越しいただき、火葬前に短時間のお別れが出来ます。
■対応地域
府中市全域
■オプションになるもの
・花束 5,500円(税込)
・お別れ花 22,000円(税込)
・遺影写真 19,800円(税込)
・お寺様による炉前読経16,500円(税込)※別途お布施35,000円が必要となります。
詳しい詳細は、下記からホームページでご覧ください。
お葬式代がない、葬儀費用が払えないかもしれないとお困りの方へ、お金がない時にどうやって葬儀を行うかに焦点を当てて1級葬祭ディレクターの筆者が解説させていただきます。
どういう葬儀社へ依頼するべきか。
具体的な例を示してお役立ていただくことを第一に考えて解説させていただきますので、最後までよかったらご覧ください。
ネット上にはお葬式代へ不安を持つ方へ向けての情報は載っていますが、うわべだけの情報ばかりで本当に役立つものなのか疑問です。
下記はよくネット上に掲載されている解決方法です。
1.給付金を受け取りましょう
2.クレジットカードで分割払いをしましょう
3.信販会社の葬儀ローンはいかがですか?
4.葬祭扶助制度を利用しましょう
給付金は自治体によりますが、受け取れる金額は3万円〜5万円が相場です。
3〜5万円では葬儀代を全て賄うことはできません。
またこの給付金が受け取れるのは葬儀後1ヶ月〜になりますので、葬儀が発生してすぐに受け取れるお金ではありません。
このような理由からあてにできません。
クレジットカードで分割払いという手段は、葬儀に限らず日常生活において、急にまとまった支払いが必要な時にすぐに思いつく方法です。
クレジットカードで分割払いという方法は、誰もが思いつきます。それができないから困ってるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
クレジットカードには限度額があります。
それを超えてしまう葬儀代の分割払いはできません。
信販会社のローンには審査があります。
年収や勤務先、その他の借り入れの有無などを申告します。
定職について毎月決まった収入がある方は、審査に通りやすいものです。
そもそもこの信販会社のローン審査に通る方であれば、その多くの方は「葬儀代が払えない」というお悩みには至ってないでしょう。
「年金暮らしで収入も少ないので、きっとローン審査は通らないと思う」
きっとローン審査には通らないだろうと自覚のある方にとって、信販会社の葬儀ローンというアドバイスは全く意味のないもの、有効ではありません。
葬祭扶助制度は国が葬儀費用を負担してくれるものですが、利用出来る方は生活保護を受けている方、そして身寄りのない方です。
生活保護を受給していらっしゃる方には有益な情報になりますが、現在生活保護を受給していない方々にとっては役立つことはなく、羨ましさを感じるだけで有益な情報にはなりません。
この記事では、現在預金がほとんどない中で葬儀が発生しそうな方、葬儀代どころか日々の生活がやっとの方、そんな方々へ突然ご不幸が訪れて「葬儀代が払えない」と頭を抱えなくても済む方法をお伝えさせていただきます。
この危機を乗り越える方法を、何度も実際に相談に乗ってきた葬儀業界20年以上の筆者が実体験を踏まえてご紹介させていただきます。
クレジットカードの限度額が高い方、信販会社へローンを組むことが出来る方、現在生活保護を受けていらっしゃる方は、すでに解決できますのでこの記事をこれ以上読む必要はありません。
そうでない方は最後までしっかり読んでください。
年金生活者は、偶数月には年金が振り込まれます。
つまりローン審査が通らない、毎月の分割払いよりも2ヶ月に一度、年金が振り込まれる月に支払うという方法はできないだろうか?
臨機応変に事情に応じて融通の利く葬儀社はないだろうか?
これが年金生活者の方々にとって一番知りたい情報のはずです。
しかしネットには答えがありません。
ですから冒頭に私はうわべだけの情報しか載っていないと申し上げました。
ご安心ください「2ヶ月に一度、年金が入る月にのみ分割払いに応じてくれる葬儀社はあります」
私は広島自宅葬儀社で何度もそのような方々のお手伝いをさせていただいています。
10万円の葬儀代を5回払い(4月、6月、8月、10月、12月)もありました。
弊社の場合は対応地域は広島県ですが、このような対応が可能な町の葬儀屋さんはどこの都道府県にもあるはずです。
全国区の葬儀社ではなく、地元の葬儀社に「2ヶ月に一度の年金月の支払いでも構いませんか?」と相談してみましょう。
葬儀は無理して行うものではありません。
出来る範囲で背伸びせずに行うこと、お金をかけることよりも生前に感謝する、心を込めて送る、気持ちの部分が大切です。
クレジットカードや信販会社の葬儀ローンなどを利用する場合、金利負担を考えて分割払いは助かるけれども、少しでも支払い回数を少なくしようとする心理が働きます。
ここが多少の無理を生じさせるポイントです。
少しでも負担がないようにするには、葬儀社と直接分割払い契約ができるところはないかを探してみましょう。
葬儀社からすれば信販会社を間に挟んだほうが、未収リスクがなく、楽で安心なのです。
それでもご家族様のために自らリスクを負って直接の分割払いに応じてくれる葬儀社というのは、どこの都道府県にもあるはずです。
「毎月15,000円づつでいいですよ」という葬儀社もあるはずです。
もし見つかれば、ご家族の無理のない範囲で月々お支払いできるでしょう。
クレジットカードには限度額があります。
限度額の高いクレジットカードを持参の方は、葬儀代が払えないとお悩みになってこの記事をご覧になっていることはないでしょう。
葬儀代をクレジットカードで分割払いでできないかとお悩みの方の限度額は10万円〜30万円になっている方が多いのではないでしょうか。
実際には葬儀代だけでなく日常での買い物をクレジットカードで行っている場合も多く、カードで使用できる金額=葬儀代とはならず、全てを葬儀代に使用できるわけではありません。
この場合、例えば葬儀費用が28万円だったとします。
クレジットカードAで14万円の支払い、クレジットカードBで残り14万円の支払いという、2枚のクレジットカードで支払う方法もあります。
または兄Aのクレジットカードで14万円、弟Bのクレジットカードで14万円、兄弟それぞれのクレジットカードでお支払いという方法もあります。
このような事情に応じた臨機応変な対応は、やはり地元の町の葬儀屋さんなら問題なく可能でしょう。
このようなことから、お葬式の予算が心配な方は全国区のCMでお馴染みの葬儀社よりも、地元の町の葬儀屋さんがおすすめです。
但し、実行前に本当にそれがご自身にとって一番無理のない最良な支払い方法なのか、確認してみてください。
いずれの方法を取るにしても、無理のない範囲で返済を行うのは必須です。
繰り返しますが、葬儀は無理して行うものではありません。
これまでは葬儀代がない方がどうやって支払いをしていくか、ここに焦点を絞って話してきましたが、次からは行う葬儀の内容について触れていきたいと思います。
まずお葬式代がないと不安になる前に、お葬式にかけられるご予算がいくらなのかを把握しましょう。
漠然と「お金がない」ではなく、いくら足りないのか、それとも足りるのか、把握していきましょう。
葬儀においては「給付金」「香典」ともらえるお金もありますが、あてにしてしまうと予想が外れてしまった場合にダメージを被るのはあなたです。
ですから、ここではもらえるお金はあてにせず、しっかり予算を把握していきましょう。
1.本人の預貯金を把握する
2.ご自身の預貯金から葬儀に費やせる金額を把握する
3.その他、兄弟など家族へ相談してみる
これらのことを整理していくと、いざお葬式が発生した時にいくらまでならお葬式代へ充てることができるのか。
把握することができます。
例えばこの金額が10万円だった場合、10万円以内で出来るお葬式を検討しましょう。
30万円だったら30万円以内のお葬式を、50万円だったら50万円以内のお葬式を検討しましょう。
ここで予算が5万円だった場合も、5万円以内のお葬式を検討しましょう。
5万円で出来るわけがないと葬儀社へ相談しないうちに自ら諦めてしまうことは避けましょう。
これはかなり大事です。
あなたの予算が5万円であれば、それを予め複数の葬儀社へ正直に伝えてみましょう。
相手が親身になってくれる葬儀社なのかどうかが依頼する前からすぐにわかるはずです。
ここでかなり依頼する葬儀社は絞れます。
自分の予算に見合う葬儀社が見つかるのか、到底見つからないほど困難なのか、徐々にわかってくるはずです。
良さそうな葬儀社が見つかれば、見積もりを依頼してみましょう。
できればもう1社見積もりを依頼してみて、複数社で比較検討できる状態にしておくと良いでしょう。
ここまでは希望するお葬式のスタイルからお葬式について考えるのではなく、予算から自分たちが可能なお葬式を考えるというプロセスを現時点では踏んでいただきました。
そのため、予算内に収まる葬儀社は見つかったけれども、考えていた葬儀と全く違うということが起こり得ます。
このようなことが起こらないためにも、今度はしっかり葬儀社と直接話をしながら内容も確認していくことが大切です。
ここで筆者が過去に執筆させていただいた下記の記事をよかったらご覧ください。
「一番安い葬儀、簡単なお葬式」というものが、どれだけ人によって認識が異なるのかを解説させていただいています。
家族の間での認識の違い、葬儀社との認識の違いなどが解けるかもしれない部分があると思います。
ここまでの過程を踏まえていけば、自分たちが無理難題を言ってしまっていると気づくこともあるかもしれませんし、葬儀社に希望を叶えてもらえたとなることもあるでしょう。
予算内で収まればOK、どうしても予算を超えてしまうのであれば、そこで初めて支払い方法について検討を始めましょう。
まずは葬儀社に支払い方法はどういうものがあるのか、そして分割払いに対応しているかを尋ねてみましょう。
信販会社を通さずに葬儀社独自で分割払いに対応しているところは数多くあります。
この場合、金利は0のところも多いはずです。
無理のない支払いが可能になります。
最後に、あてにしてはいけないと冒頭にお伝えした「もらえるお金」についても解説させていただきます。
都道府県によって異なりますが、健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入している方がお亡くなりになった場合、もれなく給付金(葬祭費)が受け取れます。
会社勤めの現役の方であれば協会けんぽなど社会保険のほうから埋葬料(費)として給付金をいただけます。
わかりやすく言えば名称が異なり、手続き先が異なるだけで、国民は必ずどこかから何らかの形でもれなく給付金を受け取れるということです。
平均して3万円〜5万円受け取れます。
お住まいの自治体で金額が異なりますので、東京都の方であれば「東京都 葬祭費」などで検索して確認してみてください。
葬祭費、埋葬料について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
突然やってくるお葬式、前もって準備しておくことは難しいものです。
香典という風習は、地域の助け合いの精神から生まれたものでもあります。
葬儀代の足しにしてくださいと地域のみんなで助け合って葬儀を行う文化が以前はありました。
葬儀を自分だけで行うものと考えなくて良いのです。
「香典をください」と親族へ言う必要はありません。
何もおっしゃらなければご親族の方々は香典を持参して来られます。
香典は「お断りしない限りは持参する」
そういう文化が今もあります。
葬祭費(埋葬料)を給付いただき、香典をいただき、残りがご家族の自己負担となるわけです。
これが最も自己負担額を抑えるお葬式の方法で、例えば給付金が5万円、親族3世帯から香典を3万円いただいた場合、自己負担は2万円となるでしょう。
弊社で行った実例をご紹介させていただきます。
■福山市の方が直葬を行う 参列者12名
| 直葬プラン | 82,500円 |
| 福山市火葬料 | 8,000円 |
| 合計 | 90,500円 |
| 福山市から給付(葬祭費) | 30,000円 |
| 親族からの香典 | 40,000円 |
| ご遺族の負担 | 20,500円 |
| 合計 | 90,500円 |
ご遺族のご負担は0円にはなりませんでしたが、20,500円となりました。
このようにできる限り負担を少なくして葬儀を行うこともできるのです。
通常葬儀社への支払いは当日が原則と思われている方もいらっしゃいますが、実は後日でも全く構わないところが殆どです。
後日支払いを理解してくれて、無理のない範囲で支払い期日を設定してくれる葬儀社へ依頼をすることをお勧めします。
信販会社にローンを組む必要はありません、事情を理解してくれて親身になってくれる葬儀社を探しましょう。
あなたの街にもきっといらっしゃるはずです。
広島県にお住まいの方であれば、広島県内ならどこでも広島自宅葬儀社にお任せください。
ご予算を伺い、ご家族に無理のない範囲で温かいお葬式を65,000円(税込71,500円)〜ご提案させていただきます。
無理のない範囲で行う分割払いもございますので、お困りの方のきっとお力になれます。
広島自宅葬儀社の詳細は下記からご覧いただけます。
葬儀・お葬式へ生花や盛籠を送りたい時、どう違うのかわからないため、どちらにするべきか悩まれることもあるでしょう。
この記事では生花と盛籠の違い、それぞれ誰が供えるものなのか、用途の違いなどをご紹介させていただきます。
生花と盛籠は、供花物と言います。
主な役割は死者の霊を慰める意味や故人へ生前の感謝の意を表す意味があります。
また、葬儀場を彩る飾りとしての役割もあります。
供花物がなくても葬儀は可能です。
葬儀において必ず必要な物ではありませんので「供花物がないとおかしい」とはなりません。
あくまでも葬儀の場においては装飾的な役割です。
従来は生花・盛籠だけでなく、花輪が会場入り口に飾られ、賑やかさを競うような時代もありましたが、現在は小規模な家族葬が中心になっています。
そのため賑やかさを競うということは見られなくなり、生花と盛籠は縮小傾向にあります。
葬儀において見栄の文化はなくなりつつあり、個人的に故人へ送りたいという方が送る形に変化しています。
生花と盛籠は葬儀場にお供えするものとして共通していますが、葬儀後の用途が異なります。
生花は、葬儀の最後に献花の場面があります。
棺の中に入れて差し上げる花として使用する場合が多くあります。
したがって棺の中を花でたくさん囲んであげたいという場合に有効です。
献花後に余った生花は、花束にして親族で分けて持ち帰る場合もあります。
盛籠は生花と違って葬儀の献花の場面では使用しません。
果物は火葬の際に棺の中に入れることをお断りされているところが多くあるためです。
火葬の妨げになるとあまりおすすめされていません。
代わりに葬儀後にお供え用の供物として自宅で使用されることや、終わってから親族で分けてそれぞれが家に持ち帰る場合もあります。
生花に比べて日もちがするのが盛籠の特徴です。
それぞれ葬儀場のどこに設置されるのか、違いがありますのでご覧ください。
生花の供えられる場所は、地域によって違いがあります。
主に関東では葬儀場の祭壇正面、両脇に設置されることが多く、西日本では祭壇の両脇ではなく、葬儀場の左右の壁面を沿って前から後ろへ設置されます。
盛籠は葬儀場の祭壇付近、両脇に設置されます。
そのため、西日本では生花は壁面、盛籠は祭壇と同じく正面と見える位置が異なります。
正面にある盛籠のほうが生花に比べて目立つと言えるでしょう。
生花と盛籠は誰が供えるものなのかを解説させていただきます。
生花は主にご親族、そしてご遺族の勤め先の会社関係、通われている学校関係、友人、知人などが出されます。
家族葬が主流の最近では、参列できない代わりに生花を出す方法を取ることもあります。
ただし、ご注文の際はご遺族が生花をお断りされている場合もありますので、事前に確認する必要があります。
盛籠は主にご親族が供えることが多いです。一般の方が供えても構わないのですが、先述したように祭壇正面に設置されるため、会場で着席していると自然と誰の目にも入ります。
目立たず控え目でいう場合は、生花のほうがよいでしょう。一般の方には生花をおすすめします。
また、生花と同様にご遺族がお断りされている場合がありますので、注文の際は事前に確認が必要です。
直接遺族に尋ねるか、もしくは葬儀社へ尋ねてみましょう。
生花の値段相場と種類は下記になります。
生花は数種類から選べる形をとっていることが多く、価格帯としては1基10,000円〜25,000円となります。
左右に1本ずつ「対」で供えたい場合は「1対」となります。
1対の場合、生花が2基になりますので、料金は1基に比べて2倍となります。
価格帯は20,000円〜50,000円となります。
白菊主体の生花と洋花主体の生花があります。
一般的に白菊主体の生花が安価で洋花主体の生花が高価格帯になっています。
ご注文の際は、イメージと実物が違うとならないように花の種類を伺ってみることをおすすめします。
1基か1対で迷う場合は、葬儀社へ尋ねてみましょう。
例えば広島は1対が多い地域なのですが、このように1基が多い地域、1対が多い地域と地域によって慣習が異なります。
悪目立ちは困る、控え目でいたい方は、その地域の慣習をよく知る葬儀社へ聞くのが一番です。
また、金額で迷われる方は下記の記事をご覧ください。
平均すると20,000〜25,000円が相場になります。
会社関係の方であればこの範囲で充分です。
相場以上の価格帯を選ばれるのは、主にご親族の方になります。
次に盛籠を見てみましょう。
盛籠も数種類から選べることが多く1籠10,000円〜20,000円で販売されています。
中身のボリュームや使用する商品によって価格が異なります。
盛籠によく使われるのは、果物、缶詰、お菓子、乾物などがあります。
いずれも生花に比べて日もちがするため、葬儀後に親族で分けて持って帰ることも可能です。
値段の相場は10000円〜12000円になります。
左右に対で設置したい場合は、2籠分の代金が必要となります。
このように供花物の生花と盛籠には同じお供えものでも、若干用途の違いが見られ、送る方の違いもありますので、ご注文の際はしっかり吟味されて送りましょう。
以前ほど葬儀に見栄を張る時代ではなくなったため、供花物を出さないと礼を欠く、恥ずかしいなどは考える必要はありません。
生前にお世話になったから、お花でいっぱいにしてあげたいからと各自がお気持ちで行うものに変化したと言えます。
なお、生花を送る方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
ご相談は無料
24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも
フリーダイヤルへご連絡ください。
「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は
メールでのご相談も可能です。
ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
