ご依頼・ご相談の方はこちら
ご相談は無料
24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも
フリーダイヤルへご連絡ください。
「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は
メールでのご相談も可能です。
ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
終活はシニアのためのものと考えられがちですが、「いざというときのために行っておくもの」と考えれば、世代を問わず取り組むべきといっても過言ではありません。
ただ、シニアと若い世代とでは、内容の優先順位が変わってきます。
20代が終活で行うときのポイントを解説します。
終活とは、葬儀やお墓、相続などに関する自分の希望を明らかにし、希望を叶えるための準備を行う活動です。
よって、死が差し迫っているという実感のない若い世代には、関係のないことと感じるかもしれません。
しかし、終活が役立つのは亡くなるときだけではありません。
20代であっても、明日突然事故に遭い、自分で自分のことができなくなってしまう可能性はあります。
そんなときのためにさまざまな準備をしておくことは、自分のためにも、お世話をしてくれる家族などのためにもなるでしょう。
また、終活を行っている間は「もし、自分が突然亡くなったら」と絶えず考えます。
すると、後悔しないようにやってみたいこと、会っておきたい人、行っておきたい場所などが明確になってくるはずです。
今後をより良く生きるためにも、終活は役に立つのです。
健康な20代の方が、自分の死をしっかりイメージするのは難しいことです。
そこで「もし明日、事故に遭ったらどうしよう?」と考えてみましょう。多くの人がしなければならないのは、次のようなことです。
・家族への連絡
・職場への連絡
・入院の準備(着替えやスリッパ、コップなどの日用品)
・ペットを飼っている場合は、ペットの世話について誰かに指示
・入院に伴う費用の準備
・医療保険に入っている場合、保険金の請求
以上のようなことを、自分自身でできない状態になったら、どうしたらよいでしょうか。
亡くなる以外にも、意識が戻らないなどの状況により、サポートしてくれる家族や友人に必要なことを伝えられない事態は多々考えられます。
このことから、若く健康な人であっても、緊急連絡先のリストアップや保険証のありかを誰かに示しておかなければならないことが分かります。
また、ペットの世話については、日ごろから家族などと共有しておくのが大事なこともわかります。
「明日、事故に遭ったとき」のために必要な項目を書き入れるためには、エンディングノートが有効です。
エンディングノートとは、終末期の医療や介護、葬儀、お墓、相続などに関する自分の希望を書き入れ、喪主となる人に託しておくものです。
エンディングノートにはさまざまな種類があり、日々新しいものが書籍として発売されています。
よって書店に行けば手に取ることができますし、インターネット書店でのアクセスも可能です。
ただ、全てのエンディングノートが20代などの若い人向けであるとはいえないため、慎重に選ぶ必要があります。
ノートによっては、シニア向けに「年代別の思い出」など自分史に関するページが多く割かれていたり、相続に関する事項が充実していたりします。
しかし、20代が「年代別の思い出」に書き込めるのは、「10代」と「20代」の項目だけですし、親御さんがいれば、相続に関しても、さほど記載する内容はないはずです。
若い人向けのエンディングノートについては、以下の記事に詳しく紹介していますので、参考にしてください。

どんな世代であっても必要で、活取り組みやすい終活が、写真の整理です。
とくにデジタルネイティブである20代の方は、スマホにたくさんの写真が溜まっているのではないでしょうか。
「写真がたくさんあって、見たい画像にすぐアクセスできない」という悩みもあるかもしれません。
不要になった写真や画像を削除したり、よく閲覧する画像をお気に入りにしたり、フォルダ分けをしたり。
整理すればするほど、使い勝手が良くなります。
写真を整理する過程で、今までの人生を振り返ることができるでしょう。
「この人に、また会いたい」「またいつか、この場所に行ってみたい」という気持ちが生じたら、「やりたいことリスト」を作って書き留めておくと、後悔しない人生につながります。
なお、自分が写っている写真の中で、特別気に入ったものがあれば、遺影用としてデータを別にとっておくのもおすすめです。
20代といえば、学生から大人になる節目の世代です。
シニアの終活では、老い支度のため生前整理を行いますが、20代の終活においては、学生から大人になるために持ち物を整理しましょう。
とくに、引っ越しを経験せず実家暮らしのままという人は、自分の部屋に幼少時代からのものがたくさん溜まっているのではないでしょうか。
子ども向けのコミック、お人形やぬいぐるみ、集めていたシールや消しゴム、学習ノートや教科書……いつか自分の子どもに譲りたいと感じるもの以外は手放し、子ども時代を卒業するのはいかがでしょう。
もちろん「まだ手元に置いておきたい」と感じるものがあれば、さよならできる時期が来るまで部屋に置いても構いません。
ただ、いつの日か、手放せない思い出の品が部屋を圧迫することになるかもしれません。
そんなとき思い切ってさよならできるよう、思い出の品は一つにまとめておきましょう。
このとき避けたいのが、思い出の品をまとめて「実家の、自室ではない部屋に置く」あるいは「実家に送る」という行為です。
自分のものがどんどん実家に溜まってしまうと、親御さんの暮らしを圧迫する原因になります。
シニアになってから、ものが多い中で暮らすのは大変です。自分の持ち物は、責任を持って自室で管理しましょう。
エンディングノートを書き、写真や部屋の整理を終えたら、「今後、どう生きていくか」を改めて考えてみましょう。
終活をする前よりも、後の方が、やりたいことがハッキリしているはずです。
すると、希望を叶えるためにやるべきことが見えてきます。
「転職して新しいことにチャレンジしたい」という目標ができたら、一刻も早く新しい業界の勉強をしたり、転職活動をしたりするべきでしょう。
「子だくさんの家庭で賑やかに過ごしたい」という希望ができたら、結婚をしていない人は、同じ家庭のイメージを共有できるパートナーを探し始めなければなりません。
思い切った変化を望んでいない人であっても、終活によって生じた「やりたいことリスト」をクリアするために計画を練れば、きっと今後の人生にワクワクすることが増えるでしょう。
終活は、「明日、もしものことがあったとき」のための活動であるうえに、今後よりよく生きるための行動を促す役割を持ちます。
よって、20代から始めるのも、決して不自然なことではありません。
人生の質を良いものにするため、人生の棚卸しを経験してみましょう。
なお、「本当は親や祖父母に終活してもらいたい」と考えている人にとっても、自身の終活を進めるのがおすすめです。
終活をしていることを、ぜひ親御さんにも伝えましょう。
きっと、終活に興味を持ってもらえます。
親御さんやおじいさま、おばあさまとともに終活を進めたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
お葬式で祭壇中央に飾られるご遺影。
お葬式が終わると納骨までの間は、自宅の仏間に後飾り壇を設置してもらい、そこにご遺骨とお写真を並べておくという方は多いと思います。
では納骨が終わると遺影はどこに置いたらいい?
この記事では、遺影の保管方法にお悩みの方へアドバイスさせていただきます。
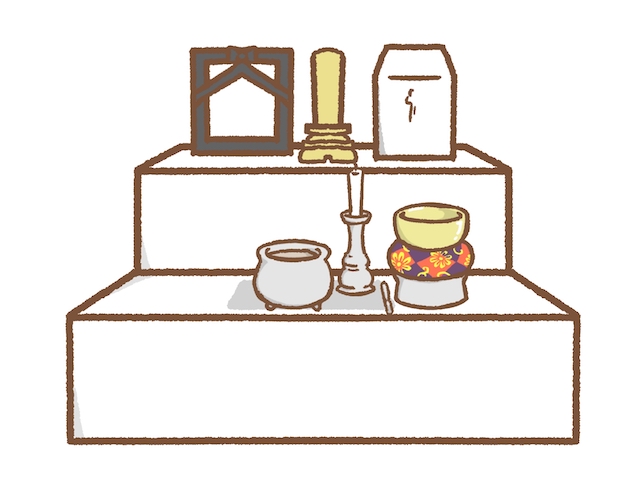
お葬式前に遺影の置き場所でお悩みになる方はあまりいらっしゃいません。
お葬式の前であれば、遺影の置き場所よりも臨終を迎えた時にどうするか、お葬式をどのように行うのか、これらに意識がいくのが自然です。
お葬式が終われば葬儀社が自宅に後飾りをしてくれますので、ここでも遺影の置き場所に悩むことはないでしょう。
遺影の置き場所に悩む方の多くは、納骨が終わり、これまで遺影を置いていた後飾り壇が不要になる、後飾り壇を撤去する前後になるでしょう。
これまで後飾り壇に置いていた遺影をこれからどこへ置くべきか。このような保管方法にお悩みになる方には共通した理由があります。
お葬式で使用した後は自宅で遺影は保管となりますが、四十九日など法事の場でも活用されるものでした。
現代も基本的に変わっていませんが、従来よりも四十九日などの法要を行う方が減少傾向にあり、法事を行ったとしても家族だけで簡単に済ませるという方が多くなりました。
そのため、お葬式以外でも活用されることがあった遺影が、お葬式でしか活用される機会がない存在へ変わる方もいらっしゃるのです。
遺影写真は、宗教的に葬儀において必ず必要なものではありません。
遺影はお葬式の会場、祭壇中央に飾られる写真として活用されている光景を思い浮かべる方も多いでしょう。
会場の後ろの席からLサイズの写真を見た場合、Lサイズでは写真が小さすぎて全く認識できません。
そのため、会場の後方でも認識できるように少し大きな写真を用意するようになったのが始まりです。
現在ほとんどの場合、四つ切りサイズが用意されています。
但し、100名以上参列するようなお葬式の場合、四つ切りサイズでも小さいため、さらに大きな電照写真が用意されることもあります。
つまり遺影は、葬儀会場の大きさに合わせて作られたものなのです。
自宅に持ち帰ると大きいと感じて、保管場所に悩む方がいらっしゃるのも無理はありません。
遺影は、お葬式後は遺骨と一緒に後飾り壇へ設置する慣習に倣い、納骨が終わって後飾り壇が不要になれば、仏間にご先祖様の遺影と一緒に飾るというのがごく自然に行われ、従来は流れに身を任せるだけでよかった時代もありました。
子が親の家を継ぎ、家の仏間には先祖代々の遺影が掲げられていました。
あなたの実家でもご先祖の遺影が隣同士に並べてある光景が今もあるかもしれません。
しかし現代では、それぞれが独立した形で生活していることが多く、実家を離れて家を持つ方も多くいらっしゃいます。
新しい新居にご先祖の遺影が仏間に隣同士に並べてことは少なく、仏壇のある仏間自体がないという方も多いでしょう。
遺影の保管場所にお悩みになる方の多くがこのケースです。
ではどのように保管すると良いのか、いくつか方法をアドバイスさせていただきます。
一つ目は、遺影を一回り小さくコンパクトなサイズにして家の中に飾るというものです。
大きいと置き場所に困るものも、小さくすればリビング、テレビ台に置くなど選択肢は増えます。
カメラのキタムラに持参すれば数千円で行ってくれるはずです。
遺影を額から取り出して写真だけをアルバムに収めるという方法もあります。
アルバムに収めれば写真に傷がつきにくく、本棚に収めることも容易です。
収納という面では選択肢がかなり広がるでしょう。
遺影をそのまま箱に収めて保管するという形もあります。
ジャストサイズな箱が見つからない場合は、緩衝材を入れて、額面が割れない工夫をすると良いでしょう。
箱に収容すれば、押し入れやクローゼットなど大切なものを保管している場所に一緒に収めるということも可能になります。
お葬式で作ってもらった遺影は、黒い額に入っていることが多いと思います。
この先ずっと家の中に飾るならお葬式を連想させる黒い額よりも、もっと華やかな額や家に溶けこむ自然な額が良いでしょう。
新たに額を購入して飾るだけでも雰囲気が大きく変わるはずです。
遺影は故人の生前の面影を残すものとして自分達だけでなく、次の世代へも影響を与えるものです。
ご先祖がどんな方だったのか、孫のその次の世代へと引き継がれる場合、生前を知る手がかりの一つになりますので大切にしたいものです。
とはいえ、お葬式が終わった後にそんなことを考えるよりも、日常生活を送る上で置き場所に困る問題を解決する方が先決となるのもよくわかります。
個人的にはご家族の思い出のアルバムを保管してある場所に一緒に置いておくのがおすすめです。
自然といつまでも大切に保管できますし、思い出を振り返る時にいつも忘れずに遺影も登場してくるでしょう。
日常生活の中で故人の存在をそばで感じることのできる空間を作るのも良いと思います。
一人でお墓に入るよりも、常に家族のそばにいたいという方であれば、なおさらです。
置き場所に決まりはなく、ご家族の自由です。
ご家族でどこに保管するのが良いか、一度話し合ってみましょう。
付き合いのある菩提寺が県外にある、遠方にある方は、葬儀になった時にお勤めは誰に頼んだらよいのだろうか。
仕事や学業の関係で地元を離れ、他県で暮らす方が多い昨今、このような疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。
この場合、正しい手順を取っていくことが何より大切になりますので、わかりやすく一つ一つ解説させていただきます。
「菩提寺が遠い」、「お寺が県外にある」からどうしようと思うのは、依頼する側の思い込みに過ぎない場合もあります。
菩提寺が遠方にある方の葬儀は、葬儀社にいれば、よくある事の一つです。
例えば、弊社は広島の葬儀社ですが、福岡、大阪からでもご家族様が連絡すると普通にお寺様がお勤めに来られています。
福岡から広島までは、お寺様にとって「遠い」にはならない印象です。
お寺で別の行事があるなどで、お寺を留守にするリスクなどを勘案して、お参りは難しいとなる場合もありますが、遠いから難しいとなる場合は稀です。
このようなことから、遠方でもお寺によっては普通にお参りに来てくださるという認識を持っていただき、菩提寺に対してご家族が勝手な判断をしてしまわないように注意しましょう。
菩提寺に対して勝手な判断をしてしまって、非礼になってしまわないために守るべき注意点を解説させていただきます。
菩提寺から「勝手に決めないで欲しかった」「一言相談して欲しかった」などと言われないために、順番を間違えないことが大切です。まずは菩提寺に相談してみるのが先決です。
たとえ疎遠な間柄であっても、これまでご先祖が長年お付き合いしていたお寺ですから、立てることは大切です。
葬儀社にとって、地元の近くのお寺をご紹介することは容易です。
しかしこれは最終手段です。
お寺が遠いので、葬儀社から近くのお寺を紹介してもらおうと菩提寺抜きで家族と葬儀社とで話がまとまるのはあまりよくありません。
葬儀社からの紹介という方法を取る場合は、菩提寺の了解のもと行うことが後のトラブルを防ぐための正しい手順です。
では次項で正しい手順を順番に見ていきましょう。
まず菩提寺がどんなに遠くても連絡をしてみることです。
本当に遠いのか、それとも遠いうちに入らないのかは、先方が答えを持っています。
ご逝去してから連絡をするよりも、前もって相談しておくことがおすすめです。
お寺様も近いうちにそういうことが起こるかもしれないと心の準備をしておくことができます。
この連絡で「葬儀の際は、お勤めに参ります」とお返事をいただければ、ここでお悩みは解決です。
いざというときは、ご連絡をすれば来てくださるでしょう。
交通費を一般的な相場よりも増やしておきましょう。
往復のガソリン代+高速道路代、あるいは新幹線代を目安にして考えてみると良いでしょう。
万が一のときは、通夜式が終わると、お寺様は一旦帰宅して翌日再び翌日来られるというのは考えづらく、宿泊先を手配しておいた方が良いかもしれません。
どのようにお考えかを確認しておきましょう。
宿泊先の手配に関しては、葬儀社に相談すると全て段取りしてもらえるはずです。
手順1で遠方の菩提寺へ連絡するも、菩提寺が直接お参りへ行くのは難しいとお返事があった場合は、菩提寺から代わりのお寺を紹介していただきましょう。
お寺同士の横の繋がりは広く、あなたの県にも縁のあるお寺があるかもしれません。
もしご紹介していただけるとなった場合は、実際に足を運んでお参りに来てくださるのは、菩提寺から紹介を受けたお寺様となります。
この場合、戒名は菩提寺から授かります。
菩提寺が戒名をつけて、お勤めされるお寺様がそれを位牌に記します。
葬儀のお布施はお勤めいただいたお寺へ、戒名料は菩提寺へとなります。
菩提寺が直接お参りは難しい、代わりのお寺をご紹介することも難しい。
このようになって初めて葬儀社から近くの寺を紹介という選択肢が登場します。
菩提寺の困り事を解決する手段になるため、非礼にはなりません。
菩提寺の了解のもと、葬儀社からお寺をご紹介します。
この場合も先ほど同様に戒名は菩提寺が授けてくださいます。
菩提寺が記した戒名を葬儀社へFAX、届いた用紙をお勤めするお寺へ渡し、位牌に戒名を記してもらう流れです。
お布施は葬儀社が紹介したお寺へ、戒名料は菩提寺へとなります。
これまで解説させていただいたのは、菩提寺が遠方にある時、菩提寺にカドが立つことなく、葬儀の読経を誰に行っていただくかを解決する方法と言えます。
しかし納骨のこと、自分達世代だけでなく、子供・孫世代のことまで考えると、今後遠方の菩提寺との関係を継続するべきなのか、悩みは尽きないという方もいらっしゃるでしょう。
この場合についての注意点をこれからはアドバイスさせていただきます。
現在、菩提寺が遠方にあるということは、実家や故郷にお付き合いのあるお寺があるという
ことだと思います。
ご両親、祖父母様など家族の万が一の時にお勤めいただくお寺を考えるならば、ご本人にとってどちらが良いかという視点も大切にしたいものです。
縁もゆかりもないお寺にお願いするよりも、その菩提寺にお勤めいただくほうがご本人にとっては良い場合も考えられます。
現在は一代で居住地が変わり、それぞれが独立した人生を歩む時代と言えます。
先祖が付き合い始めたお寺と未来永劫付き合いを継続するのは無理が生じます。
それぞれの人生の中でお寺が変わるのは致し方ないことでしょう。
ですからお寺を変えるという選択肢が生まれるのは自然なことで、罪悪感を感じる必要はありません。
しかし勝手にお寺を変えるのではなく、お気持ちそのままを現在の菩提寺に相談してみるのが良いと思います。
お寺を変えるという考えになった場合、一番やってはいけないのは葬儀社に紹介されたお寺とずっとその先も付き合いを継続するというものです。
葬儀社から紹介を受けた場合、そのお寺は葬儀を滞りなく行うための応急処置的な位置付けと言えます。
葬儀を通じて、好印象を抱いたならそのまま継続してお付き合いをお願いしても構いません。
そうでない場合は、一旦葬儀だけのお付き合いとし、今後ゆっくりお寺を決めていく方が良いでしょう。
お寺の行事に参加してみたり、評判を聞いて訪ねてみたり、ご自身の目で確かめることが大切です。
子供世代の将来を考えた時、子供世代にも人生があります。
将来は同じ地域に住んでいない可能性も十分あります。
そのようなまだわからないことに対していくら考えても最良の答えは見つかりませんし、何が最良だったかの答えがわかるのは、数十年先のことになります。
それも結果論となるでしょう。
それよりも自分達で解決できる問題、自分達世代までのことを解決していくという考えで取り組んだ方が無難です。
お寺様とのお付き合いは、ただお経をあげていただくだけの関係性ではありません。
お寺様の話されるご法話や何気ない会話の中でもご家族様のお悲しみが癒されたり、供養に対しての気持ちで元気をもらったり、不安な気持ちが和んだり、助けてくれる存在です。
日本のお葬式の多くはお寺による読経が行われていますが、グリーフワークの観点からもとても理に適うもので、多くのご遺族様がお葬式を通じてお寺様に精神的に支えていただいています。
人付き合いが気薄な世の中になっていますが、今あるご縁、せっかくいただいたご縁は大切にしたいものです。
法事の香典はいくら包むべきかお悩みの方も多いと思います。
インターネットで検索するとある程度の相場は把握できますが、なぜそれが相場なのか説明不足な場合が多く、私は不十分だと思っています。
「なるほど、そういうことか」とスッキリしていただくことを目的として、法事の香典について、わかりやすく解説させていただきます。
法事で香典をいくら包むのか。
金額を確認する前に、そもそも法事で香典の準備が必要なのかを確認しましょう。
確認方法としては、一般的に法事の場合、事前に案内状が自宅へ届きます。
案内文に香典に関する記載が何もなければ、香典を辞退する意向はないという事になります。
また、電話やメールで案内がある場合、香典を辞退であれば、「香典を用意する必要がない」と施主側から一言あるはずです。
なければ、通常通り香典を用意しておくのが無難です。
葬儀で香典を辞退されたケースでは、法事も同様に辞退する場合が多いのでよく確認してみましょう。
法事の香典は、結婚式の祝儀に近いものがあります。
結婚式は、事前に案内状が届き、参加者は当日祝儀を用意します。
会場で食事をいただき、帰りに引き出物をいただいて帰宅します。
法事の場合も事前に案内状が届き、参加者は当日香典を用意します。
会場で食事をいただき、帰りに引き物をいただき帰宅します。
まとめると下記の通りです。
| 結婚式 | 法事 | |
| 案内状 | 事前に送付 | 事前に送付 |
| 参加者 | 祝儀を用意 | 香典を用意 |
| 施主 | 食事を振る舞う | 食事を振る舞う |
| 施主 | 引き出物を用意 | 引き物を用意 |
このように法事と結婚式はとても似ているところがあります。
双方、「頂いたら、頂いた分だけ礼を返す」という日本人特有の文化からきています。
頂いただけで済ませることは、なかなか出来ないのが日本人。
礼には礼を尽くすのがマナーとされています。
法事で施主から食事の振る舞いを受け、帰りに引き物をいただいて帰宅することになった時、香典を持参せずに手ぶらで参加すれば、相手に申し訳ない気分になるものです。
そのため、予め法事でも香典を用意するのです。
葬儀の香典は、遺族の葬儀代の金銭的負担を軽減する意味合いがありましたが、法事の香典は、施主が法事の食事や引き物へかかる金銭的負担を軽減するために参加者が用意する意味合いがあります。
わかりやすく結婚式を例に出すと、皆さん結婚式へ出席する際は、3万円の祝儀を用意されると思います。
会場で1万円〜1万5千円のお料理をいただき、帰りに1万円程度の引き出物をいただいて帰ることが多く、施主側からすると手元に5千円〜1万円残るのが一般的です。
法事の場合も同様な考え方になります。
法事へ参加する方は1万円の香典を用意し、法宴で4千円〜6千円のお料理をいただき、帰りに3千円前後の引き物をいただいて帰宅します。
施主の手元に残るのは1千円〜3千円が一般的です。
施主側からすると、参加者から1万円をいただいても、料理と引き物で殆どが消えてなくなることはよくあることです。
言い換えると、法事で食事の席があるとわかっている場合、1万円は包んでいった方が良いと言えます。
| 結婚式 | 法事 |
| 祝儀¥30,000 | 香典¥10,000 |
| 料理¥10,000~¥15,000 | 料理¥4,000~¥6,000 |
| 引き出物¥10,000 | 引き物¥3,000 |
| 残り¥5,000~¥10,000 | 残り¥1,000~¥3,000 |
では次項で香典の金額相場について解説させていただきます。
法事の香典金額相場は、1万円ですと言いたいところですが、これだけでは不十分。
正確に言えば、法事の内容、お一人で参加するのか、夫婦や家族で参加するのかで決まります。
状況別に目安を記載しますので、下記を参考にしてみてください。
| 目安 | 一人 | 夫婦 | 夫婦+子供1名 |
| 法事(食事なし) | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 法事(食事あり) | ¥10,000 | ¥15,000〜¥20,000 | ¥20,000〜¥25,000 |
食事がない場合、参加人数分の食事代を考慮する必要がありません。
香典は本来、世帯に一つ用意するものなので一人でも夫婦でも香典は一つ。
金額も変わりません。
参加人数分の食事を用意いただいているはずですから、包む金額にも食事代を考慮する必要があります。
一人1万円が相場です。
夫婦の場合、食事は2名分用意されますが、引き物は世帯に一つ用意されます。
そのため香典を単純に2倍にする必要はなく、施主側に負担がかからない程度に2名分の料理代を考慮すれば良いでしょう。
引き物は世帯に一つ用意されるものなので、お一人で参加しても夫婦で参加しても帰りにいただく引き物は一つです。
このようなことから単純に2倍にする必要はありません。
お子様も加えて家族で参加する場合も同様です。
単純に倍にするのではなく、食事代を考慮してお子様一人につき5千円増額するのを目安に考えていきましょう。
これまでの説明で法事の香典とは、施主側の負担が重くならないように、赤字にならないように配慮して包めば良いということがご理解いただけたと思います。
食事ありの場合、相場は1万円、食事なしの場合は相場が5千円とご案内させていただきましたが、これはあなたが非礼にならないためにこれだけは守っておきたいという金額でした。
ここからはあなたと施主の関係性、あなたの気持ちで相場以上に上乗せするかどうかを決めてください。
よくインターネット上には法事の香典目安として1万円〜3万円などと載っています。
これは「相場は1万円。あとは上限2万円を目安に上乗せするかどうかお気持ち次第です」という解釈をしていただけるとわかりやすいと思います。
決して宗派や地域性などではなく、それよりもお気持ちの部分が大きいです。
例えば、「父が亡くなって、母もこれから一人で大変だろう。自分は長男、香典は1万円でもいいけど母が心配だから3万円にしておこう」
「もうすぐ叔母さんの四十九日、自分が小さい頃は毎年お年玉いただいていたから、しっかり返しておこう。1万円ではなく3万円にしよう。」
このように相場を目安としてそれ以上に包むかどうか、お決めになっていただけたらと思います。
誤った解釈をしていただきたくないのですが、相場に上乗せしないと気持ちが無いということではありません。
基本的に相場の金額で十分です。
これでは少ないのでは?と感じる方が多く包むものです。
法事の香典は、前もって参加予定の親族同士で相談し合い、金額を合わせるということもあります。
ご兄弟でAさんが1万円、Bさんが5万円だったと後日わかった場合、1万円だった方は「知らせてくれればよかったのに」とあまり良い気持ちにならないこともあります。
幸い法事というものは前もっての準備期間がありますので、お互いの考えを擦り合わせる時間は十分あります。
突然法事を迎えるよりも、前もって相談し合って当日を迎える方が滞りなく終えられる確率は高まります。
施主から当日の内容を伺い、施主を交えて話を行うのも全く失礼ではありません。
当日をお互いが気持ちよく過ごせるように準備をしましょう。
なお、香典の書き方については下記の記事で詳しく紹介していますので、よかったら合わせてご覧ください。
法事に出席するとき、香典の書き方に迷う人は多いと思われます。
「御霊前」「御仏前」など表書きの書き方をはじめ、「名前はどう書けば良い?」「住所を書くべき?書かなくても良い?」といった疑問まで、たった一枚の袋に文字を書くだけなのに、たくさんの悩みが出てくることでしょう。
この記事では、法事における香典の書き方をわかりやすく解説します。
法事の香典袋には、以下の4つを書き入れます。
■表書き
袋の表側、上半分に「御霊前」「御仏前」といった文字を書きます。
表書きは、香典が何のためのお金かを示すもので、宗派によって書き方が違います。
■名前
表書きの下側に、香典を包む人の名前を書きます。
■住所氏名
香典袋の裏側か、中袋の裏側に、住所氏名を書き入れます。
■金額
香典袋の裏側か、中袋の裏側に、金額を書き入れます。
それぞれマナーがありますので、わかりやすく解説します。
法事の香典袋は、宗派によって種類が違います。スーパーやコンビニ、文具店、大型商業施設の文具コーナーなどで手に入れましょう。
白黒、あるいは双銀の水引があしらわれているか、プリントされている香典袋を選びます。
蓮の花が描かれているものか、無地が仏式用です。
白黒、あるいは双銀の水引があしらわれているか、プリントされている香典袋を選びます。
必ず無地を選びましょう。
蓮の花が描かれているものは、仏式用なので避けます。
水引がない無地の香典袋を選びます。
お店によっては、十字架があしらわれた香典袋を販売しているところもあります。これもキリスト教用です。
白黒、あるいは双銀の水引があしらわれているか、プリントされている香典袋を選びます。
何も描かれていない無地のものが良いでしょう。
なお、関西や北陸の一部では、法要での水引を「黒と白」ではなく、「黄色と白」とするところがあります。
香典袋を選びに立ち寄った文具店などで「黄色と白」の水引を使った香典袋が売られていたら、その地域の法事では「黄色と白」を使う可能性が高いといえます。
親族の年長者などに確認してから購入するのが無難です。
筆記具は、筆ペンがふさわしいとされます。
お葬式では薄墨がよく使われますが、法事では濃い墨の一般的な筆ペンを使うのがマナーです。

法事の香典袋には上側に、表書きを縦書きしましょう。
宗教・宗派によって文字が違うため、注意が必要です。
四十九日法要までは「御霊前」、四十九日法要からは「御仏前」と書きます。
四十九日までは「死者の魂は、亡くなってから四十九日の間、霊としてさまよっている」とされているため御霊前、それ以降は仏様になられているので御仏前となります。
「御仏前」とします。日本の仏教の中で、浄土真宗だけは「亡くなったら、死者の魂はすぐ仏となる」とされているためです。
葬儀の場でも、浄土真宗だけは「御仏前」となります。
「御玉串料」あるいは「御榊料」とします。
玉串とは、神式の儀式中に捧げる、榊(さかき)の枝に紙垂(しで。白く長細い紙で、しめ縄などにも使われる)をつけたものです。
「御花料」と書きます。
「御香典」と書けば、何のためのお金かがとりあえず相手には伝わるので無難です。
表書きの下には、香典を出す人の名前を縦書きで書き入れます。
出席者には親族が多いため、「○○家」ではどの家からの香典かが判別できません。
必ず世帯主の氏名を書きましょう。
夫婦連名にしたいなら、1つだけ名字を書き、その下に2つ名前を並べましょう。
男性の名前を右側、女性を左側に書き入れるのが一般的です。
また、有志が連名で香典を送る場合は、袋の右側を上位としてそれぞれの名前を書き入れます。立場が同列なら、50音順に書きましょう。
施主が後でお返しものを送るとき便利なように、住所氏名を書き入れます。
「近しい親戚だから、住所くらい分かるだろう」と省略する人もいますが、次に不幸が起こったとき、次世代が前回の法事の資料を参考に連絡を取ることもあります。
必ず書きましょう。
香典袋に金額を書き入れる欄が設けられている場合は、そこへ金額を書きましょう。
書き込み欄がないなら、中袋の裏面の左下に書きます。
中袋がない場合は、香典袋の裏面の左下に書きます。
金額は、「一」「二」「三」を使わず、「壱」「弐」「参」を使うのが従来のマナーでした。
これは改ざんを防ぐためと言われています。
また、「万」より「萬」、「円」より「圓」を使うのが丁寧とされます。
「一万円」であれば、「壱萬圓」と書きます。
しかし近年、壱、弐、参などの漢字は、日常生活で使うことはほぼなくなりました。
このため法事でも普通に一万円と書く方が年々増えています。
法事も葬儀同様に身内で少人数という形が増え、改ざんを防ぐという主旨は適さない面もあります。
相手にわかりやすい記載は心遣いの一つですし、普通に一、二、三と記載しても構いません。
香典を入れたら、香典袋を元のように包みましょう。
最後、袋を折りたたむときは、下側の短い折り返しに、長い上側の折り返しをかぶせるようにします。
これには、「顔を下向きにする」や、「涙を流す」といった意味が込められており、弔時特有の包み方とされます。
一方、お祝いの場合には、ご祝儀袋の上側の折り返しに、下側をかぶせるように包みます。
「顔を上向きにして、喜びを表現する」「(運や人生などが)上向きになる」という意味が込められています。
覚えておくと便利です。
香典袋は、裸で持参するのではなく、法事でも袱紗に包んで持参するのがマナーです。
袱紗とは、香典袋を包む小型の風呂敷を指します。
風呂敷型だけでなく、布バッグの形をした袱紗もあります。
最近は、クラッチのような形をした布バッグ型の袱紗が多く売られているため、包み方に迷うことはあまりないでしょう。
ただし、弔事の場合は、右手に袱紗を置き、左手で開くようにします。いわゆる「左開き」です。
反対の「右開き」は、慶事での開き方なので、香典袋の向きに気をつけて包みましょう。
風呂敷型の袱紗であっても、開いたときの形は同じです。
まず、袱紗を裏向きにして、菱形になるように置きます。
その後、袱紗の中心よりもやや右寄りに、香典袋を置きます。
そして、「右→下→上→左」の順に、袱紗の端をたたんで香典袋を包みましょう。
すると、右手に袱紗を置き、左手で開く「左開き」の包み方が完成します。
法事の席には、通夜や葬儀のときのような受付はありません。
このため、「いつ香典を出せば良いのか」と迷う人は多いでしょう。
法事の際、香典は施主に渡しましょう。
法事に到着したら施主に挨拶をし、その場で香典を渡します。
もしかしたら、焼香場所に置かれているお盆に香典を置くよう促されるかもしれません。
その際は、焼香場所まで進んで一礼し、黒いお盆に香典を置いてから、焼香を済ませます。
香典を手渡しするときは、直前まで袱紗に香典を包んでおきます。
施主の目の前で袱紗から香典を外し、渡すようにしましょう。
「水引は、黒白?黄白?」など、しきたりで分からないことがあれば、事前に施主へ連絡して尋ねるのがいいでしょう。
葬儀の場では「忙しい喪主に、あれこれ尋ねてはならない」とするマナーが確立されていますが、招待から開催まで日数の開く法事については、その限りではありません。
むしろ、気兼ねして他の親族に尋ねるよりも、施主にきちんと尋ねた方が、間違いがなく安心です。
四十九日や一周忌など、葬儀を終えたあとも定期的に家族が集まって法事を営み、故人様を供養します。そんな法事に対して…
「一体どうして法事をするの?」
「法事は何回忌まですればいいの?」
「親戚の人をいつまで呼べばいいの?」
などの疑問を抱く方も少なくないのでは?
この記事では、法事をどうして行うのか、その本質的な意味や、期間や呼ぶべき親族の範囲などについて詳しく解説いたします。
法事とは冠婚葬祭の儀式のうちの一つで、家族や血縁が集まって故人や先祖の供養をします。冠婚葬祭の「祭」は先祖祭祀の意味を表し、先祖となった亡き人とのつながりの場として、古代の日本や中国でも見られる古くから続く風習です。
法事では主に次のことをします。
●家族や親族の再会
●僧侶による読経と参列者の焼香
●お斎(法事後の会食)
では、なぜこうした儀式を執り行うのか。次の章では、そのことについてさらに深くお伝えしてまいります。
一体どうして法事を行うのでしょうか。法事を定期的に行うのは、主に次の3つの意味があると考えられます。
●グリーフケア
●つながりの再確認
●自分自身を見つめ直す時間
それでは、順番に見ていきましょう。
グリーフとは、大切な人を失ってしまった方が抱える死別の悲しみのことです。
この悲しみをケアする取り組みがグリーフケアです。
通夜や葬儀が癒えるからといって、大切な人を失った悲しみがすぐに和らぐわけではありません。
むしろ、葬儀を終えたあとの長い日常の中で、大切な方の不在を実感し、落ち込んでしまうという人も少なくありません。
死別を受け入れるには、長い長い時間が必要なのです。
法事はまさに、定期的に行われるグリーフケアの場と言えます。
ひとりで抱え込まずに、まわりの親戚や、供養の専門家である僧侶の力を借りることで、悲しみを和らげていけるのかもしれません。
法事を営むことで、普段会うことのない家族や親戚とも顔を合わせることができます。
法事はいわば、再会のきっかけともなる場です。
「元気にしてた?」「大きくなったね」「最近腰が悪くてねぇ」など、こうした近況報告を交わすことで、お互いの時間の経過を知ることができます。
つながりを感じあうことは私たちに幸福感や安心感をもたらします。
また、法事におけるつながりとは、家族や親戚だけのものではありません。
故人や先祖とのつながり、その媒介をしてくれるお寺や僧侶とのつながりをも意味します。
私たちはひとりじゃない。法事はそんなことを教えてくれる場でもあるのです。
普段、仕事や家事に忙しく立ち回る現代人。
目の前のことに追われて大切な何かを見失いがちです。
法事は、そんな自分自身と向き合う機会にもなります。
亡き人への供養を通じて、「自分はいまどうしてこんな生活をしているのだろう」「いつかは誰もが亡くなる。自分の生き方はこのままでいいのだろうか」などと、生きることや命について見つめ直すという声は、思いのほか多く聞かれます。
故人や先祖、家族や親戚、そして自分自身と向き合うために、法事という場が設けられているのです。
法事を定期的に執り行う意味はご理解いただけたと思いますが、では一体、いつまで行えばいいものなのでしょうか。
葬儀後の法事は主に、「追善法要」と「年忌法要」に分けられます。
それぞれ個別に解説して参ります。
追善法要とは、葬儀後、四十九日までの法事のことです。
亡き人は四十九日を経て成仏し、ご先祖様の仲間入りをすると言われており、死後きちんと成仏できるかどうかは、閻魔王の裁きによるとされています。
遺された家族たちは、「きちんと成仏できますように」と、故人に代わって法事を執り行い、善を積む(追善)のです。
追善法要は次のように営みます。
・初七日法要(死後7日目)
・二七日法要(死後14日目)
・三七日法要(死後21日目)
・四七日法要(死後28日目)
・五七日法要(死後35日目)
・六七日法要(死後42日目)
・七七日法要(死後49日目。四十九日法要)
初七日法要は、もともとは死後七日目に僧侶が自宅にお参りをするものでしたが、葬儀を終えて間もないことから、最近では葬儀当日にあわせて初七日のお勤めをするスタイルが全国的に採用されています。
二七日から六七日までは、毎週決まった曜日に僧侶が自宅の祭壇にお参りに来ますが、最近では省略するケースも少なくありません。
そして七七日法要(四十九日法要)は、故人が仏となる大切な法要です。
家族や親戚が再び一堂に集まり、故人を供養します。またこの日に合わせて、位牌や仏壇を用意し、香典返しの手配をします。
年忌法要とは、四十九日以降の法要のことです。次のように営みます。
・百箇日法要(死後100日目)
・一周忌法要(葬儀の翌年の命日)
・三回忌法要(葬儀の2年後の命日)
・七回忌法要(葬儀の6年後の命日)
・十三回忌法要(葬儀の12年後の命日)
・十七回忌法要(葬儀の16年後の命日)
・二十三回忌法要(葬儀の22年後の命日)
・二十七回忌法要(葬儀の26年後の命日)
・三十三回忌法要(葬儀の32年後の命日)
一周忌や三回忌は、葬儀を終えたばかりということもあり、きちんと親戚を招いて執り行うという人が多いようです。
また、このあたりくらいまでにお墓を用意する人も多く、その場合はあわせて納骨法要を営みます。
その後は、三十三回忌法要の「弔い上げ」まで、定期的に法事を執り行います。
地域によっては三十七回忌や五十回忌までするところもあるようです。
民俗学的には、その家の先祖から、村全体の氏神に昇華すると考えられています。
33年もの年月が経つと、故人様を弔い本人たちも高齢化し、グリーフも和らぎ、「次は自分たちの番だ」と言える時期です。
死者の個性はゆっくりとうすらぎ、徐々に古いご先祖様の中に溶け込んでいきます。
日本では、三十三回忌までの長い年月をかけて、死者やご先祖様を大事にしながら世代交代をしていくのです。
法事を営む際に悩みがちなのが、親戚にいつまで、どこまで声をかけるべきか、というもの。
「どこまでの人に来てもらえばいい?」
「今年で十三回忌になる。いつまで親戚たちに来てもらおうか」
「私たち家族だけで法事をしたら、失礼に当たらないだろうか」
このように悩んでしまうものです。
この記事では一つの目安を示したいと思います。これが決まりではないので、あくまでも参考にとどめておいていただくと幸いです。
親戚への声掛けに決まりはありません。
施主の想い、親戚との関係性などから、個別に判断するとしか言いようがないのが正直なところなのです。
声をかける親戚の範囲は、
・故人様の直系親族(親、子、孫、ひ孫)
・故人様の兄弟姉妹とその家族
このあたりまでではないでしょうか。
たとえば、故人の長男であるあなたが施主を務めるとします。
お父様の法事ですから、当然、あなたの家族(母、妻、子、兄弟)は法事に参列します。
そしてお父様と血を分けた兄弟姉妹(あなたのおじ、おば)に声掛けをするのも、何ら違和感はないでしょう。
その上で、この人たちがその家族(あなたのいとこ)を連れてくるかどうかは、状況によるでしょう。
そして、いつまで親戚を呼ぶかについてですが、さまざまなおうちの様子を見ていると、七回忌、あるいは十三回忌くらいまででひと段落されているように見えます。
十三回忌にもなると、故人様の兄弟姉妹も高齢化し、「無理に声をかけずに、あとは家族だけでやろう」という雰囲気になるようです。
もちろんどこまでの人を法事に招くかは、相手との関係性や、地域や親戚の中でのしきたりが優先されます。
あまり一般論に捉われずに、ご自身の考え、相手の想い、地域性やしきたりを重んじることをおすすめします。
いかがでしたでしょうか。
法事は故人や先祖の供養のため、その儀式を通じて、まわりの人たちとのつながりを感じ、自分自身を見つめ直す貴重な時間となるものです。
有意義な法事を過ごすことができるよう、もしも分からないことがありましたら、どうぞお気軽に広島自宅葬儀社にご相談下さい。
どんなささいなことでも構いません。
お客様の声に耳を傾け、親切丁寧に、アドバイスさせていただきます。
法事の服装は、喪服と決まっているわけではありません。
没後何年も経過していたり、かなりの暑さ、寒さが見込まれたりするときは、施主の判断により平服で行われることもあります。
なかには「喪服であるとしても、葬儀のときよりカジュアルではダメだろうか?」と、少しでもラフにしたいという方もいるでしょう。法事の服装について、詳しく解説します。
法事の服装は、喪服が基本です。
法事の案内に「平服でお越しください」など服装についての記述がなければ、喪服で参列するのがマナーとされます。
しかし、施主に「よりカジュアルにしたい」「参列者に、楽な格好で着てほしい」という意思があるのであれば、施主側が平服を指定しても構いません。
喪服から平服への切り替えのタイミングは、七回忌以降が良いとされています。
故人が亡くなってから年が浅い三回忌までは、平服ではなく喪服とするのが一般的です。
また、回忌に限らず、施主の判断で平服となることもあります。
夏、あまりの暑さが予想されるときや、厳寒地帯の冬に行われるときなどです。
非常に寒さを感じる場合、とくに女性の喪服は中に何かを着込むのが難しいため「喪服に限らず、温かい格好で」と案内されることもあるのです。
施主から平服の指定がない場合は、以下のような服装で法事に出かけましょう。
葬儀のときに着用する、ブラックフォーマルが基本です。
光沢のない黒いスーツに白いワイシャツを合わせ、黒ネクタイ、黒いベルトを着用します。
20代など、まだ喪服を揃えるには若いとされる年齢の場合は、黒いビジネススーツでも構いません。
また、ワイシャツは長袖が基本ですが、真夏は半袖でも良いとされます。
靴や靴下などの小物も、黒の無地で揃えます。
葬儀のときに着用する、ブラックフォーマルが基本です。
黒いワンピースに黒ジャケットを着用し、ストッキングも黒とします。
ただし、20代など手持ちの喪服がない若年層は、黒いビジネススーツでも構いません。
スカートのスーツに、白いワイシャツを着用しましょう。
パンツスーツしかない場合は、パンツスタイルでもやむを得ません。
髪留めや靴などの小物も黒無地で、アクセサリーは、結婚指輪の他は一連のパールネックレスとイヤリングだけが許されています。
パールの色は、白もしくは紫、黒です。
子どもは、制服を着用します。
制服がない場合は、黒やグレーなど、地味めの色を選んで着せましょう。
男の子ならジャケットに白いワイシャツ、女の子ならワンピースにボレロなど、大人の喪服に服装を寄せるのが理想的ですが、手持ちにおしゃれ着がない場合は、持っているワードローブの中で工夫しても構いません。
ただし、服、靴ともにキャラクターものやキラキラ光る装飾などは控えます。
音の鳴る靴も避けましょう。
平服と指定されたときは、喪服を着用してはいけません。
また、ジーンズやTシャツ姿といったラフな服装でもいけません。
法事のときの平服は、一言で表せば「地味な色味のお出かけ着」です。
ブラックフォーマルではない、黒や紺、グレー、ブラウンなど暗めの色味のスーツを着用します。
スーツには、ストライプなどの柄が入っていないものがよりふさわしいとされます。
スーツの中は長袖か半袖の白いワイシャツで、これも地紋などが入っていないシンプルなものを選びましょう。
ネクタイはグレーや紺などの無地を選び、ベルト、靴下、靴は黒が望ましいですが、手持ちになければ黒以外の暗い色でも構いません。
結論として、男性の平服はビジネスシーンで着用しているスーツ姿で間に合います。
ただ、長くクリーニングに出しておらずヨレヨレだったり、膝が出ていたり、ヒジ部分がこすれてテカっていたりするようなスーツはやめておきましょう。
ブラックフォーマルではない、黒や紺、グレー、ブラウンなど暗色系の無地のワンピースに、同系色のジャケットやカーディガンを合わせます。
もしくは暗色系のスカートスーツか、パンツスーツを着用します。
ジャケットの下は、白いワイシャツやブラウスが最も適していますが、黒や紺のブラウスでも良いでしょう。
ストッキングは肌色とし、髪留めや靴などの小物は黒無地が無難ですが、喪服のときほど厳格ではありません。
手持ちの中で最もシンプルなものを選びます。
普段使いしているパンプスを着用する場合は、かかと部分が傷んでいないかチェックしておきましょう。
地味めのおしゃれ着を意識します。
喪服指定のときと同様に、男の子ならジャケットに白ワイシャツ、女の子はワンピースにボレロなどがいいでしょう。
なるべく落ち着いた色味のもの、無地に近いものを選びます。
厳密に言えば、子どもの制服は正装であり平服ではないため、平服を指定されたときは制服の着用を避けるのがベストといえます。
しかし、手持ちにふさわしい服がない場合には、制服を着せても、とがめる人はあまりいません。

法事の持ち物は、喪服であっても平服であっても同じです。以下の5つを忘れずに準備しましょう。
法事では、黒白の水引があしらわれた香典袋を使用します。
仏式の場合、四十九日法要以降の表書きは「御仏前」です。
初七日法要など、四十九日以前の法事に参列するときは、浄土真宗なら「御仏前」、それ以外の宗派なら「御霊前」となります。
神式の場合、香典の表書きは「御玉串料」または「御榊料」です。
香典は裸で持参せず、袱紗に包みます。
袱紗の色は、紫や黒、グレー、ブラウンなどの地味な色とします。
桜色、黄色などの華やかな色は慶事用なので、持たないよう注意しましょう。手持ちに袱紗がない場合は、香典を白いハンカチに包んで持参します。
仏式の法事であれば、数珠を持参します。持っていないのであれば、必ずしも持参しなくて構いませんが、日にちに余裕があるなら買い求めるのもいいでしょう。
数珠の種類は、厳密にいえば宗派によって多少の違いがありますが、施主となる人以外はそれほどこだわらなくても構いません。
初めて購入するなら、一連のシンプルなものを選ぶのがおすすめです。
また、ご実家を出て暮らしている人なら「実家に電話をして、法事の際に自分のぶんの数珠も持ってきてもらう」という手も使えます。
ご実家の仏壇には、数珠が複数眠っている可能性があります。
男女ともに、白か黒のハンカチを持参しましょう。
もしかしたら、「ついつい忘れてしまって……」と、ハンカチを持ち歩く習慣のない人もいるかもしれません。
しかし、法事に焼香はつきものです。焼香の後は必ず手を洗いたくなりますから、忘れないようにしましょう。
とくに女性の場合、香典や数珠は、黒い鞄に納めて持参します。
喪服の際はブラックフォーマル用の布バッグを使用し、平服であれば暗い色味のバッグを選びます。
チャームなど装飾品があれば、外しておきます。
男性の場合、女性が使うような布バッグは持ちません。
喪服でも平服でも、黒いセカンドバッグがふさわしいですが、数珠や香典は胸ポケットに納め、手ぶらで参列する人もたくさんいます。
以上、法事の服装について解説しました。
喪服はふだん着慣れないものなので、いざというとき「何を準備すれば?」と慌ててしまいがちです。
服装をしっかり整えたら、最後に身だしなみをしっかり整えるのも忘れずに。
ヒゲのそり忘れや、寝癖のままでの参列は、どんな服装であってもマナー違反になってしまうため気をつけましょう。
法事・法要を行うとき、お寺様へ包むお布施はどのくらいが適切なのか。
お悩みになる方も多いと思います。
この記事ではそんなお悩みを解決するために、法要別にお布施の目安を記載した一覧表をご紹介させていただきます。
合わせてお布施の用意の仕方、渡すタイミングについてもご紹介していますので、最後までご覧ください。
| お布施 | お車料 | お膳料 | |
| 初七日 | 20,000〜30,000 | 5,000 | |
| 週参り | 3,000〜5,000 | ||
| 四十九日 | 20,000〜50,000 | 5,000 | 5,000 |
| 祥月命日 | 3,000〜5,000 | ||
| 百箇日 | 10,000〜30,000 | 5,000 | |
| 盆・彼岸 | 10,000〜30,000 | ||
| 一周忌 | 20,000〜50,000 | 5,000 | 5,000 |
| 三回忌 | 20,000〜50,000 | 5,000 | 5,000 |
| 入仏式 | 10,000〜30,000 | 5,000 | 5,000 |
| 納骨 | 10,000〜30,000 | 5,000 | |
| 墓石建立 | 10,000〜50,000 | 5,000 | |
| 七回忌 | 10,000〜30,000 | 5,000 | 5,000 |
| 十三回忌 | 10,000〜30,000 | 5,000 | 5,000 |
| 十七回忌 | 10,000〜30,000 | 5,000 | 5,000 |
| 二十三回忌 | 10,000〜30,000 | 5,000 | 5,000 |
| 二十七回忌 | 10,000〜30,000 | 5,000 | 5,000 |
| 三十三回忌 | 10,000〜30,000 | 5,000 | 5,000 |
従来、葬儀も法要もお布施の金額は、地域や宗旨によって相場は異なるものでした。
しかし現在、全国的に葬儀は家族葬が主になり、法事全般も同じように縮小傾向があります。
例えば四十九日のお布施相場が、2万円〜5万円とありますが、2万円包むのか、3万円包むのか、5万円包むのか。
「一般的に○○県は、○○万円」「○○宗は普通○○万円」などは気にされず、個人のお財布事情で無理のない範囲で行えば良いと考えます。
家族が無理して行うことはお寺様も望んでいません。
一番大切なのはお寺様への感謝の気持ちです。
この感謝の気持ちは、無理のない範囲で行わない限り、生まれるはずがありません。
お車料は、お寺以外の場所で法要が行われる際、ご用意した方が良い交通費です。
相場は5千円となりますが、遠方からお越しの場合など、距離によって1万円にした方が良い場合もあります。
往復のタクシー代を目安に考えてみてください。
お寺で行う場合は必要ありません。
お膳料は、お寺様と一緒に会食を行う場合は、用意する必要はありません。
一緒に会食をしない場合、食事代として渡すのがお膳料になります。
ここで注意いただきたいのが、お寺と一緒に会食をしない場合の中には、ご家族、ご親族様自体も会食を行わない場合もあるでしょう。
そもそもスケジュールの中に会食を予定していない、読経のみで考えている法事の場合です。
この場合、お膳料を用意する必要はありません。
つまり上記の一覧表でお膳料が目安で書かれている箇所は、法事の場で会食をおこなった場合のものになりますので、会食を行わない場合は省略しても結構です。
ではお布施を包む袋はどのようなものが良いのか。
最も丁寧とされるのは、奉書紙と言われますが、あまり気にする必要はありません。
コンビニや文具店にある真っ白な封筒や「お布施」と書いてある袋で問題ありません。
お寺様へお気持ちで行うものですから、封筒の質感よりも前もって準備したことが伝わるものであれば、心がこもっているので十分です。
逆にNGなのは郵便番号欄がある封筒を使用するなど、明らかな準備不足な印象を与えてしまうものは、相手に気持ちが伝わりづらいので注意しましょう。
お布施の書き方やお金の入れ方など、用意について詳しく書いた記事が下記にありますので、よかったら合わせてご覧ください。
お布施を渡すタイミングは、特に決まりはありません。
タイミングよりも大切なのは、渡せる時に渡す、渡せずじまいで終わることがないようにするが基本です。
最も多いのは法事が始まる前に渡す方法です。
「今日は、どうぞよろしくお願いいたします」と挨拶を兼ねてお渡しすると良いでしょう。
お寺様が始まる時間ギリギリに到着して、相手に余裕がない場合は、読経終了後に渡す形が良いでしょう。
「今日はありがとうございました」とお渡しすれば、何ら問題はありません。
納棺とは、お亡くなりになられた方のお体を棺の中へ納める儀式になります。
それまでは布団の上でお休みになられているため、その姿はいつもの日常同様、眠っているように映ります。
しかし棺の中へ入る故人を見れば、非日常な光景なため、そこで初めて家族の死を実感する方も少なくありません。
死の現実を受け入れたくないと拒否反応を示していた家族が死の事実に向き合い、受け入れていくきっかけにもなる儀式です。
人が死別の悲しみから悲しみが癒えるまでの過程をグリーフワークと言いますが、そのプロセスの中でも納棺は大切な役目を果たします。
グリーフワークについての詳細は下記の記事で紹介していますので、よかったら合わせてご覧ください。
辛い場面ではありますが、お悲しみの中にいらっしゃる方々こそが参加すべき儀式であることから、主に近親者にて行います。
ですから単に棺の中に故人を移す作業ではなく、納棺を通じて故人への想いを整理する時間にもなるのです。
お亡くなりになられた方のお体を棺の中へ納める前に故人の体を洗い清める場合や、清拭を行う場合もあります。
これらは葬儀社を中心に行われますが、故人の手足、顔周りなどを家族が拭いてあげる形でご家族も参加されます。
身なりを整えた後にお棺へと納め、愛用品など思い出の品を棺の中へ副葬品として入れます。
お棺の中へ入れて良いものは、下記の記事で詳しく紹介していますので、合わせてご覧ください。
本題の納棺はいつ行うのかという疑問についてこれからは解説させていただきます。
結論から申し上げますと納棺を行うタイミングに決まりはありません。
ですからこのタイミングで行うべきという特定のマナーや決まり事はありません。
そもそもお棺に故人を納める目的は、故人をお棺に納めた状態でないと火葬ができないためです。
つまり決まりごととして存在するのは、火葬場到着時に納棺した状態であること、
言い換えれば火葬場到着までに納棺を済ませておけばいいと解釈できます。
火葬場へ出発する、出棺までの間のどこかのタイミングで納棺を行えばよいということです。
しかしながら葬儀の形式など様々な要因でこのタイミングで行った方が良いということもあります。
次項で解説させていただきます。
一般的な葬儀の形式として最も多いのが通夜式・葬儀告別式と2日間にわたって行われる形式です。
この場合、納棺は通夜式前に行われます。
例えば18時から通夜式がある場合は、15時〜16時頃の2〜3時間前に行われることが一般的です。
これは納棺の所要時間として30分〜60分、時間が早すぎると身内が集まりづらい、遅すぎると通夜式へ影響が出る、などが考慮されています。
とはいえ葬儀の形式、日程、地域性、家族の状況によっても納棺を行うベストなタイミングは異なります。
例えば今日お亡くなりになられた方の通夜式が明日行われるとします。
この場合、明日行われる通夜式の2〜3時間前に納棺することもあれば、本日中に納棺を行うこともあります。
いずれも通夜式前に行うということに変わりはありませんが、今日なのか明日なのかで日程が異なります。
今日でも明日でも構いません、納棺は冒頭でご説明した通り、とても大切な儀式ですから、通夜式の前にご家族がお揃いになるタイミングで行うと良いでしょう。
葬儀社がご家族の揃うタイミングや都合を伺い、それに合わせてスケジュールを調整してくれます。
ご逝去後、葬儀社へ連絡すると葬儀社が駆けつけますが、このタイミングで納棺とはなるケースは非常に稀です。
つい先ほどまでご存命だった方ですから、亡くなるとすぐに納棺というのは、家族にとってとても残酷なことです。
また、病院でお亡くなりになった場合、他の患者様の目もありますから、病院内に棺を持ち込むことはあまりありません。
通常はシーツにお体を包み、ご安置場所までストレッチャーで搬送、そしてお布団にご安置となります。
稀なケースですが、死後かなりの日数が経過しているなどの場合は、布団にご安置が困難なため、すぐに納棺が行われることもあります。
「納棺は通夜式前に行われることが多い」とされてきましたが、最近ではこの説明だけでは不十分になってまいりました。
通夜式が行われない葬儀の形が増えつつあるためです。
ここでは通夜式が行われない葬儀の場合、納棺はいつ行うものなのかを解説させていただきます。
宗教的儀式を行わず火葬のみを行う直葬という形式の場合、納棺のタイミングは様々です。
火葬場へ向かうご出棺の時刻までに納棺を済ませておけば良いことになりますので、特に決まりはありません。
ご出棺時間直前に納棺を行うこともありますし、火葬前日に行うこともあります。
近親者の家族が揃ったタイミングで行うと良いでしょう。
通夜式がないのは、考え方によってはメリットもあります。
火葬前日の晩に納棺を済ませておかなければいけないという決まりはないため、火葬前日の最後の夜もお布団へ安置のまま過ごすことができます。
故人の側に布団を敷いて一緒に川の字でお休みいただくことも可能になります。
それが住み慣れたご自宅であれば、とても思い出に残る一夜になり得ることもあります。
一夜が明けて翌日、ご出棺前に家族で納棺を行うという形でご出棺も素敵だと思います。
通夜式を行わず、葬儀告別式のみを行う一日葬という形も近年増えつつあります。
この場合の納棺のタイミングは、通夜式がないため、葬儀告別式が始まるまでに納棺を行う形になります。
葬儀が始まる前にではいつ行うのかは、近親者の家族が集まる時間帯を考慮することと、もう一つ考えることがあります。
直葬火葬のみの時と同様に、火葬前日の晩を家族がどういう形で過ごしたいか、というものです。
一日葬のメリットは、通夜にあたる1日目は宗教的儀式が行われないため、リラックスして普段通りに過ごせることが挙げられます。
喪服を着用する必要もありません。
いつもと変わらない家族団欒の1日を最後に経験できます。
納棺を行い、棺が目の前に登場すれば、それは日常ではなく、非日常な光景となってしまうでしょう。
1日目はリラックスして過ごす、2日目は納棺を行って儀式を行うというメリハリをつけるのも一つの方法です。
散骨に興味はあるけれど、どのような散骨方法なら違法とならないのか、わからないという人は多いのではないでしょうか。
「故人の遺言に、散骨してほしいと書いてあった」
「海が好きだった父のために、少しだけでも海へ遺骨を還してあげたい」など、散骨をしようと考える人の事情はさまざまです。
散骨は、気をつけて行わないとトラブルにつながる恐れがあります。
違法とならない4つの方法と、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
まずは、違法になってしまう散骨とは、どういう場合なのかを押さえておきましょう。
違法となるのは、以下の場合です。
遺骨を、墓地と認められていない場所に埋めると、「墓地、埋葬等に関する法律」に違反してしまいます。散骨は、あくまで遺骨を「撒く」行為です。
他の人が所有している土地に、無許可で散骨すると、トラブルになる可能性が高く、謝罪で済まされなかった場合は訴えられてしまうかもしれません。
訴えられると、何らかの法律に違反したと判断されてしまう可能性は高いでしょう。
日本には、条例で散骨が禁止されている自治体が複数あります。
よく調べずに散骨すると、条例違反になってしまう恐れがあります。
「散骨」と銘打って、ただ遺骨をうち捨てるように撒いてしまうと、遺棄罪等に問われる可能性があります。
心を込めて、弔いとして遺骨を撒くことが、散骨を行う人の姿勢として求められます。

散骨は、賛成派もいれば反対派もいる弔い方です。法律に違反していない散骨であっても、以下のようなマナーを守らないと、他の人とトラブルになるケースがあります。
撒かれた遺骨を見かけた人が「何かの事件では?」と驚くことのないよう、遺骨はパウダー状になるまで粉砕します。
故人との思い出の場所だからと、人が集まる場所で、目につくように散骨すると、多数の人の気分を害してしまうかもしれません。
漁場の近くで散骨する姿を誰かが見かけると、風評被害などにつながる恐れがあります。
パウダー状の遺骨は、風に舞ってさまざまな場所へたどりつきます。
「自宅なら大丈夫」と黙って散骨するのではなく、遺骨が飛んでいってしまうかもしれない近隣に、しっかり許可を取りましょう。
遺骨と一緒に、花や飲み物をお供えする姿が見られます。
花束を包むビニールや、飲料のペットボトルをそのまま海や山にうち捨てると、環境によくありません。
自然に還らないものは、撒かないのがマナーです。
【参考】「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」研究報告書より
それでは、違法やトラブルにならない散骨方法には、何があるのでしょうか。
場所別に、4つをご紹介します。
また、それぞれの方法のメリットやデメリットについても、合わせて解説します。
日本の散骨の多くが、海で行われています。人の目の届かない遠方まで船で出かけて、水面へ遺骨やお花を撒きます。
海への散骨は、「海洋散骨」と称されています。
世界のどこへでもつながっている、大いなる海に眠れることや、陸よりも散骨可能な場所が豊富であることがメリットです。
一方で、船を持っている人は少ないため、業者を通さなければならないというデメリットもあります。海洋散骨については、以下の記事に詳しいので、参考にしてください。
山一つ分が自分の所有地である場合には、あまり他人に迷惑をかけずに散骨が可能です。
また、山への散骨を行っている業者も、少ないながら存在します。
もともと散骨に興味のあった人が、所有地を散骨場所として整備したり、寺院が広大な墓地の一部を散骨場所としていたりと、かたちはさまざまです。
メリットは、花や草木に守られ、大地の循環を感じながら眠れることといえるでしょう。
海洋散骨よりも撒いた場所がわかりやすいため、命日などに合わせて訪れるといったことも可能です。
デメリットは、陸への散骨はどうしても遺骨が風に舞ってしまいやすいため、他人の土地に遺骨が飛んでしまう可能性があることです。
「飛んできた白い粉は一体何?」と、問い合わせを受けるかもしれません。
散骨に反対する意思のない人でも、ある日突然白い粉が洗濯物にたくさん付着し、それが他人の遺骨だと分かったら、かなりショックでしょう。
空への散骨は、「バルーン葬」や「宇宙葬」と呼ばれ、それぞれ行う業者が存在します。
「バルーン葬」は、大きなバルーンに遺骨を納め、大空に飛ばす方法です。
バルーンは空高く上がり、成層圏付近で膨張して破裂し、宇宙空間へ散骨されます。
空に憧れを抱く人であれば、バルーン層のメリットは大きなものとなるでしょう。
一方で、安全性の面で打ち上げができる場所に条件があることや、実施できる業者が少ないことがデメリットとなります。
「宇宙葬」は、人工衛星などに少量の遺骨を搭載する方法です。
遺骨は、人工衛星の寿命が尽きるまで、地球を回り続けることになります。
宇宙葬のメリットは、やはり宇宙に強い憧れがある人にとってぴったりの葬法であること。
デメリットは、打ち上げの機会が少ないことや、ほんの少量しか宇宙に行けないため、他の遺骨の弔い方を考えなければならないことです。
また、行っている業者がかなり少ないのも、デメリットの一つです。
故人と行った思い出の国や、「いつか一緒に行きたいね」と話していた国へ出かけて、散骨するという方法があります。
ただ、海外においても法律や条令などで散骨が禁じられているケースがあるため、海外散骨を行っている業者に依頼するのが安心です。
海外散骨のメリットは、思い出や憧れのある国で散骨できることです。
「故人と最後の海外旅行」と考えれば、素敵な想い出になるでしょう。
デメリットは、トラブルに巻き込まれたとき、言葉や文化の違いで苦労すること。
自力で海外散骨するときには、十分慎重になりましょう。
この記事では、違法やマナー違反とならない散骨方法についてお伝えしました。
マナーを守って散骨できれば、自力でも行えます。
しかし、とくに遺骨をパウダー状にすることなど、越えなければならないハードルはあります。
散骨が一般的な葬法として認知されつつある今、安全、安心に実施してくれる業者が多数出てきています。
希望の場所に散骨を行ってくれる業者が見つかったら、まずは相談してみてはいかがでしょうか。
信頼できる業者かどうか、やりとりをしたうえで見極めましょう。
ご相談は無料
24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも
フリーダイヤルへご連絡ください。
「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は
メールでのご相談も可能です。
ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
